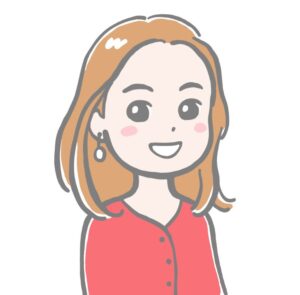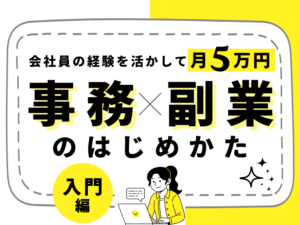あなたは、「開業届」という言葉を耳にしたことがありますか?
会社員をしながら副業をしている場合にも、副業でやっているビジネスは立派な「個人事業」です。
つまり、もう既に副業を始めているあなたは、立派な個人事業主なのです。
このため、副業を始めたら、税務署に開業届を提出し、事業を開始したことを届出する必要があります。
この記事では、副業で売上が上がった方や売上が得られそうな見込みが立った方のために、開業届の提出をはじめとした副業に必須な手続きを解説します。
副業の中身だけでなく、副業を進めていく上で必要な手続きも、並行して抜かりなく進めていきましょう。
副業をはじめたら、開業届を出そう
開業届とは何か?
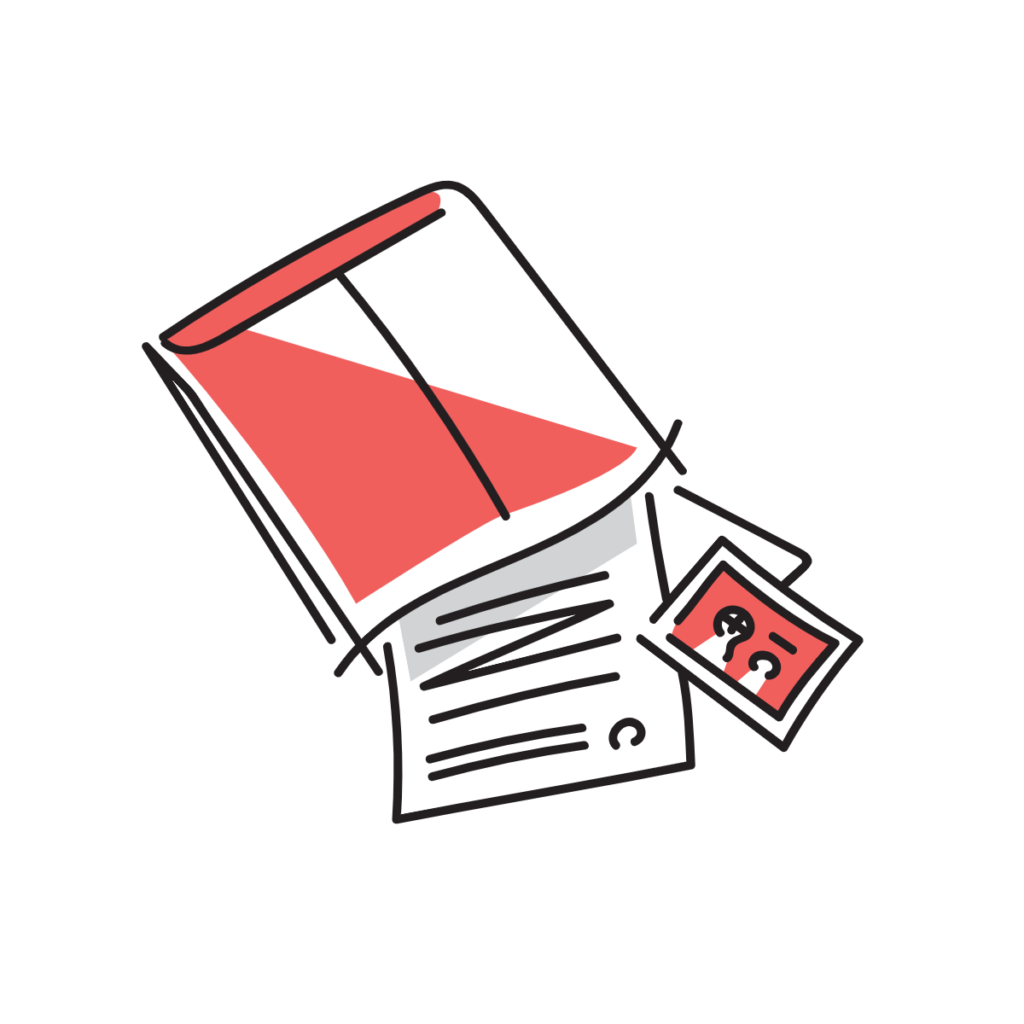
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。
副業を始めたら、開業届を出す必要があります。
事業の開始という観点では、副業か本業かは区別がありません。
会社員の副業でも、開業は開業です。
開業届を提出するタイミングは?
国税庁のホームページでも、「事業を開始してから1カ月以内」に提出することと記載されています。
翌年の2月に確定申告があることを念頭に、適切なタイミングで開業届を提出しておきましょう。
わたしは最初の売上が得られたタイミングで、開業届や青色申告承認申請書を提出しました。
開業届を届出するタイミングに迷う人は、スポット対応が可能な税理士さんに相談して決めるのが良いと思います。
開業届は出さないとダメ?
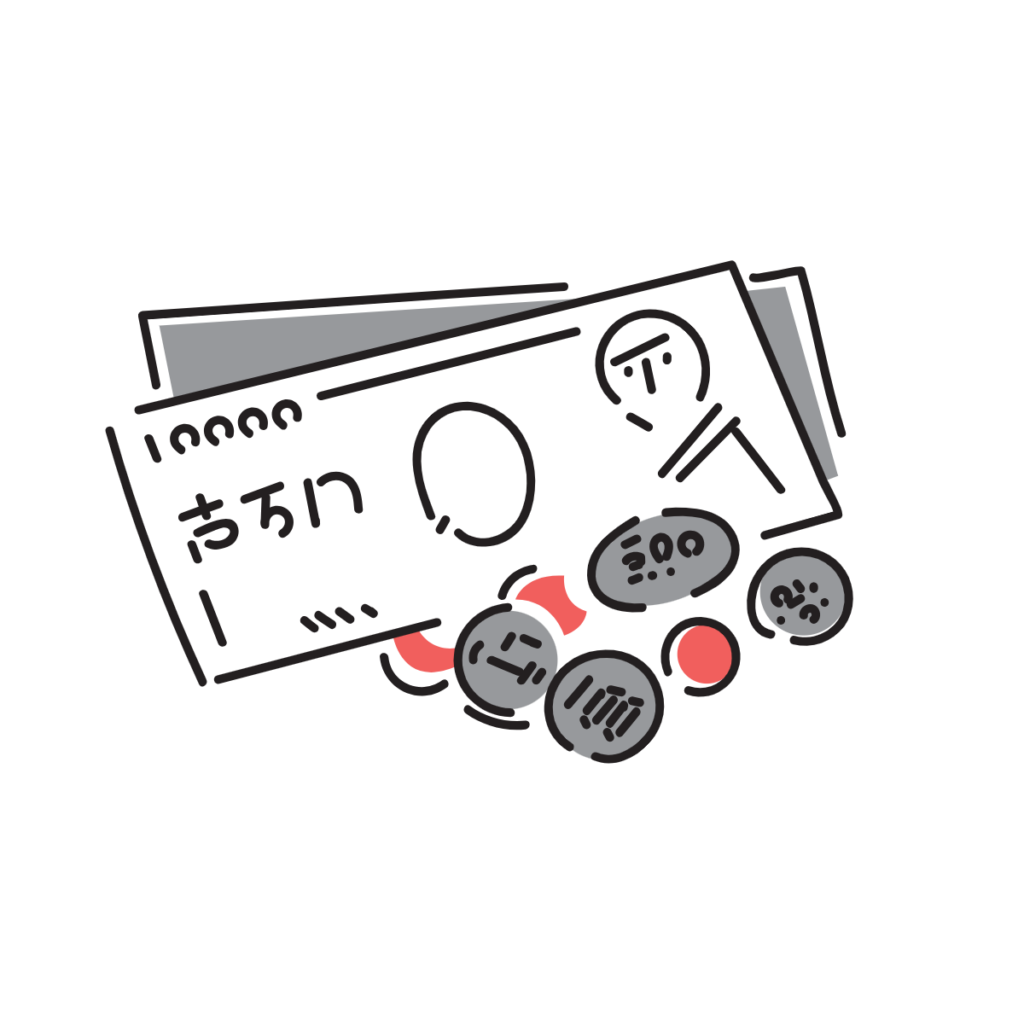
開業届を出さないことによる罰則規定やはありません
ですが、青色申告で確定申告をする場合は開業届の提出が必須です。
国や地方自治体が募集している補助金を申請するときにも、個人の場合は「開業からX年以内」などされ、開業していることを要件としているケースが多いです。
開業届を提出していなくても副業はできますが、開業届を出した方が金銭的な理由で有利に働くことが多いです。
副業をはじめた方は、開業届とセットで青色申告承認申請書を提出しておくのがお勧めです。
副業の年間所得が20万円を超えたら、確定申告が必要
年間所得(1月1日〜12月31日)が20万円以下の場合は、副業をしていても確定申告をしなければなりません。
所得とは、副業で得た売り上げから経費を差し引いた金額です。
例えば…
- 売上が30万円、経費が20万円の経費の場合は、所得は10万円となり、確定申告は不要です。
- 売上が30万円、経費が2万円だった場合、所得は28万円となり、確定申告が必要となります。
副業で成果を上げられた場合、その年は確定申告が必要になる可能性が高いです。
特に事務副業は、ルーティン業務の案件が獲得できると、継続的に売上があがることに繋がり、確定申告になる可能性が高いことは認識しておきましょう。
【参考】住民税の申告は別物

副業で得た収入が20万円以下で確定申告の必要がなくても、それは所得税に限っての話です。
1円以上の収入があるの場合には、住民税の申告は必要になります。
会社によっては、副業を禁止しているケースもあります。
住民税によって副業の事実が勤務先に知られる可能性があるため、住民税の申告には注意が必要です。
💡 会社にバレずに副業するためのポイントが知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

ところで「青色申告」って何?
個人事業主やフリーランスの期末の大仕事として、確定申告があります。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告と青色申告それぞれのメリット・デメリットが異なり、提出すべき書類や控除を受けられる金額、控除の要件なども異なります。
白色申告とは?
事業所得を申告する際に、簡易な手続きで提出できるやり方です。
簡単な帳簿(収支内訳書)の作成が求められますが、詳細な複式簿記での記帳は不要で、税務署への事前届出も不要で、誰でも選択できます。
メリット
- 手続きが簡単で、帳簿作成の負担が軽い
- 事前申請の必要がないため、すぐに利用できる
- 最大で10万円の所得税控除を受けることができる
デメリット
- 青色申告に比べて税制上の優遇が少ない(青色申告特別控除がない)
- 損失の繰越ができない
青色申告とは?
事業所得の申告において、複式簿記を用いることで、税制上の大きなメリットを受けることができる制度です。
ただし、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。(通常、年度の開始から2か月以内)
また、確定申告の際には、詳細な帳簿(複式簿記)を作成し、貸借対照表や損益計算書の提出が求められます。
メリット
- 青色申告特別控除:65万円または10万円の特別控除が受けられる
※65万円控除は電子申告が必須、電子申請を利用しない場合は55万控除となる - 赤字が発生した場合、翌年度以降3年間まで繰り越せる。また、前年度に黒字であれば、繰戻して税金の還付を受けることも可能
- 家族への給与(専従者給与)の経費計上が認められる
- 資産の減価償却などの適用範囲が広い
デメリット
- 白色申告に比べると、帳簿作成や申告手続きが複雑で手間がかかる
- 事前申請が必要なため、申告を始める時期を計画的に判断する必要がある
白色申告と青色申告、おすすめはどっち?
白色申告も青色申告も、帳簿をつけなければいけないことに変わりはないので、せっかくなら控除金額が大きい方(=節税効果が高い方)を選んでおくのがお勧めです。
ただし、青色申告には複式簿記での帳簿作成が必要となります。
これまでに経理業務を経験したことのない方や簿記の勉強をしたことがない方であれば、青色申告を選択しつつ、簿記3級程度の知識を身に付けておくことをお勧めします。
 りか
りかわたしも、副業時代に開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しましたよ!
開業届・青色申告承認申請書を提出するにはどうすれば良い?
開業届と青色申告承認申請書の提出方法は3パターンあります。
一度しかやらない手続きですので、自分が一番簡単にできるやり方で済ませてしまうのが良いと思います。
【提出方法①】税務署の窓口に持参又は郵送する
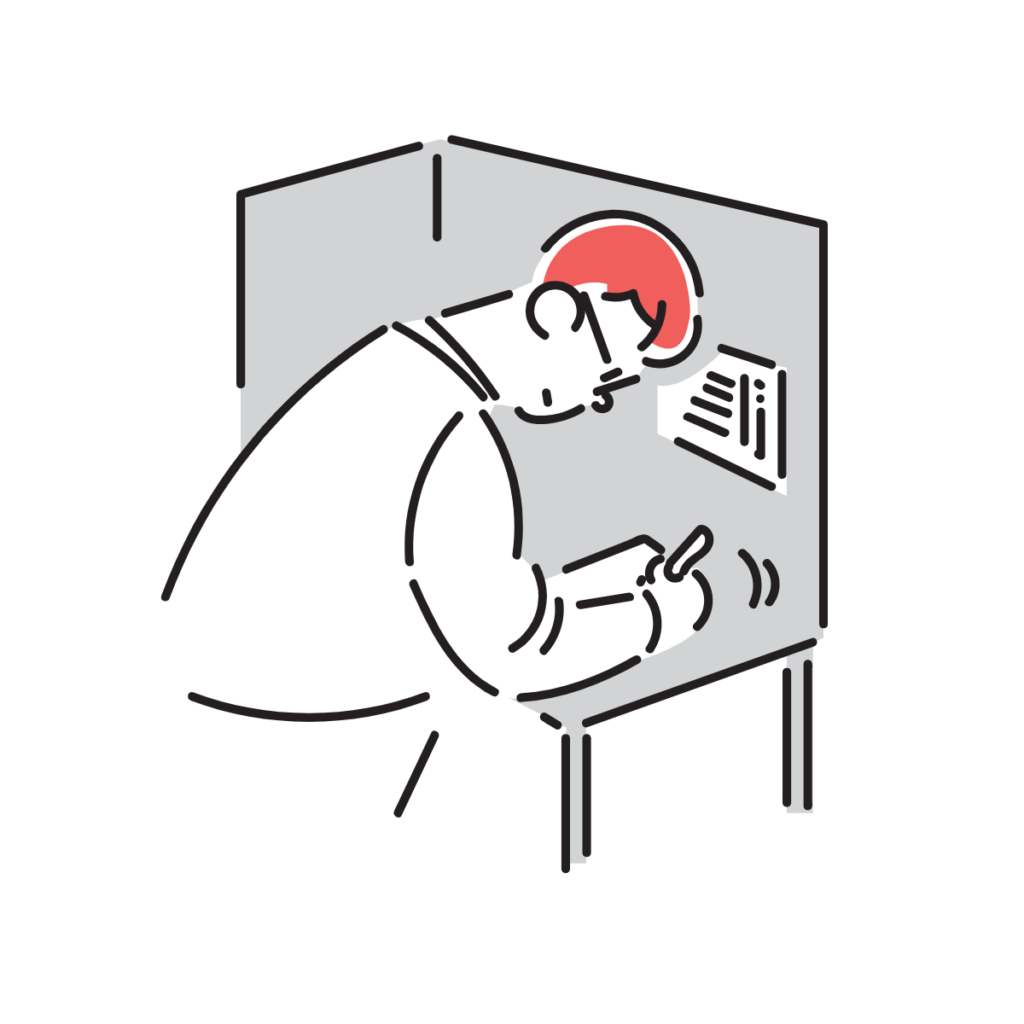
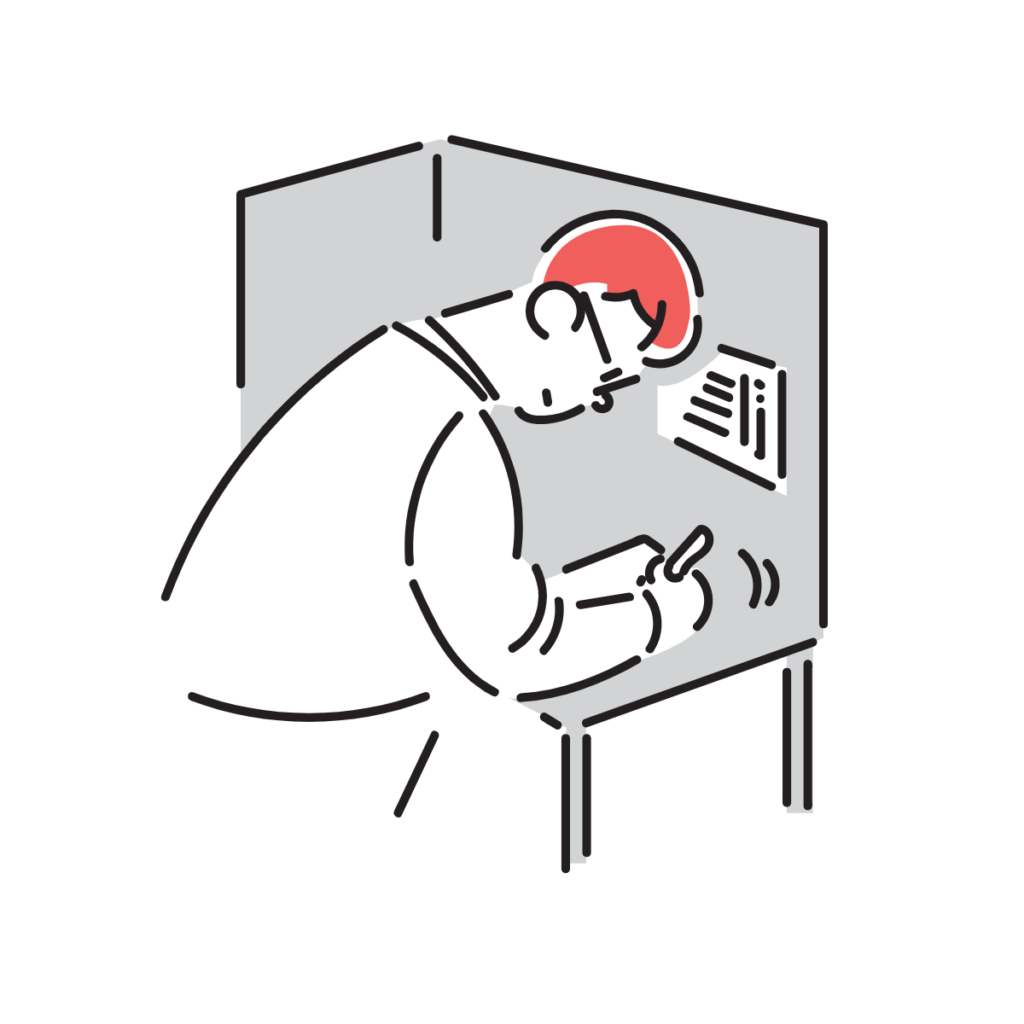
青色申告承認申請書と開業届は、通常はセットで管轄の税務署に提出します。
どちらも、国税庁のホームページからダウンロードし、印刷して手書きするか、PDFファイルに必要事項を入力し印刷します。
提出時は管轄の税務署に持参するか、郵送で提出することもできます。
紙で申請する場合は、2枚準備しておくことをお勧めします。
同じ内容で2枚作成し提出すると、1枚は回収されてしまうのですが、もう1枚は受付印を押して「控え」として返却してもらえます。
※郵送で提出する場合で「控え」が欲しい場合は、切手を貼った返信用の封筒かレターパックも同封しましょう。
【提出方法②】電子申請する(E-tax)
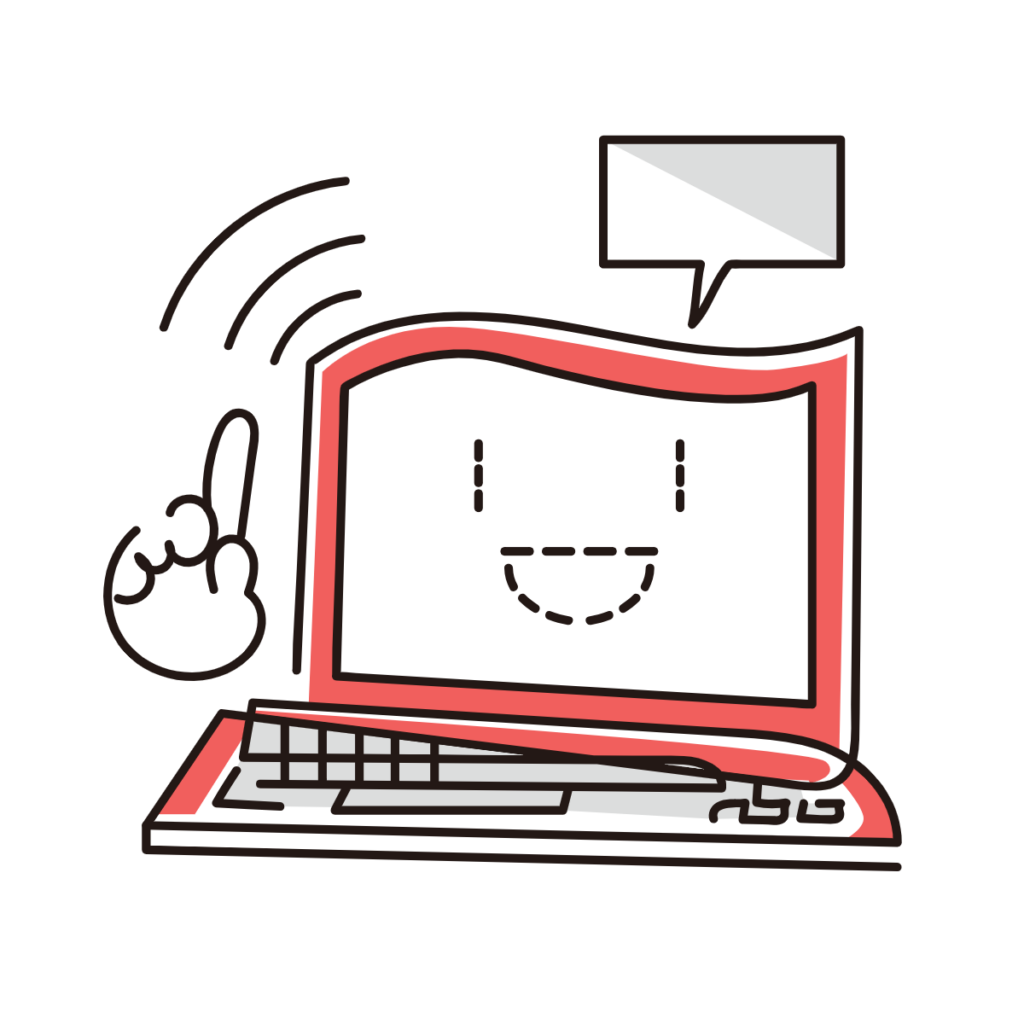
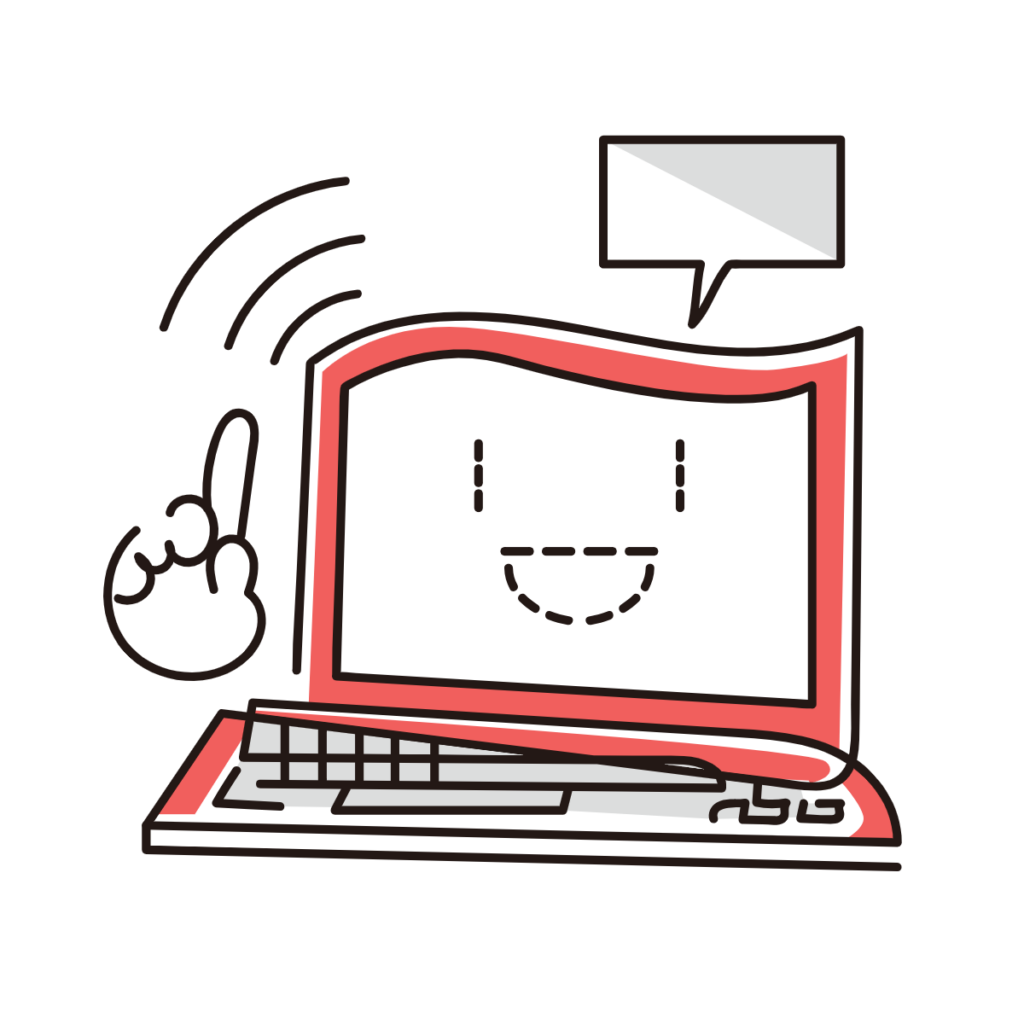
E-Taxという、国税庁のポータルサイトから電子申請することが出来ます。
既に、ふるさと納税や医療費控除等で確定申告をしたことがある方は、E-taxのアカウントを持っていて、そのままお使い頂くことが出来るかもしれません。
もしE-taxを一度も使ったことがない場合も、開業のタイミングでE-taxのアカウントを作っておいても良いと思います。
ただし、E-taxから電子申請を行う場合には、マイナンバーカードによる電子署名が必要です。
マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバーカードを作るところから始める必要があります。
マイナバーカードはお住まいの区市町村の窓口で作成することができますが、申請から発行までに約1ヶ月かかる自治体が多いです。
このため、開業届と青色申告承認申請書を提出する時点でまだマイナンバーカードを持っていない場合は、E-tax以外の方法で申請することをお勧めします。
【提出方法③】電子申請する(会計ソフト)
開業届を提出する時点で既に会計ソフトを導入している場合は、会計ソフトから開業届と青色申告承認申請書に対応しています。
会計ソフトごとに対応が異なるので、お使いの会計ソフトのヘルプページを参照しながら進めてみてください。
freee会計、マネーフォワード確定申告、やよいの青色申告オンラインが個人向けの会計ソフト3強です!



開業後にご自身が使用予定の会計ソフトを使われるのが良いと思います。
開業に必要な事務手続き(まとめ)


会社員であっても、副業を始める際に開業届を提出する必要なこと、また開業届と青色申告承認申請書を提出するメリットについてお伝えしました。
開業届を出すことで青色申告を利用できるようになり、確定申告の時に、税務上のメリットが得ることが出来ます。
ただし、翌年の確定申告のタイミングでは、複式簿記で作成した帳簿と決算書類が必要になります。
経理経験のない方や簿記の知識がない方は、これを機に簿記3級程度の知識を学んでおくことをお勧めします。
開業届を提出して以降は、廃業しない限りはほぼ毎年確定申告をすることになるでしょう。
副業を始めた今のタイミングで簿記の知識も習得し、なるべく自社経理がスムーズに進むようにしておきましょう。
💡 副業や個人事業主の会計ソフトに関して、基本的なことを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。詳しく解説していますので、参考にしていただけると嬉しいです!


💡 マネーフォワード確定申告の使い勝手に興味のある人は、こちらの記事を参考にしてみてください。



-1024x1024.png)