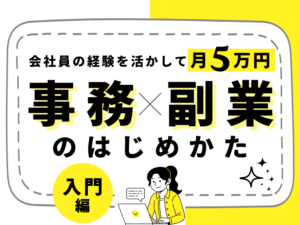会社員であっても、副業を始めて売上が出来はじめたなら、それはもう立派なビジネスです。
売上を管理したり、副業にかかった経費を精算するためには、会計ソフトを使うのが一般的です。
この記事では、副業を始めたばかりの方のために、会計ソフトの必要性と、どんな会計ソフトを選べば良いのか、おすすめのソフトをご紹介します。
副業で売上が上がった方や売上が得られそうな見込みが立った方は、ほぼ間違いなく、会計ソフトの契約が必要となります。
副業を始めた今のタイミングで、自社経理がスムーズに進むように抜かりなく準備しておきましょう。
なぜ会計ソフトが必要なのか?
副業で始めた個人のビジネスになぜ会計ソフトが必要なのでしょうか?
会計ソフトを導入する目的は大きく分けて2つあります。順番に見ていきましょう。
【目的①】事業の収支を把握するため
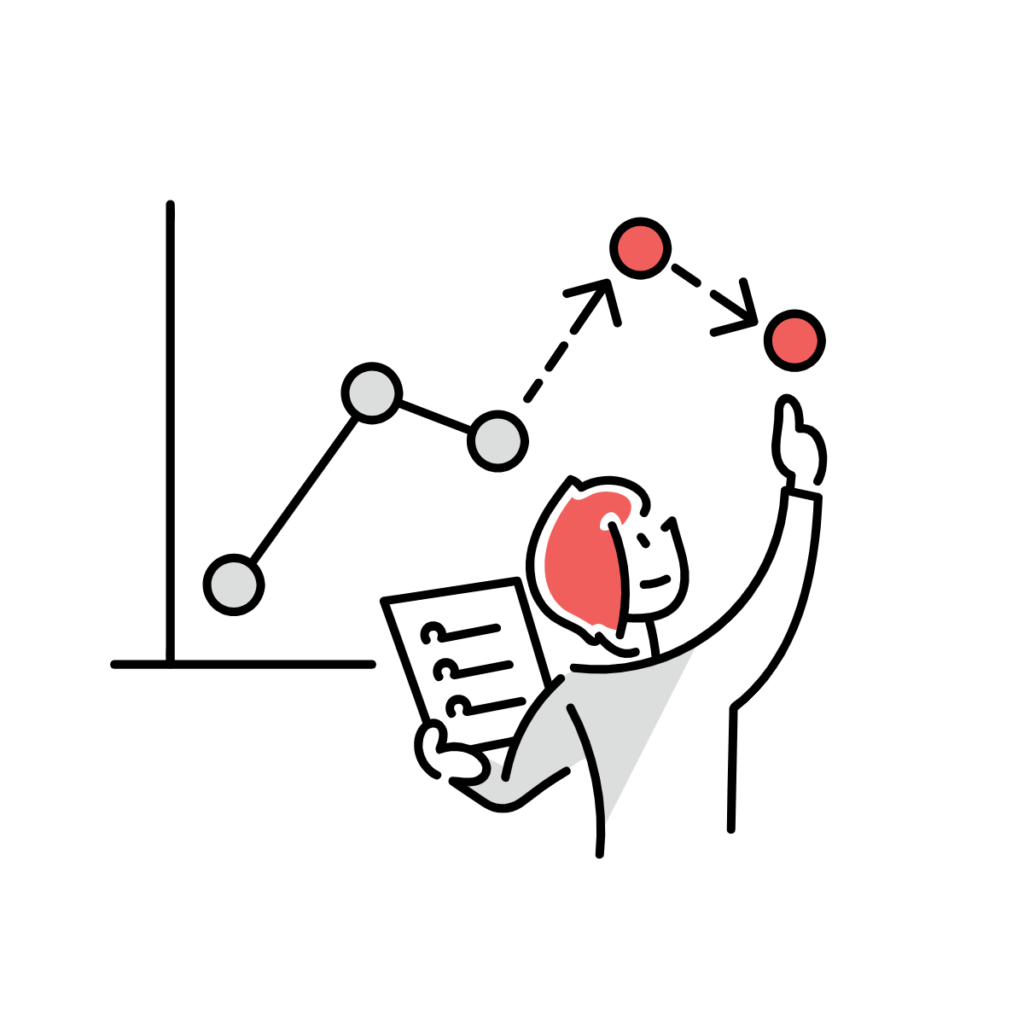
個人事業主として自身の収支を把握するために、会計ソフトを導入するのがお勧めです。
会社員をしながら副業をしている場合にも、副業でやっているビジネスは立派な「個人事業」です。
事業の収支を把握するためには、帳簿を付ける必要があります。
EXCELや手書きノートでも管理できなくはないとは思いますが、今は、クラウドで使える便利な会計ソフトが出回っているのですから、せっかくなので会計ソフトを使ってスムーズに管理をしましょう。
【目的②】確定申告の時に複式帳簿を提出する必要があるため

開業届とセットで青色申告承認申請書を提出している場合は、翌年の確定申告のタイミングで複式簿記で作成した帳簿と決算書類が必要になります。
副業を始めたら、税務署に開業届を提出し、事業を開始したことを届出する必要があります。
そして、開業届を提出する際には、青色申告承認申請書を提出することで、最大65万円の所得控除を受けることができます。
これは、確定申告の時に得られる税務上の大きなメリットですので、使わない手はないです。
開業届と青色申告、そして会計ソフトはセットで準備を進めるのが良いと思います。
💡 「開業届って必要?」「青色申告って何?」と疑問に思った方は、こちらの記事をご覧ください。開業届や青色申告に関して詳しく解説をしていますので、参考にしていただけると幸いです。

会計ソフトはいつから契約すれば良いの?
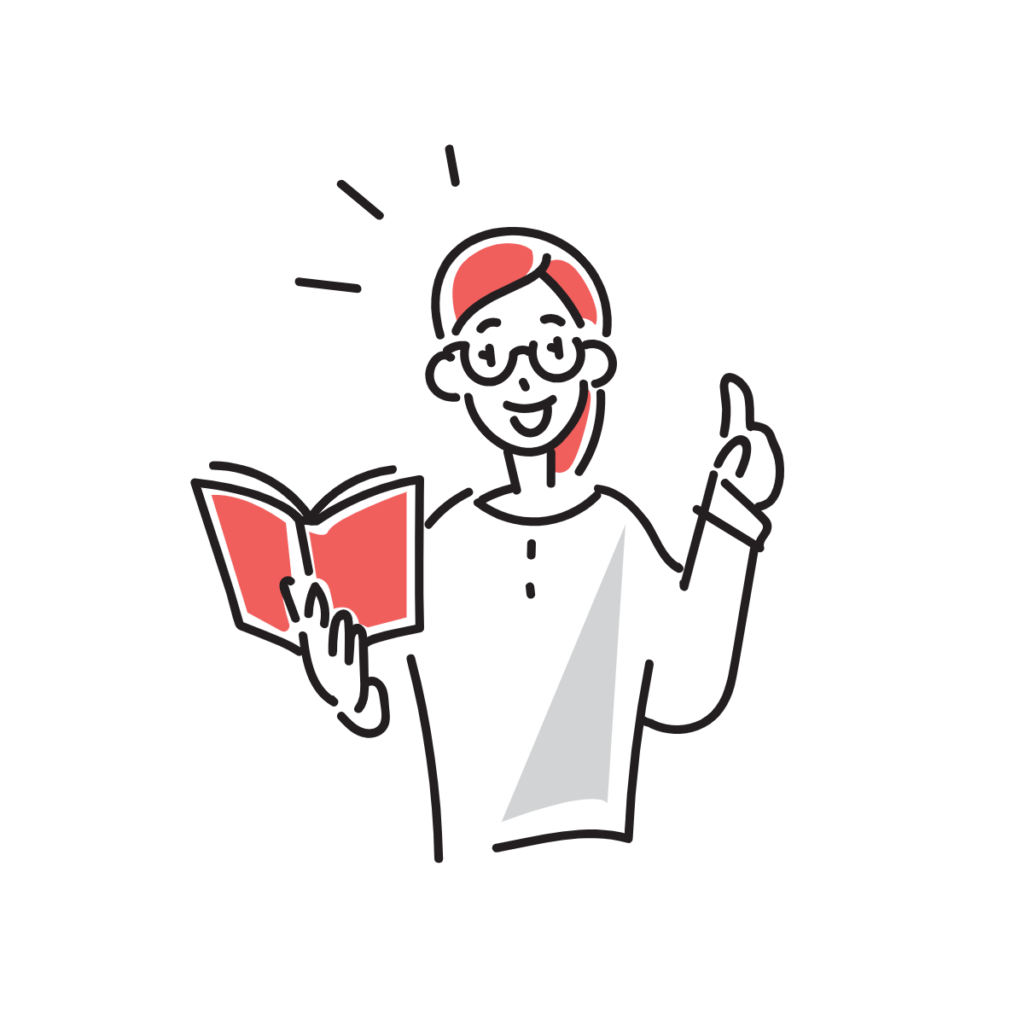
事業の収支を管理するのが目的なので、売上が1円もできていなくても、本来的には、事業を始めた段階で会計ソフトを導入しておくべきでしょう。
ただし、現実問題として、会計ソフトを導入すると毎月数千円単位でのコストがかかります。
売上が出ない時期が数か月~年単位で続いて、毎月会計ソフトの料金だけが固定的に発生するのは経済的にも精神的にも負担になると思います。
このため、わたしがお勧めするタイミングは、副業で継続的に売上が発生する見込みが立った時か、売上が発生した直後でも良いと思います。
もしくは、既に開業届と青色申告承認申請書を提出している場合は、まだ売上が発生していなくても、会計ソフトの契約をしましょう。
 りか
りか年末に近づいてから開業届と青色申告承認申請書を提出した場合は、確定申告を見据えて、速やかに会計ソフトを契約しましょう
会計ソフトを契約しよう
会計ソフトの必要性を理解し、自分が会計ソフトを導入するべきタイミングが見えてきたら、次は実際に何のソフトを導入するかを検討しましょう。
おすすめの会計ソフト3選


大手の会計ソフトで有名なのは、以下の3つのサービスです。
クラウド会計ソフト3選
この中でも、freee会計は簿記の知識がない人にも使いやすいように作られているのが特徴です。
家計簿に近い感覚で取引を入力すると、freee会計のシステム内で自動的に複式簿記の仕訳を生成してれる仕組みなのです。
わたしの周囲では、個人事業主の中ではfreee会計のシェアが一番大きいです。
一方で、簿記の知識がある人には、freeeの入力方式は煩わしいと感じる人もいると聞きます。
実は、わたしもその一人で、わたしは開業以来、3年以上ずっとマネーフォワード確定申告を使っています。
クライアントワークでは、ベンチャー2社でfreee会計を使っていますが、複式簿記の仕訳で直接登録した方が分かりやすいと感じるときもあります。
なお、同じ事務職でも「経理ガチ勢」の人は、会社の経理業務で弥生会計を使っているケースが多く、弥生会計に馴染みのある人も多いようです。
大手であれば、どのサービスを利用しても「確定申告」という目的を果たすことができますので、あなた自身の経理経験に合わせて、一番使いやすいと思う会計ソフトを導入すれば問題ないと思います。



同業種・異業種を含めて、まだマネーフォワードを使っているフリーランスの人には会ったことがありません!
💡 簿記3級程度の知識がある方には、マネーフォワード確定申告をお勧めしたいです。3年間使ってきて感じたことをレビュー記事にまとめていますので、ご興味のある方はこちらの記事を参考にしてみてください。


💡 家計簿アプリ「マネーフォワードME」で自分のお財布全体を管理する方法をお伝えしています。事業費だけでなく家計管理もしたいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。


おすすめの支払方法はクレジットカード払い


ご自身がどの会計ソフトを導入するかを決めたら、申込みの手続きを済ませてしまいましょう。
支払方法は、クレジットカード払いを選択しておくのがお勧めです。
一度会計ソフトを申し込んだら、個人事業を廃業するまで、使い続けることになります。
このため、クレジットカード払いにしておけば自動で契約が更新されるから安心です。
月額契約と年間契約はどっちがお勧め?
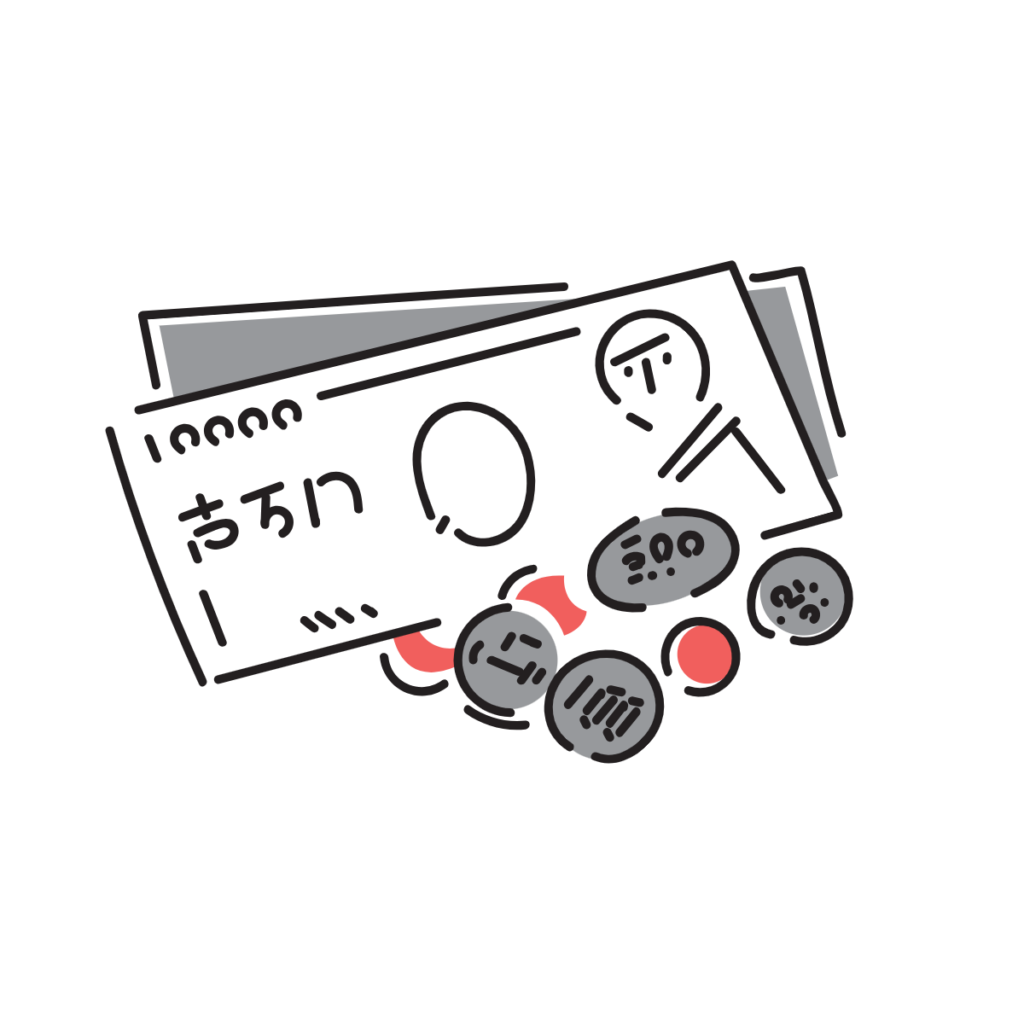
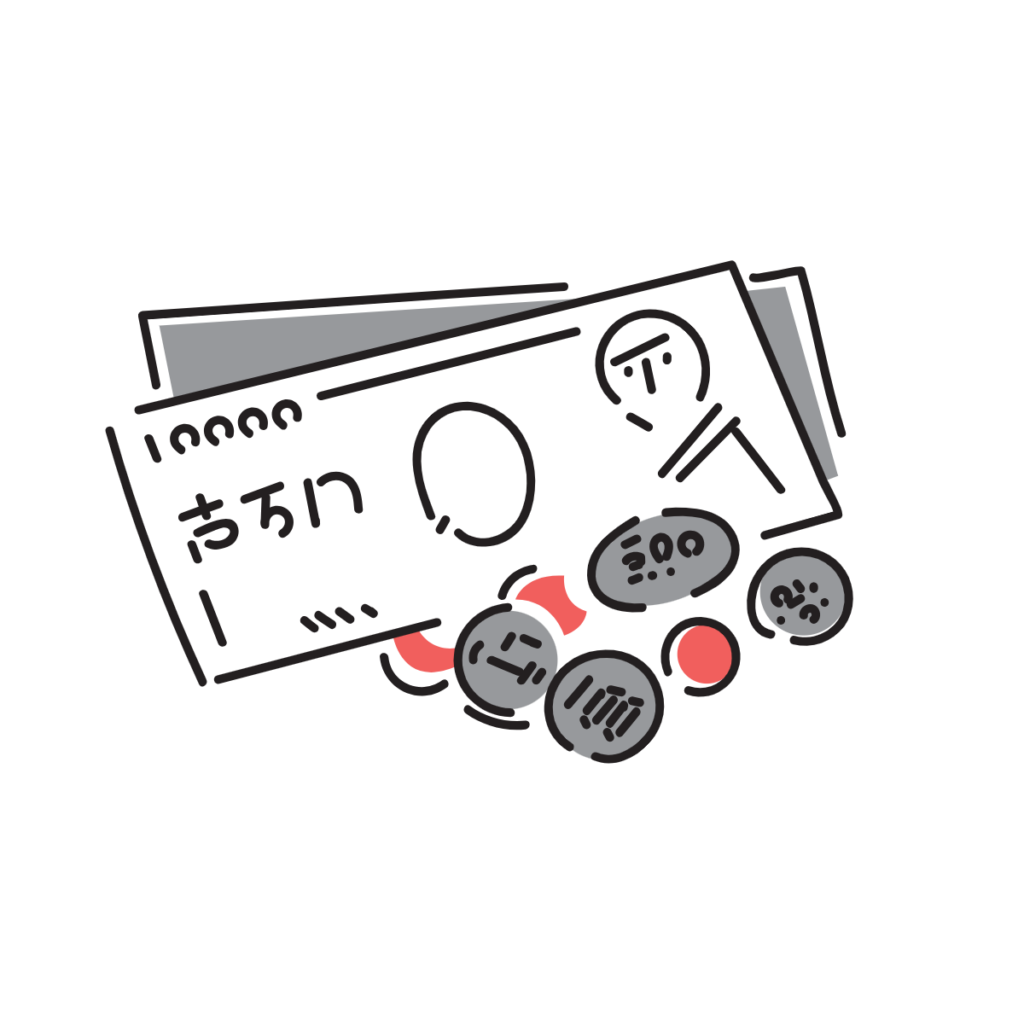
契約期間ですが、月額契約と年間契約が選べる場合は、年間契約を選択するのが良いと思います。
年間契約の方が割安になっているケースが多いのと、会計処理が年1回で済むメリットがあります。
ただ、一度に年間契約をするのに抵抗がある方も、いらっしゃるのではないかと思います。
そういう場合は、多少割高でも月額契約を選択しましょう。
こんな方には月額契約がお勧め
- まだ経理処理に自信がなく、継続的に使い続けることに不安がある方
- 副業を始めたばかりで続けられるかどうか不安を感じている方
- 会計ソフト自体を複数使ってから決めたいと思っている方



わたしも会計ソフトを契約した当初は月額契約から始めて、自信が出てから年間契約に切り替えました💡
会計ソフトの初期設定を終わらせよう
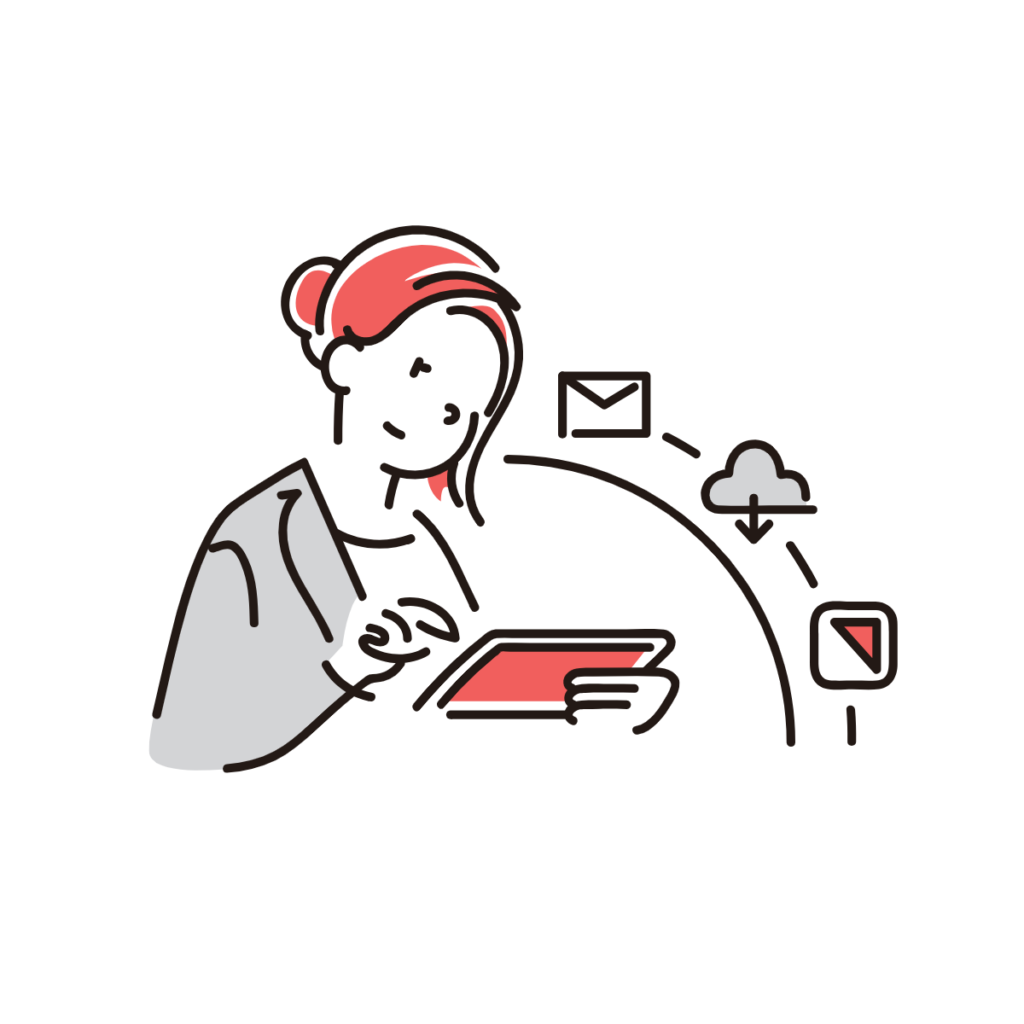
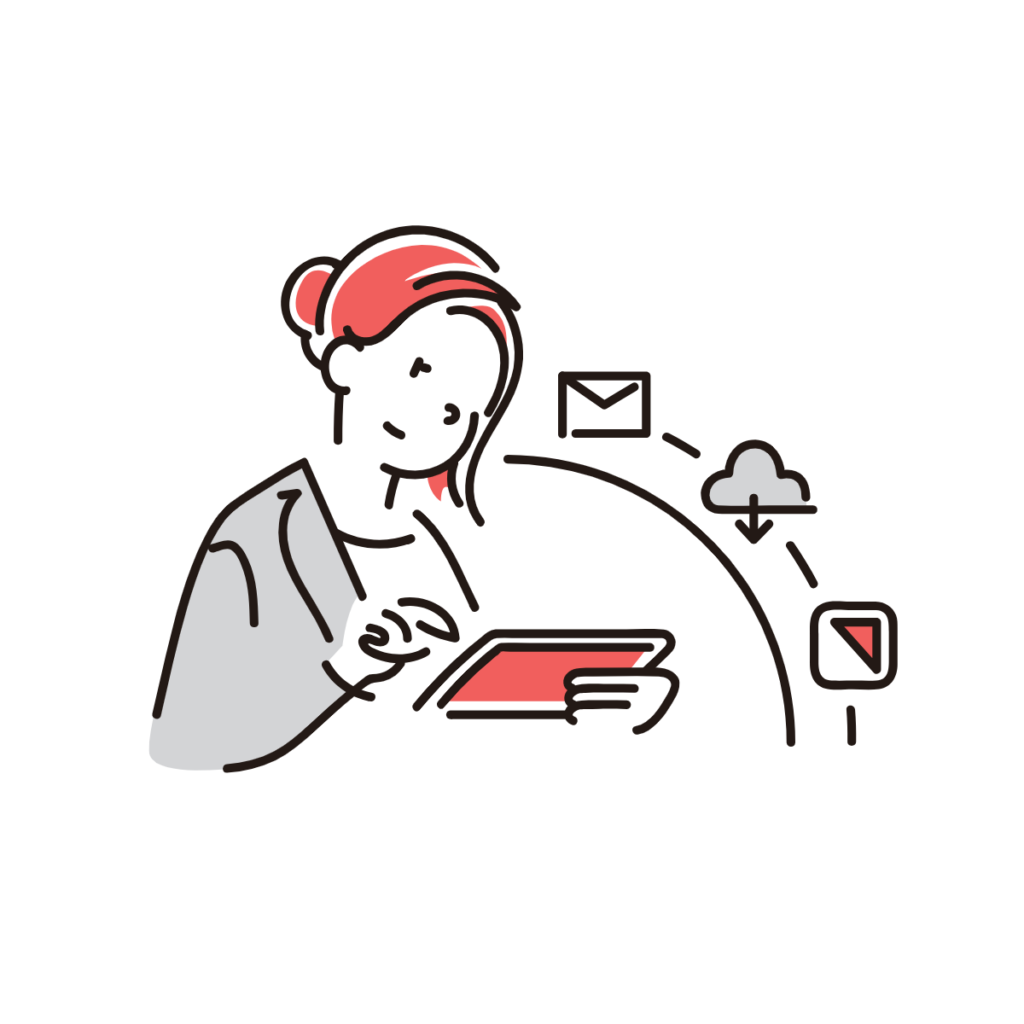
会計ソフトの申込み手続きを済ませたら、早々に初期設定を済ませてしまいましょう。
会計ソフトの主な初期設定
- 事業用クレジットカードのデータ連携
- 事業用銀行口座のデータ連携
- 取引先、勘定科目、補助科目等のマスタ追加
これらの初期設定が完了したら、後は毎月の売上計上と経費の仕訳の登録を行うだけです。
会計ソフトの入力タイミングは?
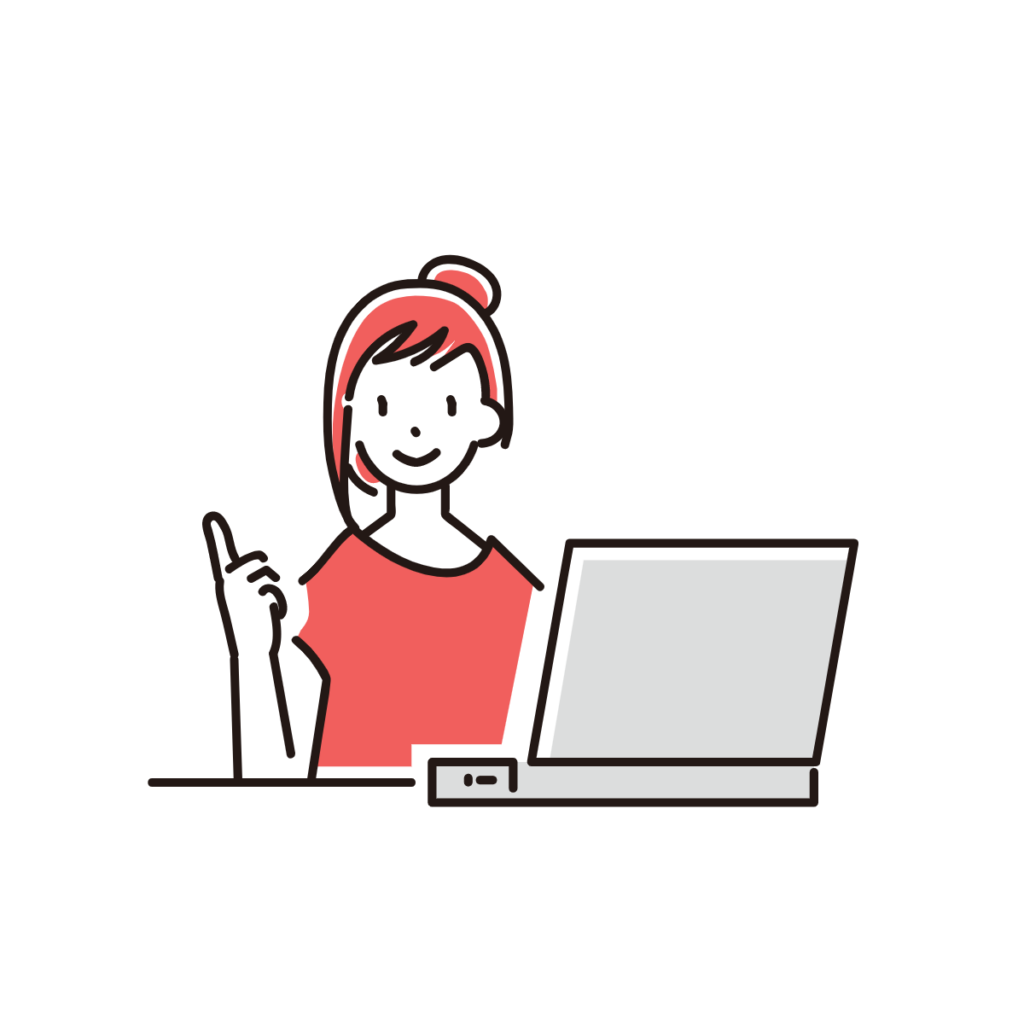
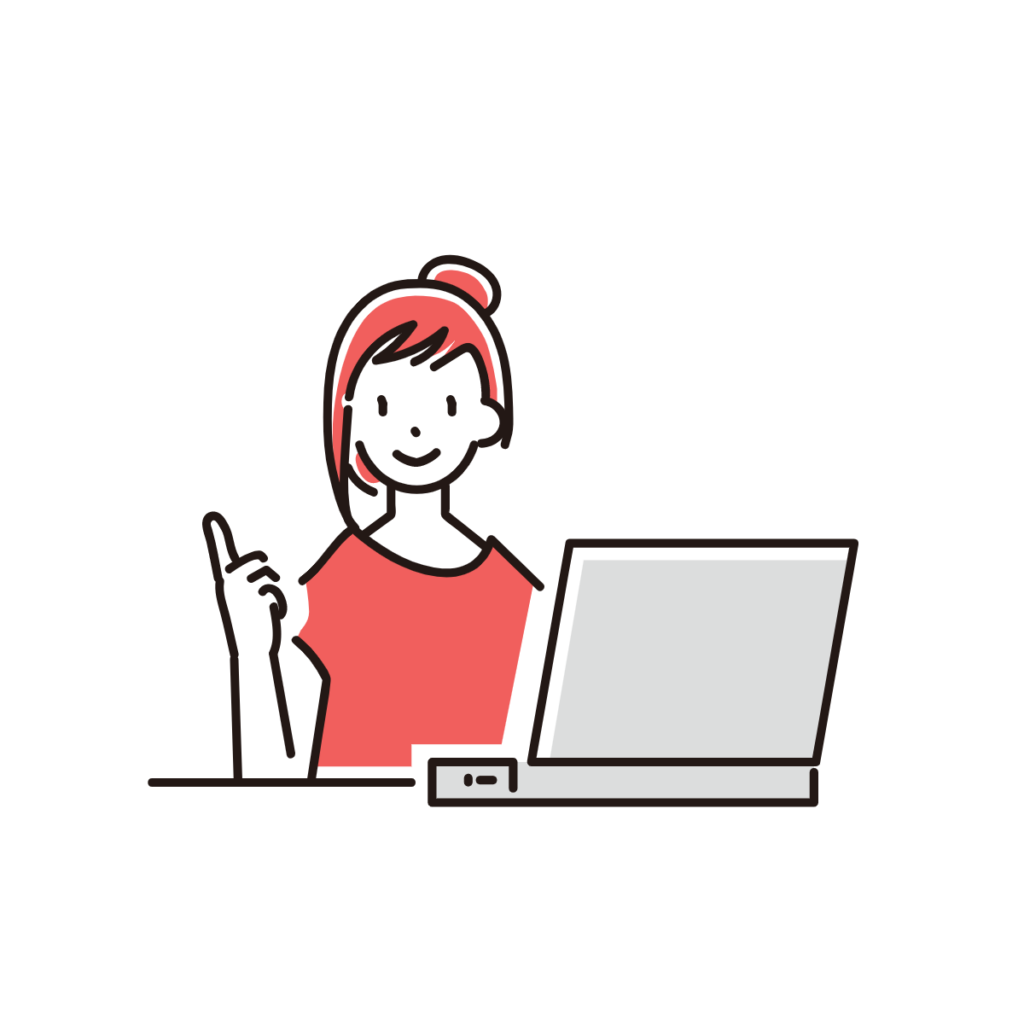
売上も経費も処理をためずに日次や月次で処理しましょう。
確定申告の締め切り直前にまとめて1年間の売上と経費を処理する人もいるようですが、おすすめできません。
わたしの場合は、売上は毎月月初に、経費は発生した都度会計ソフトに入力しています。
確定申告を恐れる必要はありません。
毎年3月に確定申告で大騒ぎしている人は、直前まで経理処理を貯めて、1年分を処理する人たちです。



都度処理しておけば確定申告は1日で終わります (笑)
わたしは毎年1月に終わらせています
【番外編】事業用の銀行口座とクレジットカードを作ろう
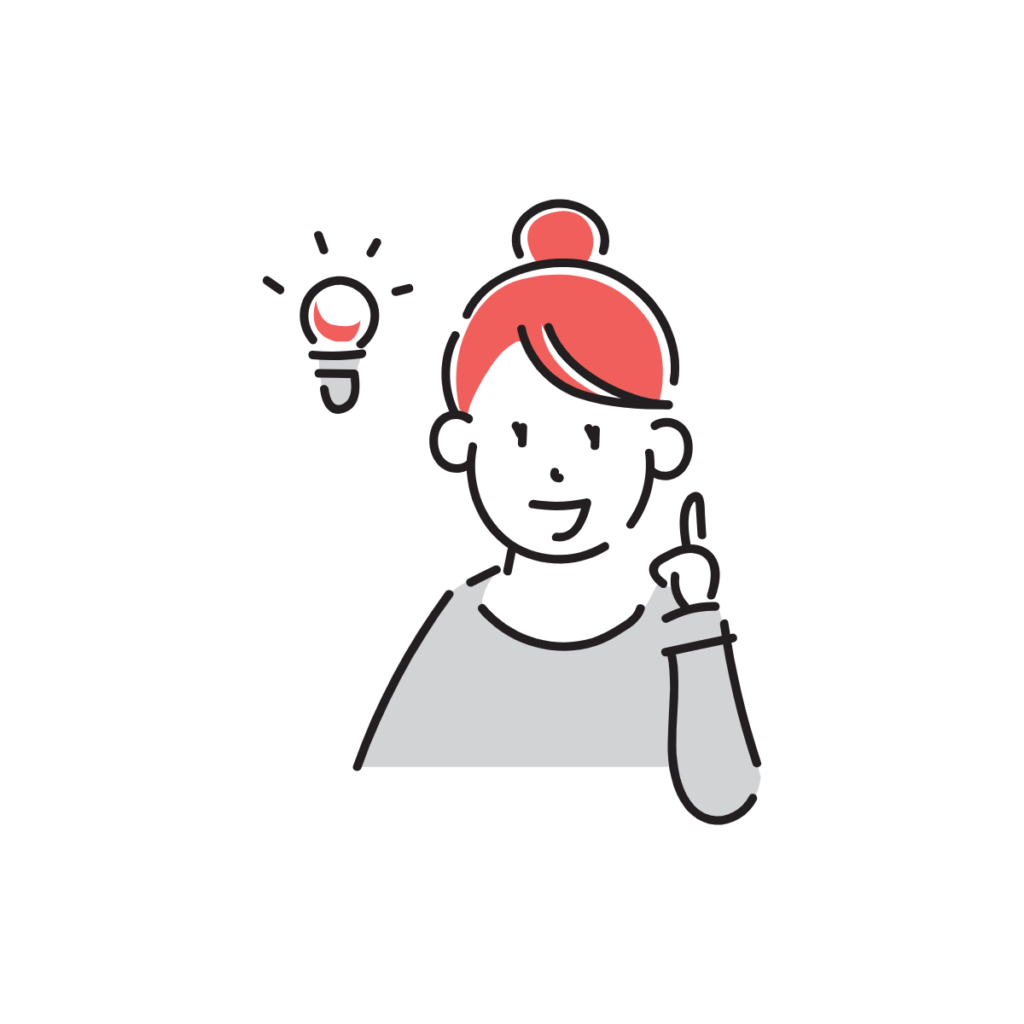
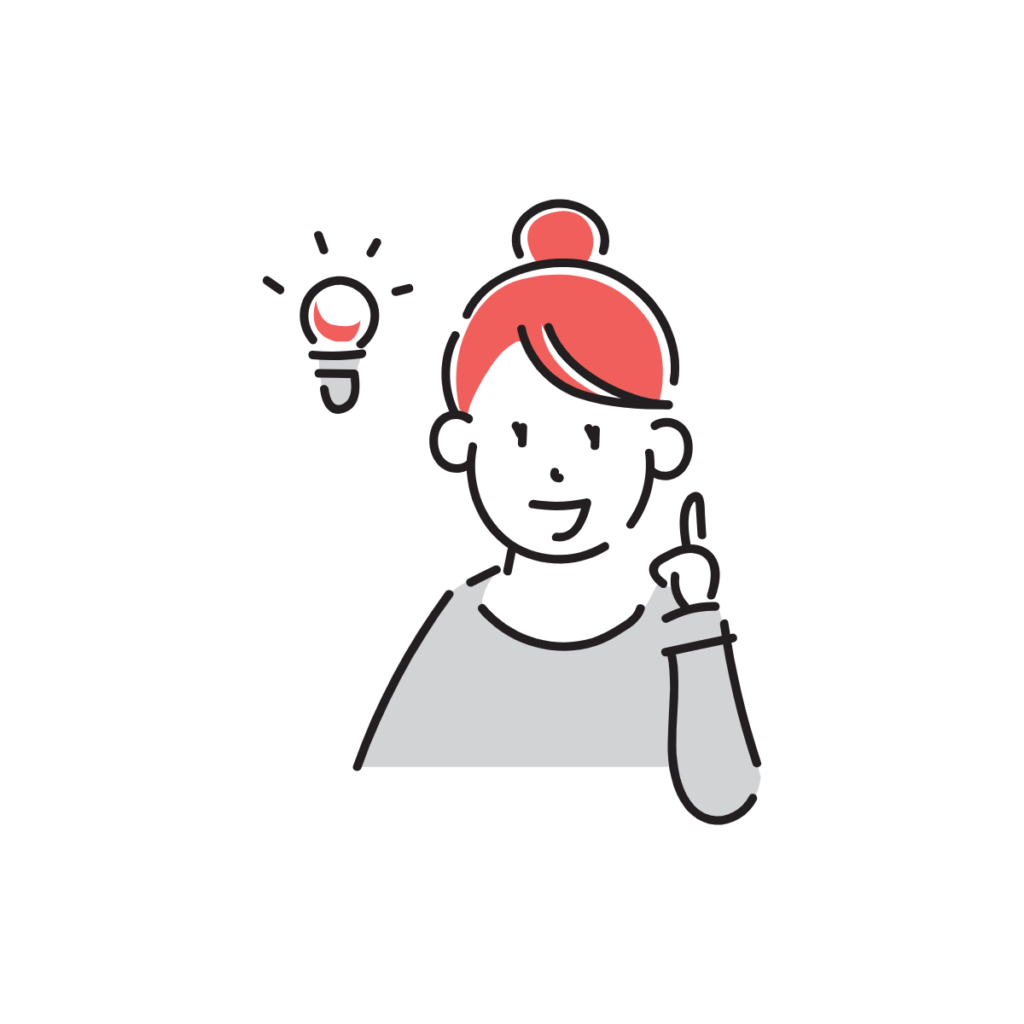
会計ソフトの契約とセットで準備しておきたいのは、事業用の銀行口座とクレジットカードの準備です。
理由は、銀行口座の入出金履歴やクレジットカードの利用明細に、事業用とプライベートの履歴が混じっていると管理がしづらいからです。
特に、会計ソフトを効率的に使いたいなら、銀行口座やクレジットカードの履歴を自動で取込みながら使うことになると思います。
その時に、プライベートの入出金が混じっていると、大量のノイズが入り込むことになります。
必ずしも新しく銀行口座やクレジットカードを作る必要はありませんので、既に持っているけれども使わなくなった銀行口座とクレジットカードがあれば、それらを使いまわしましょう。



現金での入出金が多い業態をしているなら、現金の管理もプライベートと分けた方が良いと思います。
💡 事業用の銀行口座とクレジットカードを作る必要性と具体的なはじめ方を詳しく説明しています。良かったら、こちらの記事も参考にしてみてください。


会計ソフトの必要性とおすすめの会計ソフト(まとめ)


会社員の副業であっても、それは立派なビジネスであり、個人事業です。
このため、売上があがりそうな見込みが出来たら、なるべく速やかに会計ソフトを導入しましょう。
お勧めのクラウド会計ソフトは以下の3つです。
なかでも、経理初心者はfreee会計がお勧めです。
また、会計ソフトの契約と同時に、事業用の銀行口座とクレジットカードも持っておくことを強くお勧めします。
会計ソフトの導入は初期設定と操作方法を習得するのに少し時間と手間がかかります。
廃業しない限りはほぼ毎年確定申告をすることになるため、最初にしっかりと基礎を作ってしまい、なるべく自社経理がスムーズに進むようにしておきましょう。
💡 確定申告の基本的なルールを知りたい方は、こちら記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。副業初期から準備を進めておくことで、確定申告にスムーズに取り組むことができます。


💡 副業でまだ売り上げが上がっていない場合は、会計ソフトの導入はもう少し待っても良いと思います。「自分には、会計ソフトの導入はまだ早い」と感じた方は、こちらの記事が参考になると思います。



-1024x1024.png)
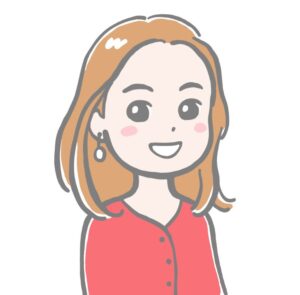
でどう違う?種類と節税対策-300x169.png)