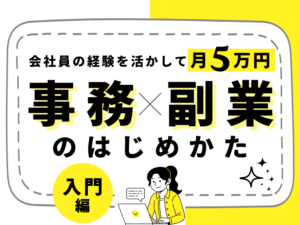この記事では、わたしの苦手分野である「貯金」を敢えてテーマに取り上げます。
副業が軌道に乗り始めると、「このまま独立したい」と考え始めるのは、ごく然な流れだと思います。
しかし、勢いだけで会社を辞めるのはそれなりのリスクが伴います。
独立を考える際には、ある程度、準備しておいた方が安心なことも多いです。
税金や社会保険の話など、独立後のお金のことについて理解しておくこも、独立前にやっておくべき準備のひとつではあります。
加えて「生活防衛資金」、つまりいくら貯金しておくべきか?という考え方をご紹介します。
副業がうまくいったらいずれはフリーランスとして働いてみたい
というあなたが、これから独立準備を進める上で、この記事を参考にしていただけたら嬉しいです。
そもそも論|「生活防衛資金」って一体何のこと?

生活防衛資金とは、予期せぬ事態に備えるための生活費の蓄えであり、収入が途絶えた際の生活の安定を図ることを目的とした貯金を言います。
これは、将来の特定の目的(例:子供の学費、住宅購入、老後資金)に備えるための貯蓄とは異なり、緊急時の生活維持を目的としています。
わたしが「生活防衛資金」という考え方を知ったのは、会社員として勤めながら副業をしていた当時でした。
リベラルアーツ大学(以下「リベ大」とします)の両学長は、生活防衛資金について以下のように定義しています。
生活防衛資金の目安は、あなた自身の働き方や家族構成、基準となる生活費よって人それぞれ異なります。
また、リベ大では、働き方によって以下のような生活防衛資金の目安を示しています。
会社員の場合:生活費の6ヶ月分
自営業者・フリーランスの場合:生活費の1年分
例えば、月の生活費が20万円の場合、会社員は120万円、自営業者・フリーランスは240万円が生活防衛資金の目安となります。
 りか
りか生活防衛資金を計算するときは、月収や年収に関係なく必要最低限の支出で計算することがポイントです。
【参考】両学長リベラルアーツ大学
💡 生活防衛資金にご興味のある方は、両学長の「お金の大学」という書籍が参考になると思います。わたしの副業時代の経験も踏まえて書いた、「お金の大学」のレビュー記事を覗いてみてください。


【コラム①】生活防衛資金の定義に個人の価値観が出る
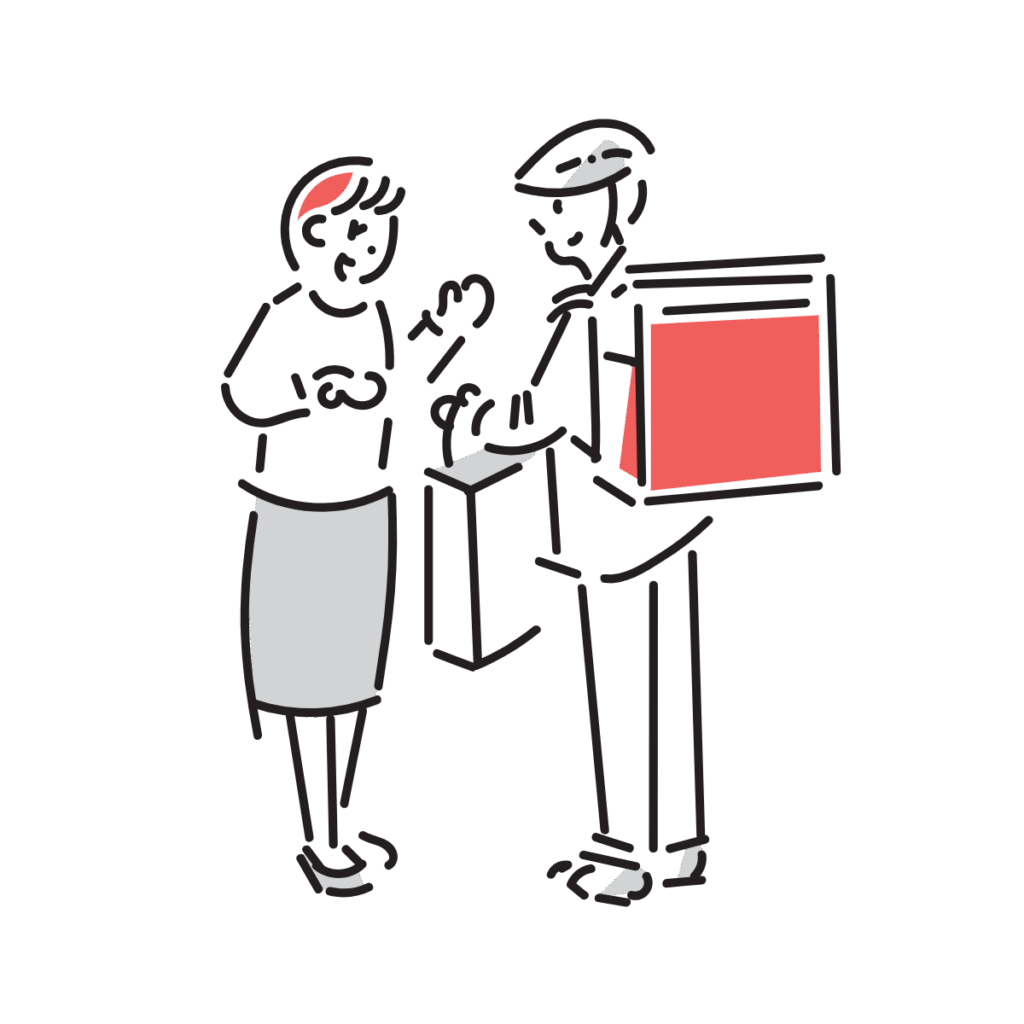
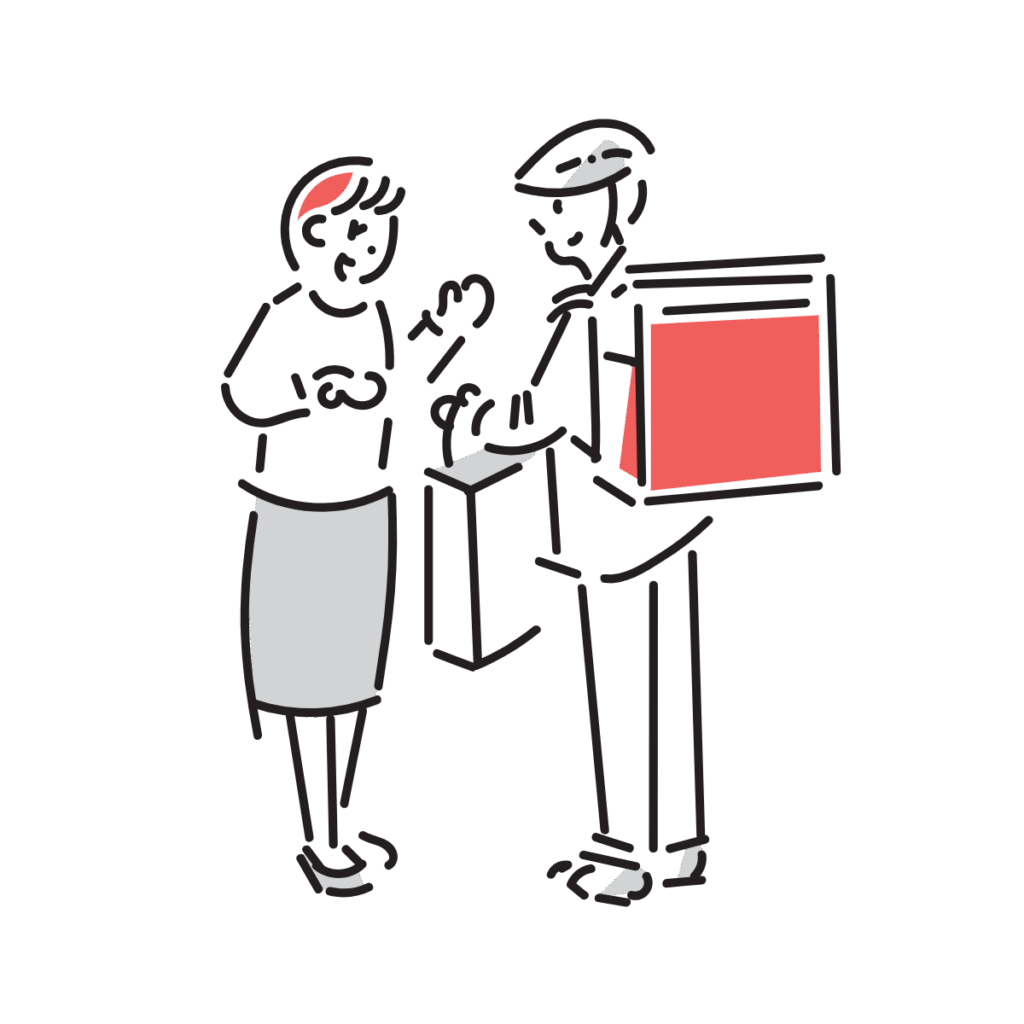
どこまでを必要最低限の支出とするかは、本当に人それぞれです。
判断が分かれそうな支出の例を挙げてみるので、あなたの場合はどうか、振り返ってみてください。
どこまで生活防衛資金に含めるか(例題)
- 年1回の家族旅行
- 月1回のマッサージ
- Amazonプライムの年会費
- 友達との飲み代
わたしなら、家族旅行と飲み代は生活防衛資金に入れませんが、マッサージとAmazonプライム会費は生活防衛資金にカウントすると思います。
生活防衛資金に含める理由(わたしの価値観)
- 副業時間を捻出するために生活用品をAmazonで購入したり、自己研鑽のために書籍を購入したい
- デスクワークの肩こりや腰痛がひどいと働けなくなってしまうため、健康維持のためにマッサージは必須
「生活費をどこまで削っても、生活していけるのか?」
そこには、あなた自身の価値観がダイレクトに反映されます。
わたしの価値観では、旅行の優先度は高くないため必須ではないのです。
ですが、あなたがもし旅行することが人生最大の楽しみで、年1回の家族旅行も「絶対に譲れない」という考えなら、それもきちんと生活防衛資金に計上した方が良いでしょう。
生活防衛資金を持っておくことの「精神的なメリット」


生活防衛資金は、緊急時の生活維持を目的とした資金で、これを確保しておくことで、予期せぬ事態にも冷静に対処できます。
生活防衛資金を持つメリットとしては、実際に売上が途絶えたときに、生活していくことが出来るという現実的なメリットが第一です。
この他に「精神的な安心感が得られる」という側面もあります。
収入が途絶えた際にも生活を維持できるという安心感が土台にあれば、自分がやりたくない仕事の依頼が来ても勇気をもって断ったり、将来に向けた準備期間を取る等の冷静な判断がしやすくなります。
貯金がなくても独立できるのか?(ケーススタディ:わたしの場合)


この記事の冒頭に記載したとおり、わたしは貯金がとても苦手です。
正直なところ、わたしの場合は、独立したタイミングで生活防衛資金は3ヶ月分しか確保できていませんでした。
生活防衛資金を貯めてから独立しようと思ってはいたのですが…
独立した直接のきっかけは、会社で上司から受けたパワハラだったため、生活防衛資金を確保する前にフリーランスになりました。
あくまで結果論ですが、生活防衛資金がなくても、フリーランスとして生きてくることはできました。
ただ、順番は前後しますが、独立して以降に生活防衛資金を1年分以上は確保したところで、精神的な余裕が全然違うと感じています。



実際に生活防衛資金を1年分確保してから独立していたら、独立まで2~3年は会社員を続けていたかもしれず、会社を辞めるタイミングとしては適切だったと感じています。
【コラム②】あなた自身がどこまでリスクをとれるのか


結局のところ、あなた自身がどこまでのリスクを取れるのか、これにつきます。
独立時に考慮すべき要因(例)
- あなた自身の性格(楽観的なのか、慎重なのか等)
- ご家庭の状況(単身なのか配偶者がいるか、扶養親族の有無等)
- 生活レベルをどこまで下げられるか
貯金があれば独立しても大丈夫かというと、人によっては…
わたしには貯金があるから、しばらくは営業しなくても良いや…
という具合に、貯金があることで安心してしまい、「稼ぐ」思考にならないという場合もあるでしょう。
独立するにあたって貯金があるに越したことはないです。
ですが、貯金だって使ってしまえばいつかはなくなってしまうので、絶対的な安心材料ではありません。



どこまで準備してから独立・起業するのかは人それぞれ事情が違うので、総合的に判断するしかないのかなと思います。
固定費の見直しでリスクに備える
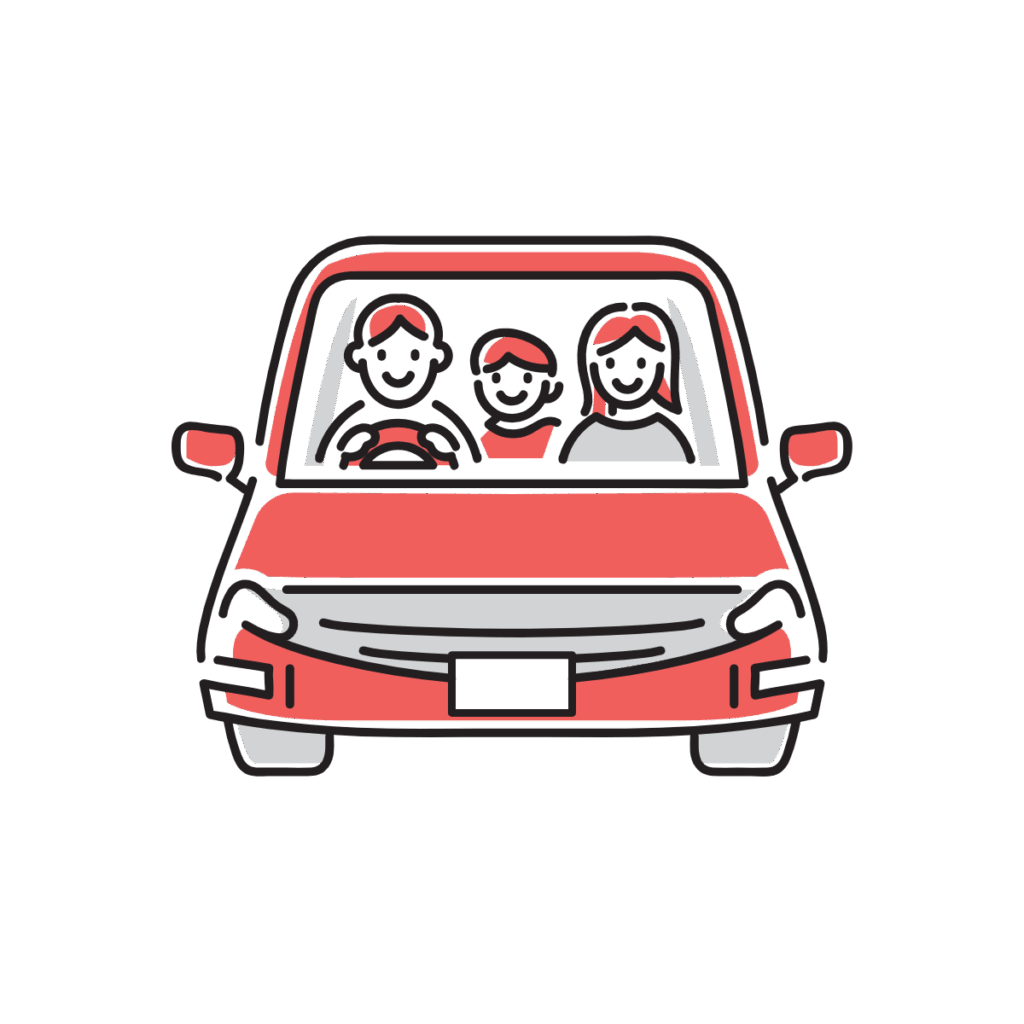
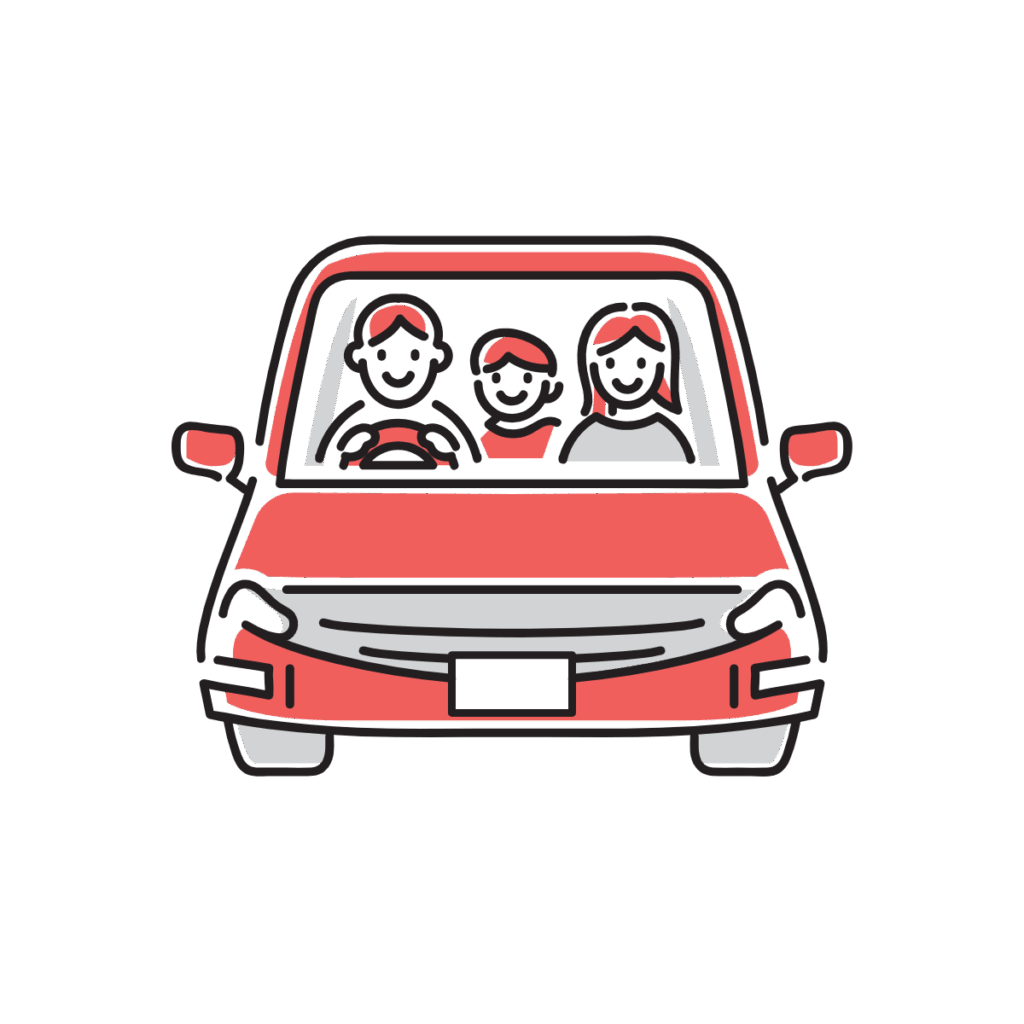
繰り返しになりますが、わたしは貯金が苦手です。
貯金が苦手だからこそ、生活防衛資金の目標額を抑えたくて、独立前に固定費の見直しをしました。
副業では「稼ぐ」ことに注力しがちですが、独立を目指すなら一方で「貯める」ことも意識をした方が良いと思います。
そして、目的が「貯金」なのだとすれば、副業や転職で年収を増やす活動より、支出を減らす方が即効性があります。
特に固定費(住居、車、携帯電話、保険料など)の見直しが最も効果的です。
固定費の見直しポイント
- 住居費:家賃の見直しや引っ越しを検討する
- 車:車の維持費を見直し、必要であれば手放す
- 携帯電話:格安SIMへの乗り換えを検討する
- 保険料:保険の見直しや解約を検討する



毎月の支出を減らして貯金をしながら、生活防衛資金の目標額を下げることで、独立までの準備期間を短縮することにも繋がります。
💡 固定費の見直しに興味のある方は、両学長の「お金の大学」という書籍が参考になると思います。わたしの副業時代の経験も踏まえて書いた、「お金の大学」のレビュー記事を覗いてみてください。


独立を目指すなら、家計管理をはじめてみよう
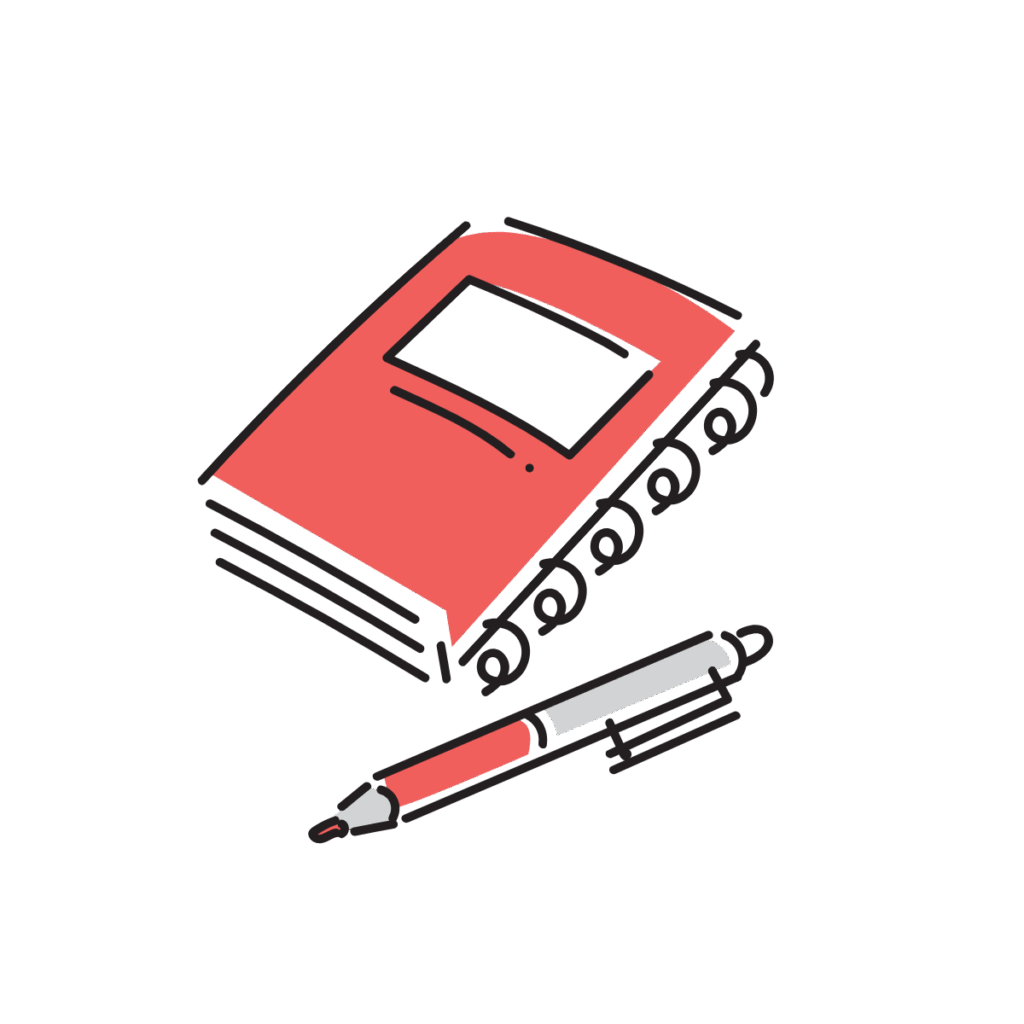
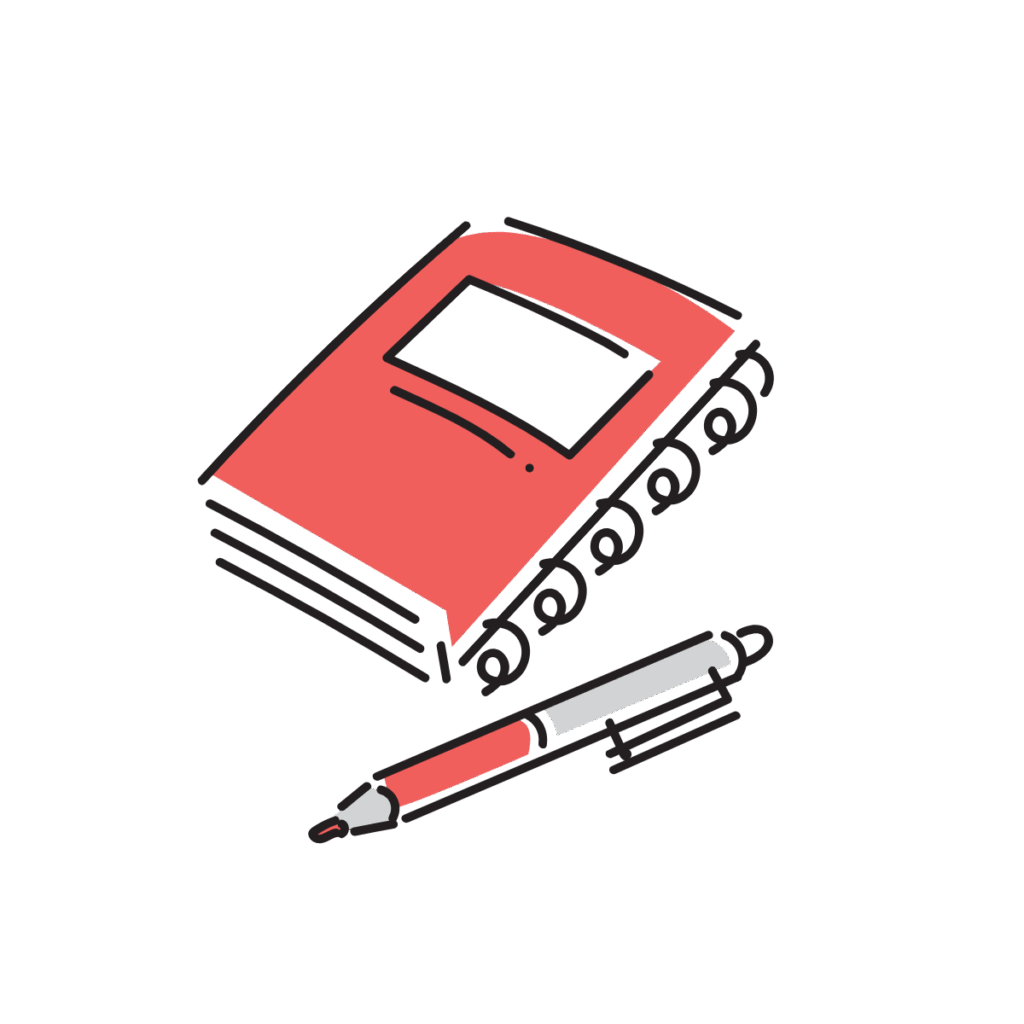
生活防衛資金の必要性と、その算出方法を理解したあなたは、
わたしの生活防衛資金て具体的にいくらなんだろう…?
というふうに疑問に感じられたと思います。
もし、今現在は家計管理をしていないという状況なら、最低でも今日から3か月間は家計簿アプリを使って、自分が毎月何にいくら使っているのかを把握してみましょう。
まずは、あなたが毎月いくらあれば生活していけるのか、あなた自身の(あるいはご家庭の)生活費を把握していないと、そもそも生活防衛資金の算出が出来ません。
また、生活費が毎月の支出が少ない方が、生活防衛資金も少なくて済むため、独立のハードルも下がります。
これから独立や起業を目指している方は、あなた自身(あるいはご家庭で)の生活費が毎月いくら必要なのかを独立前に把握しておくことをお勧めします。
💡 会計ソフトだけでなく家計簿アプリをつけておくメリットに関して、こちらの記事で詳しく解説しています。独立準備のマネーリテラシーとして、参考にしていただけたら幸いです。





わたしは貯金が苦手ですが、独立を視野に入れたタイミングで家計簿アプリを導入して家計管理を始めました!
自分に合ったリスクの取り方を考えよう(まとめ)


わたし自身も含めて、実際のところ、セオリーのとおりに計画・準備して独立できる人は、少ないのかもしれません。
ただ、会社員からの独立を考える際には、生活防衛資金を計算することだけでも、ぜひ一度やってみて欲しいです。
支出が把握できていないと、いくら稼げばよいかもわかりません。
つまり、独立した後にどれくらい稼げばよいかの売上目標も立てづらくなります。
あなたが、もし「収入が途絶えても3年は生きていけるくらいの貯金がないと安心できない」と感じているなら、安心するに足る金額を貯めてから会社を辞めたら良いでしょう。
その分、独立のタイミングが遠くなります。
一方で、貯金がなくても生きていける自信や経済的な後ろ盾があるのなら、生活防衛資金の話は忘れてもらって、近々に独立の決断をすれば良いと思います。
あなたのキャリアにおいて、独立してフリーランスとして活動できる期間は早まりますが、貯金してから会社を辞める人に比べるとより大きなリスクを背負うことになります。
あなたの価値観や生活環境にあったリスクの取り方を、真剣に考えてみましょう。
「会社を辞める」という大きな決断を判断する際に、基準の一つとして「生活防衛資金」という概念があることを覚えておいてください。



わたしが経験から言えることは、経済的な余裕は「ある」に越したことはない、ということです。
💡 副業を始めたからと言っていきなり会社を辞めない方が良いとわたしは思います。その理由について、詳しく解説した記事がありますので、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
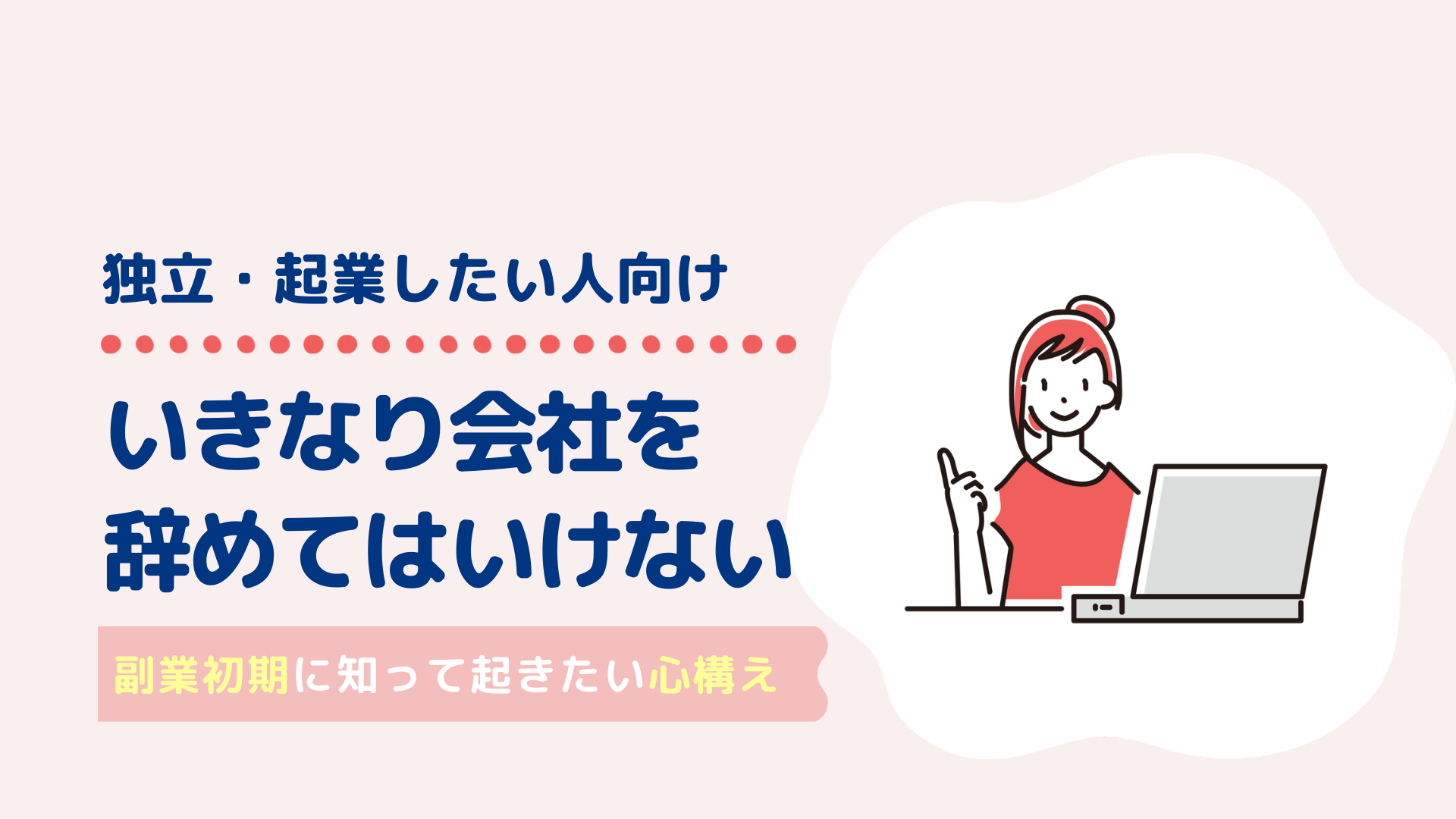
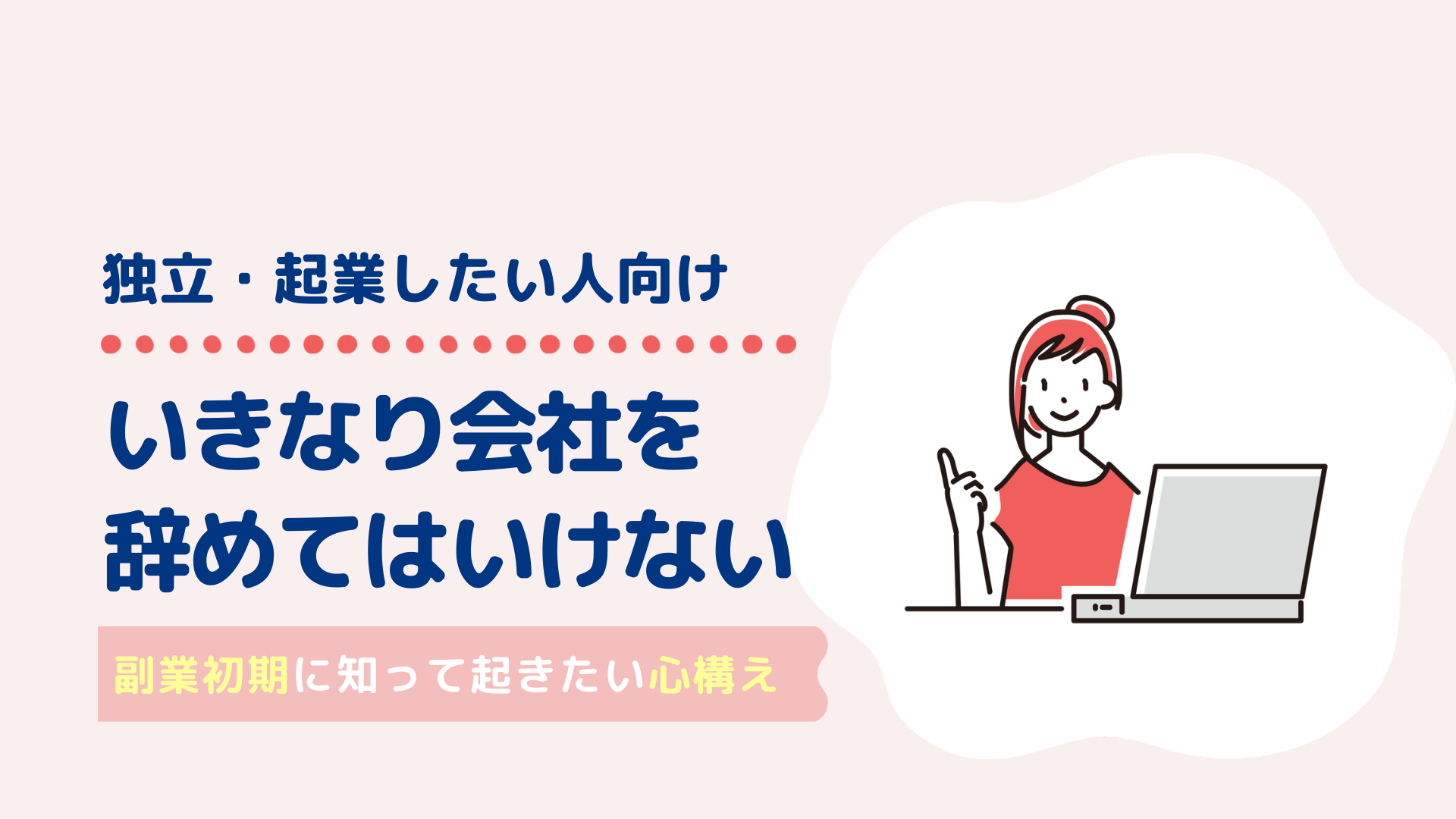
💡 独立前に知っておいた方が良いお金の知識として「税金」と「社会保険」があります。それぞれ、会社員とフリーランスの違いを解説した記事がありますので、こちらも併せて独立準備の参考にしてみてください。
でどう違う?種類と節税対策.png)
でどう違う?種類と節税対策.png)



-1024x1024.png)
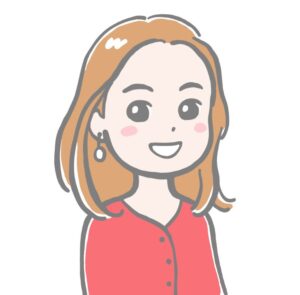
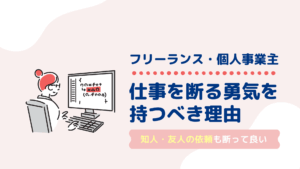


でどう違う?種類と節税対策-300x169.png)