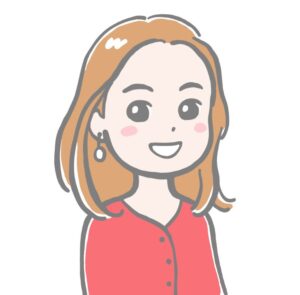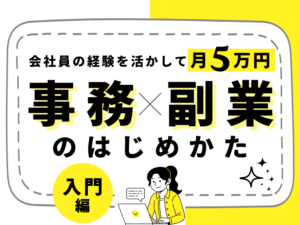「安定していて高収入」「ワークライフバランスが取りやすい」そんなイメージで憧れる人も多い大学職員です。
しかし、実際に働いてみると理想と現実のギャップに悩み、転職を考える30代女性が増えています。
特に30代という人生の重要な時期において、キャリアアップや将来設計への不安から「このままでいいのだろうか」と感じる方も少なくありません。
この記事では、大学職員を辞めたいと感じる理由を整理し、実際に転職して「辞めてよかった」と感じているわたしの体験談もご紹介します。
また、実際に転職するにはどんなことに気を付けたら良いのか、キャリアコンサルタントの視点から、転職を成功させるヒントもご紹介します。
もし今の職場に疑問を感じているなら、今後のあなたのキャリアを考える上で、参考にしていただけると嬉しいです。
大学職員を辞めたい理由8選
まずは、大学職員を辞めたいと感じている人が、今の職場環境にどんな不満を感じてるのか、その代表的な理由をまとめてみました。
あなたの場合は、この中の理由のどれに当てはまるでしょうか。
自分の場合に置き換えて、理由を考えながら読み進めてみてください。
大学職員を辞めたい理由8選
- 年功序列でモチベーションが維持できない
- 給与の上限が見えてしまう将来への不安
- 単調な業務内容でやりがいを感じられない
- 繁忙期と閑散期の激しい業務格差
- 教員との上下関係・板挟みによるストレス
- 専門スキルが身につかず、頻繁な異動で将来が不安
- 女性の多い職場特有の負担増
- 組織の保守性で新しい挑戦ができない
大学職員を辞めたい理由①|年功序列でモチベーションが維持できない

大学職員の多くは年功序列制度を採用しており、どんなに頑張っても報酬や評価に反映されない環境があります。
成果主義のない職場では、優秀な職員ほど退職してしまうという現実があります。
30代になってキャリアアップを望んでも、個人の実績が評価されにくく、やりがいを感じられなくなってしまうケースが多発しています。
「努力しても報われない」という状況は、向上心の高い女性にとって大きなストレス要因となっています。
💡 大学という職場は年功序列で、昇給と評価がかみ合わないことが多いです。給与や待遇面での限界を感じている方には、こちらの記事が参考になると思います。

大学職員を辞めたい理由②|給与の上限が見えてしまう将来への不安

大学職員は年功序列で安定している一方、どんなに頑張っても年収の上限が決まっているという現実があります。
30代になると将来設計を具体的に考える時期ですが、昇給の限界が見えてしまうことで、経済的な不安を感じる女性が増えています。
特に結婚や出産、住宅購入など、ライフイベントが多い30代女性にとって、給与の伸び悩みは深刻な問題です。
どれだけ頑張っても人との差がつきにくい環境では、将来への投資や自己実現が困難になってしまいます。
💡 同じような仕事内容でも、環境を変えるだけで給与アップに繋がることがあります。安定した職場環境ではあるものの、内心では「もっと稼ぎたい」と思っているなら、こちらの記事を参考にキャリアを見直してみてください。

大学職員を辞めたい理由③|単調な業務内容でやりがいを感じられない
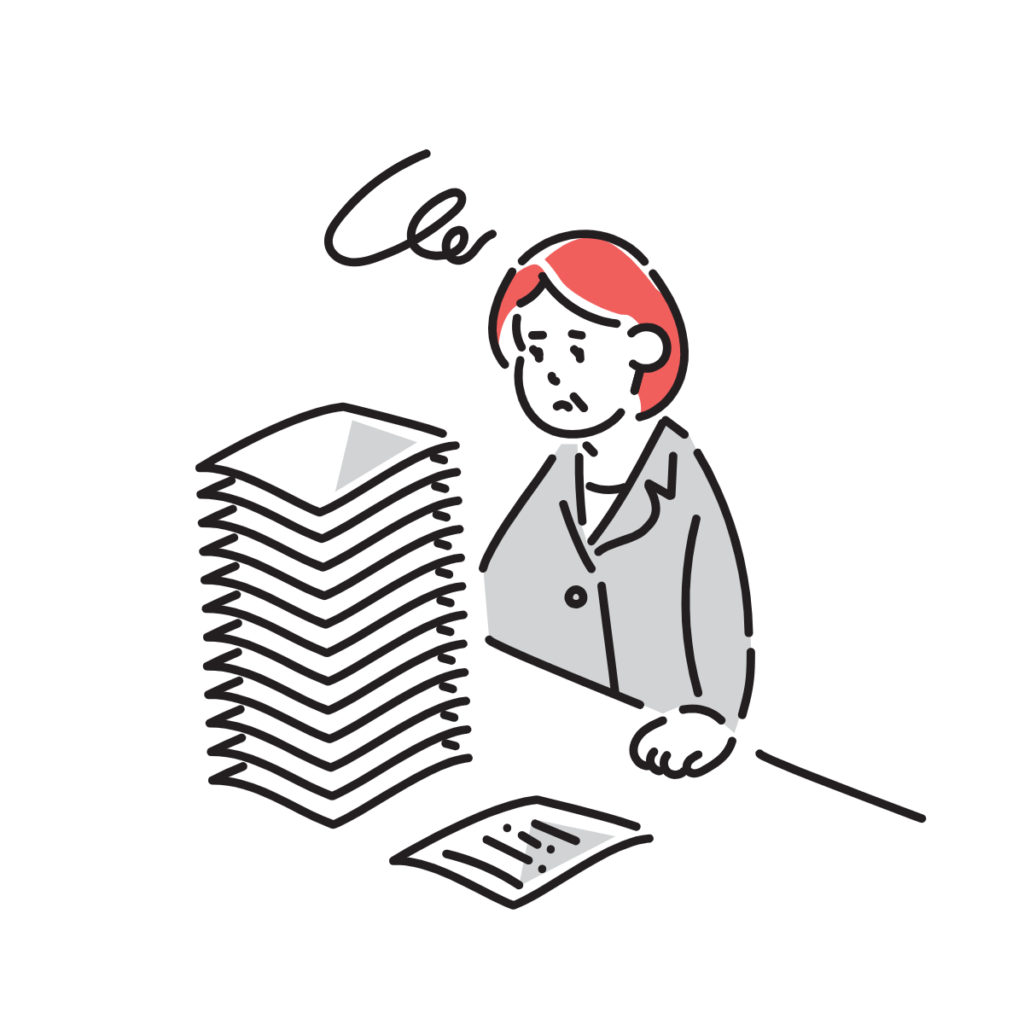
大学職員の仕事は毎日同じような内容で、まったく新しい業務を始めることはめったにありません。
1年のサイクルが決まっており、一つの仕事を覚えてしまえば毎年それを繰り返すだけです。
書類作成、データ入力、窓口対応など、仕事の繰り返しも多く含まれているため、日々の業務に面白みを感じられないと思う人も多いでしょう。
単調な作業がずっと続くことに嫌気がさし、「もっと刺激的で成長できる仕事がしたい」と感じる30代女性が多いのです。
💡安定した職場環境だからと言って、個人の将来性が保障されているとは限りません。大学職員として働き続けることに「将来性がないのでは?」と不安を感じている方は、こちらの記事が参考になると思います。

大学職員を辞めたい理由④|繁忙期と閑散期の激しい業務格差
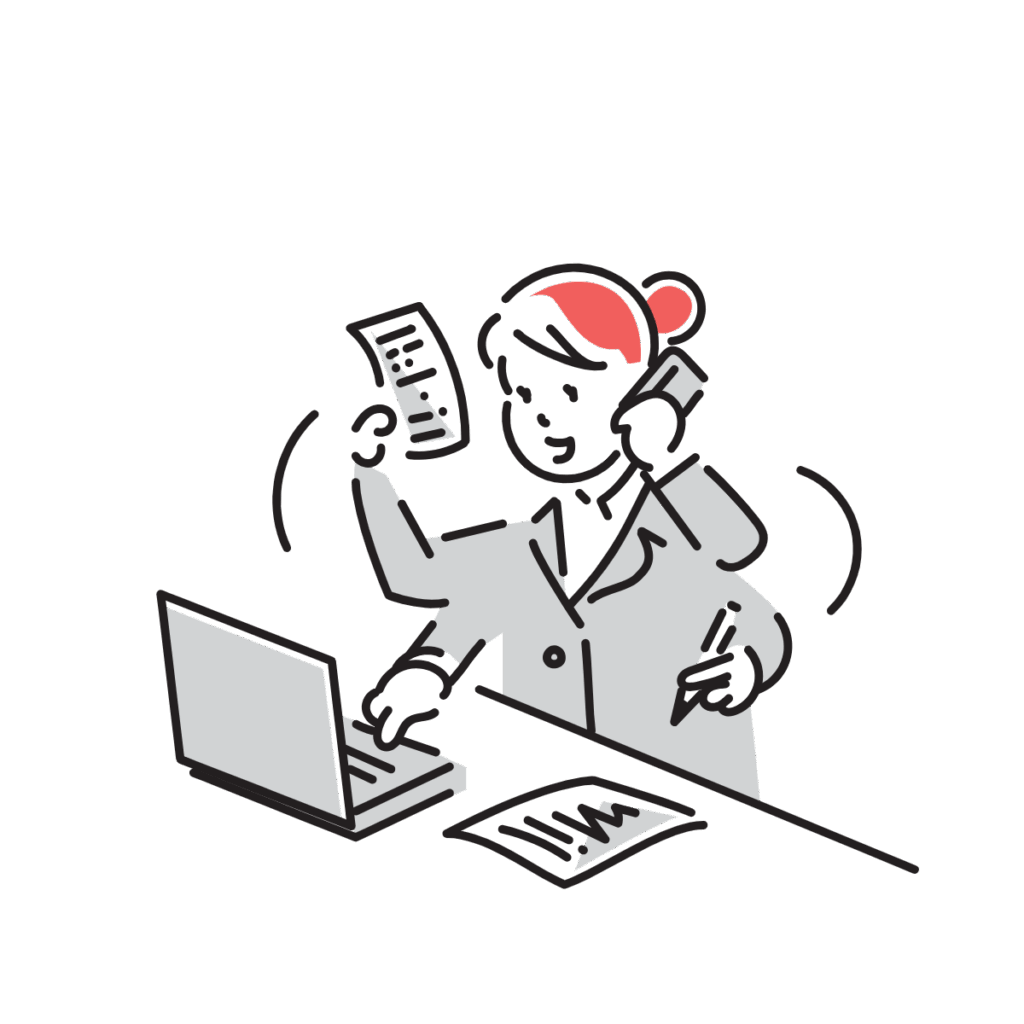
年が明けて年度が変わるまでの繁忙期には、深夜まで残業をすることが多いのが大学という職場です。
繁忙期や大学のイベント時には休日出勤も当たり前で、プライベートな時間がほとんどない、というケースもあります。
この極端な業務量の波が、ワークライフバランスを崩す要因となっています。
繁忙期の激務で体調を崩したり、閑散期の退屈さでモチベーションが下がったりと、安定したペースで働きたい女性には大きな負担となっています。
大学職員を辞めたい理由⑤|教員との上下関係・板挟みによるストレス

大学は今でも縦社会で、教員の上からの圧力を感じることが多い職場です。
上司と教員が対立した際に板挟みで苦しむ状況や、教授や学長からの仕事を断ることが難しい環境で、精神的なプレッシャーを感じやすくなっています。
権力争いもあり、上司に意見を言えずに従うケースも多く、嫌な上司や理不尽な教員に当たった場合の精神的負担は計り知れません。
30代女性にとって、このような人間関係のストレスは転職を考える大きな要因となっています。
大学職員を辞めたい理由⑥|専門スキルが身につかず、頻繁な異動で将来が不安

大学の事務は専門的なスキルを得ることが難しく、将来に不安を感じやすい環境です。
さらに、大学は組織が非常に大きい分、配属される部署も様々で、入職時点での能力や適性によって自分がイメージしていなかった部署に移ることもよくあります。
せっかく業務に慣れても数年で異動となり、ゼネラリストとして浅く広い経験しか積めないため、30代も半ばを過ぎてくると一気に市場価値が下がってしまいます。
特に30代女性にとって、専門性を身につけたいタイミングで異動を繰り返すことは、キャリア形成の大きな障害となっています。
💡 人事異動が多すぎて疲れている方には、こちらの記事が参考になると思います。キャリアの見通しが立たない場合の対策も解説していますので、今後のキャリアを考える上でヒントになれば幸いです。

大学職員を辞めたい理由⑦|女性の多い職場特有の負担増
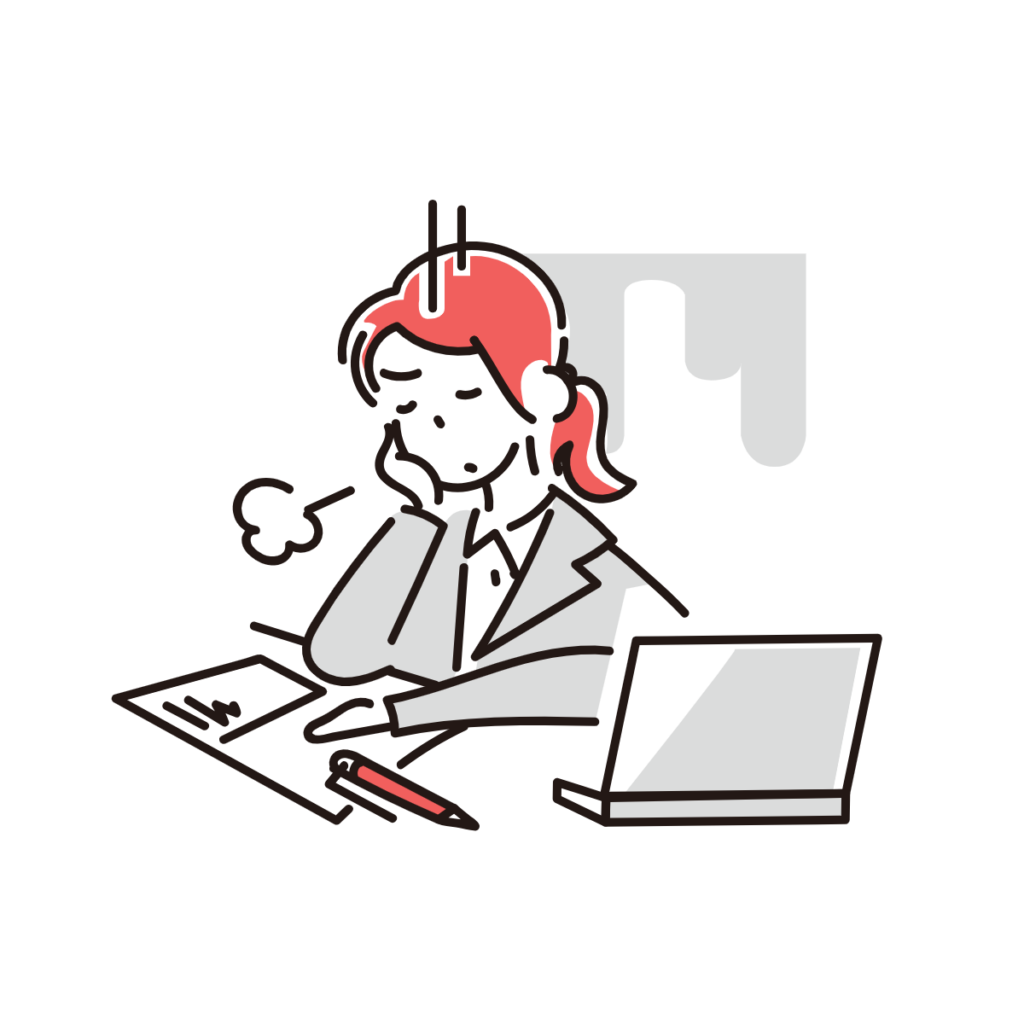
大学職員は女性比率が高く、30代前後で産休・育休を取得する同僚が多い職場です。
制度としては整っているものの、実際には残された職員にしわ寄せが集中し、一人当たりの業務量が大幅に増加してしまいます。
特に同世代の30代女性は、自分も将来的に出産・育児を考えているにも関わらず、現在は代替要員が確保されない中で長時間労働を強いられるという矛盾した状況に置かれがちです。
本来ワークライフバランスが取りやすいはずの職場が、実際には家庭との両立が困難になってしまうケースが少なくありません。
💡 仕事ができるのに、他人のフォロー等、損な役回りばかり引き受けて疲弊していませんか?損な役回りを脱却したいと思っている方のために、理由と対策をまとめた記事がありますので良かったらこちらを参考にしてみてください。

大学職員を辞めたい理由⑧|組織の保守性で新しい挑戦ができない
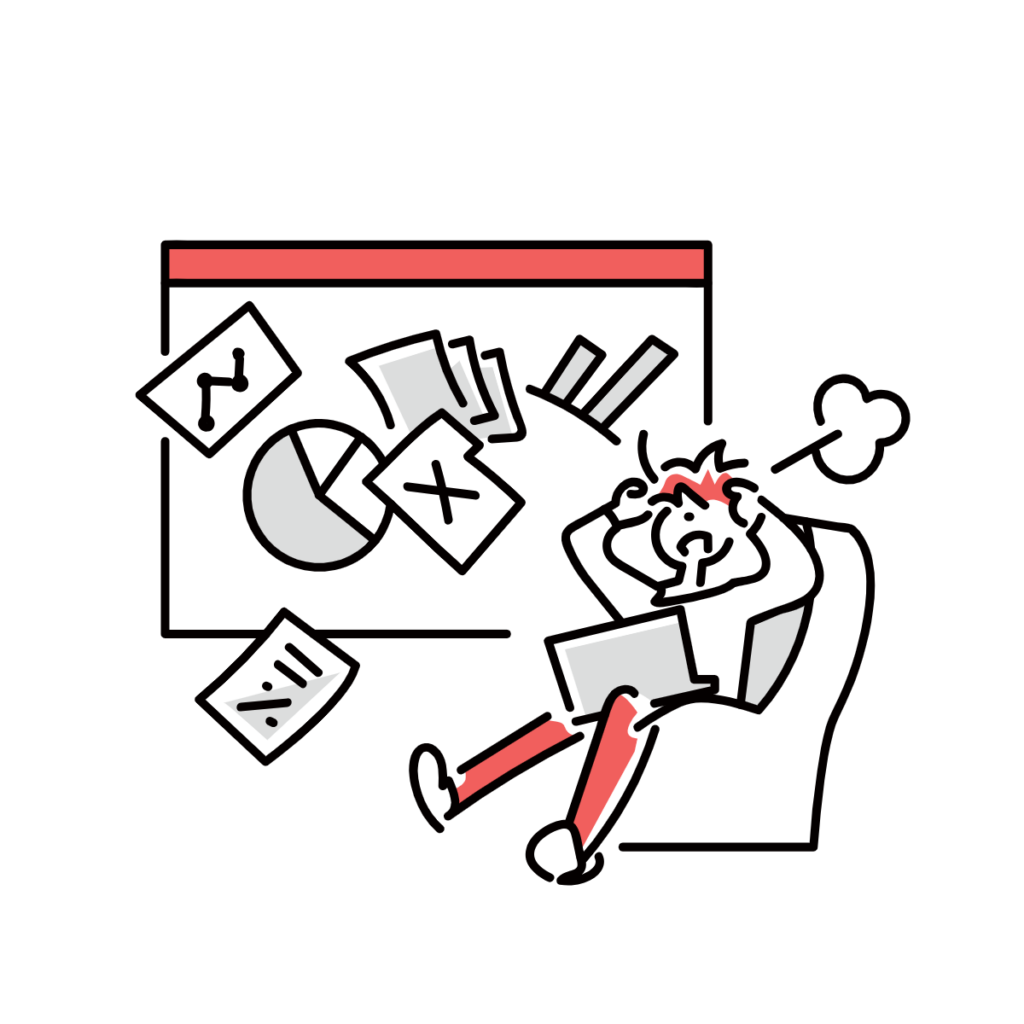
大学は伝統を重んじる組織文化が強く、新しいことに挑戦しにくい傾向があります。
30代になってキャリアアップや新しいスキル習得を望んでも、前例主義や稟議制度により、革新的な取り組みが困難な環境です。
変化の激しい現代において、スピード感を持って業務改善や新規プロジェクトに取り組みたい女性にとって、この保守的な体質は大きなストレスとなっています。
「もっと自分のアイデアを形にしたい」という想いを抱く30代女性には、物足りない環境と言えるでしょう。
大学職員を辞めてよかったと感じた点3つ【実体験】
わたし自身、今はフリーランスでベンチャー企業やスタートアップの事務をやっていますが、30代の時に、大学職員から民間企業に転職した経験があります。
その時の実体験や、今の働き方と大学職員時代を比較してみて、大学職員を辞めてよかったと感じるポイントを3つご紹介します。
「大学職員を辞めたい」と感じているあなたが、将来のキャリアを考える際に、参考にしていただけたら幸いです。
大学職員を辞めてよかったと感じた点3つ(実体験)
- 自分の考えを実現できる環境で働けている
- ワークライフバランスが本当の意味で改善された
- 理不尽な人間関係から解放された
大学職員を辞めてよかった点①|自分の考えを実現できる環境で働けている

民間企業では、大学に比べると意思決定が早く、良いアイデアを実行に移せる文化が根付いている場合が多いです。
大学職員時代は稟議や委員会で時間がかかっていた提案も、転職先では「まずやってみよう」という前向きな姿勢で受け入れてもらえるようになりました。
中期計画や年度計画は民間企業にも存在しますが、市場の動きや社会の変化に合わせて、より柔軟に業務や働き方が変わっていく傾向が強いように感じています。
自分の意見や提案が形になり、結果に直結する経験を通じて、30代からでも新しいスキルを身につけ、キャリアアップを実感できています。
大学職員を辞めてよかった点②|ワークライフバランスが本当の意味で改善された

大学職員時代は、予算編成の時期や年度末、監査対応等があるタイミングで月100時間の残業をすることが頻繁にありました。
また、繁忙期でなくても、正規職員の退職や女性職員の産休・育休のタイミングで、部署内で仕事のしわ寄せが発生することが多く、誰かのワークライフバランスの犠牲になっているという感覚が強かったです。
転職先の規模感や採用方針にもよりますが、女性が多い職場で、かつ、予算や採用計画が硬直的な大学という職場に比べると、民間企業の方が柔軟な対応をしているケースが多いと感じます。
民間企業への転職を経て、今はフリーランス(業務委託)で働いていますが、特に今は大学職員に比べると業務負担が穏やかになっており、体力的にもしんどいと感じることは少ないです。
大学職員を辞めてよかった点③|理不尽な人間関係から解放された
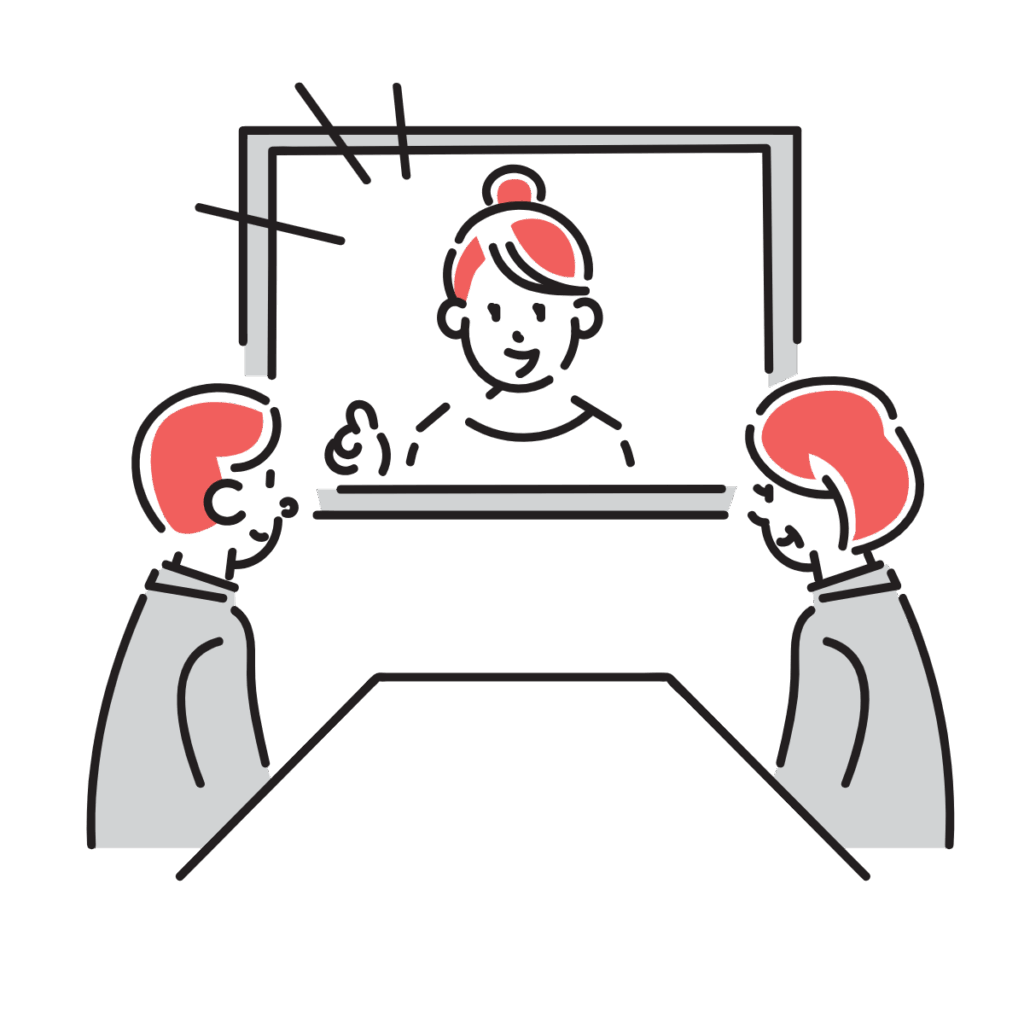
大学職員は人間関係が硬直的で、年功序列の賃金体系のため、理不尽な人間関係に悩まされる場面が多いと感じていました。
わたしの場合は、国公立大学の職員だったため、財政団体からの出向者も多い環境にあり、人件費とパフォーマンスが釣り合わない人とも一緒に働かなければならない環境でした。
教員は、アカデミックの世界しか知らない方も多く、民間企業では通用しないような非常識なことを言う人も一定数いると思います。
民間企業でも、働かない人や変わった人は一定数いますが、それでも大学に比べると「競争の原理」が働くので、理不尽な人間関係は減ったと感じました。
特に今はフリーランスになり、上下関係のストレスがない環境で働けることで、本来の自分らしさを取り戻し、健康的な生活を送れるようになります。
30代が大学職員からの転職を成功させるポイント
転職を成功させるポイント
- 自分が譲れないものを明確にする
- 自分のスキルや経験を棚卸しする
- 転職理由をポジティブに言い換える
- 計画的なスキルアップを行う
- ネットワークを活用する
大学職員から転職を成功させるポイント①|自分が譲れないものを明確にする
転職活動を始める前に、まず自分にとって本当に大切な価値観を整理しましょう。
- 年収アップなのか
- ワークライフバランスなのか
- やりがいなのか
- 成長機会なのか
- 自分の裁量を持って働ける環境なのか
すべてを同時に手に入れるのは困難なため、優先順位をつけることが重要です。
自分が絶対に譲れない条件を3つ程度に絞り込みましょう。
自分が絶対に譲れない条件3つ(具体例)
- 子育てとの両立を最優先にしたい
- 専門性を身につけてキャリアアップしたい
- 人間関係のストレスから解放されたい
 りか
りかこれが転職先選びの軸となり、迷った時の判断基準にもなります
💡転職活動を始める前に、あなたの大切にしたい価値観を言語化しておくと、今後のキャリア選択がしやすくなります。「ライフラインチャート」を使って、価値観を明確にするワークが参考になると思います。


💡 価値観を明確にする上で「仕事に求める14の価値」という考え方も参考になると思います。こちらの記事も参考にしてみてください。


大学職員から転職を成功させるポイント②|自分のスキルや経験を棚卸しする
大学職員として培ったスキルは決して無駄ではありません。
民間企業の転職市場で評価される要素を中心に、スキルや経験を整理しましょう。
棚卸しの具体例
- 学生対応経験:カスタマーサポート・営業スキル
- 教員との調整業務:ステークホルダーマネジメント
- 入試業務・広報活動:マーケティング・企画力
- 予算管理・事務処理:経営管理・業務効率化
- システム導入・データ管理:DX推進・分析スキル
大学職員から転職を成功させるポイント③|転職理由をポジティブに言い換える
「やりがいを求めて」「成長したくて」など、前向きな理由で転職活動を行うことが重要です。
現職への不満ばかりを口にするのではなく、新しい環境で何を実現したいのかを明確に伝えましょう。
転職理由の言い換え(例)
- 年功序列で評価されない→ 「成果に応じて正当に評価される環境で、自分の能力を最大限発揮したい」
- 単調な業務でつまらない→ 「多様な業務に挑戦し、新しいスキルを身につけながら成長したい」
- 給料が上がらない→ 「自分の努力と成果に見合った報酬を得て、将来の目標を実現したい」
- 人間関係がストレス → 「チームワークを大切にし、お互いを尊重し合える職場で働きたい」
- 新しいことに挑戦できない →「革新的なアイデアを形にし、社会により大きなインパクトを与える仕事がしたい」
大学職員から転職を成功させるポイント④|計画的なスキルアップを行う
転職を考え始めたら、目指す業界や職種で求められるスキルをリサーチし、必要に応じて、転職前に必要なスキルを身につけることから始めましょう。
資格取得やオンライン学習など、働きながらでもできることから取り組むことが大切です。
スキル習得の具体例
- デジタルスキル:Excel上級、PowerBI、Salesforce等のツール習得で、どの業界でも重宝される人材に
- 語学力強化:TOEIC700点以上、ビジネス英語を身につけて、グローバル企業や外資系への道を開く
- プロジェクトマネジメント:PMP資格やアジャイル手法を学び、チームをまとめる力をアピール
- 財務・会計知識:簿記2級、FP資格で、経営企画や管理部門への転職に有利
- コミュニケーションスキル:プレゼンテーション、ファシリテーション研修で、対人スキルをさらに磨く
大学職員から転職を成功させるポイント⑤|ネットワークを活用する
大学職員時代に築いた人脈や、同じような転職を経験した「元・大学職員」の先輩からのリアルな体験を聞いてみることも有効です。
自分ひとりで抱え込まず、転職エージェントの活用も含め、様々なチャネルから情報を集めましょう。
ネットワーク活用(具体例)
- 大学時代の同期や先輩・後輩:様々な業界で活躍している人が多く、業界の実情や転職のアドバイスを得られる
- 他大学の職員との交流:研修や会議で知り合った他大学職員から、転職成功事例や求人情報を収集する
- LinkedIn等のSNS:同じ業界への転職を目指す人とのつながりや、転職先候補企業の社員との接点作り
- 転職エージェント・キャリアコンサルタント:専門知識を持つプロから、市場動向や選考対策のサポートを受ける
- 業界セミナーや勉強会:目指す業界の最新情報収集と、現役で働く人々との人脈形成
💡 あなた自身が叶えたい未来があるなら、既に実現している人に会いに行ってみましょう。環境の力を使ってキャリアを成功させる方法をこちらの記事でまとめていますので、活用してもらえたら嬉しいです。


💡 東京都内を中心に、女性限定のオフライン交流会をやっています。お互いの生き方や働き方に刺激を受けられる場にご興味ある方は、こちらの記事もご覧になってください。


30代からでも遅くない!新しいキャリアを始めよう(まとめ)
大学職員は確かに安定した職業ですが、それが必ずしもすべての人にとっての「理想の働き方」とは限りません。
特に30代という人生の重要な時期において、自分らしいキャリアを築きたいと考えるのは自然なことです。
転職は勇気のいる決断ですが、多くの方が「辞めてよかった」と感じているのも事実です。
もし今の環境に疑問を感じているなら、まずは自分の価値観や将来のビジョンを整理することから始めてみてください。
あなたの人生はあなた自身が決めるものです。
30代からでも、新しい挑戦は決して遅くありません。
自分らしいキャリアを築くための第一歩を、今日から踏み出してみましょう。
💡 人事異動が多すぎて疲れている方には、こちらの記事が参考になると思います。キャリアの見通しが立たない場合の対策も解説していますので、今後のキャリアを考える上でヒントになれば幸いです。



-1024x1024.png)