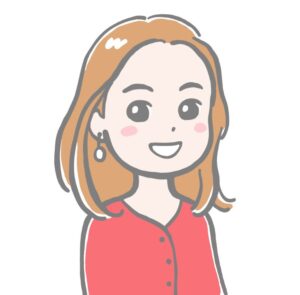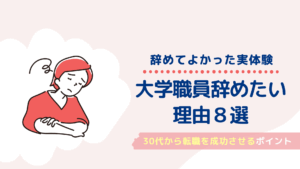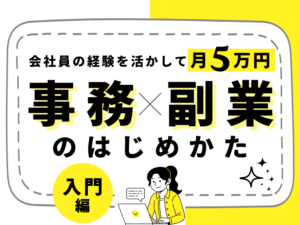大学職員として数年働き、やっと仕事にも人間関係にも慣れてきた頃…
突然の人事異動はやってきます。
新しい部署では仕事内容も人間関係もゼロからのスタートです。
それまで積み上げてきた経験や知識は、ほとんど活かせない場合も多く、「自分は何のために努力してきたのだろう」と虚しさを感じることもありますよね。
この記事では、大学職員に人事異動が多い背景と、異動によって経験や知識がリセットされてしまう現実について整理していきます。
また、そうした環境下でも、できるだけ人事異動に左右されずに、自身のキャリアを築いていくための現実的な対策についても解説します。
この記事が、数年おきにやってくる人事異動に怯えながら仕事に取り組んでいるあなたにとって、自身のキャリアを前向きに築いていくためのヒントになれば幸いです。
大学職員はゼネラリスト|人事異動の実態
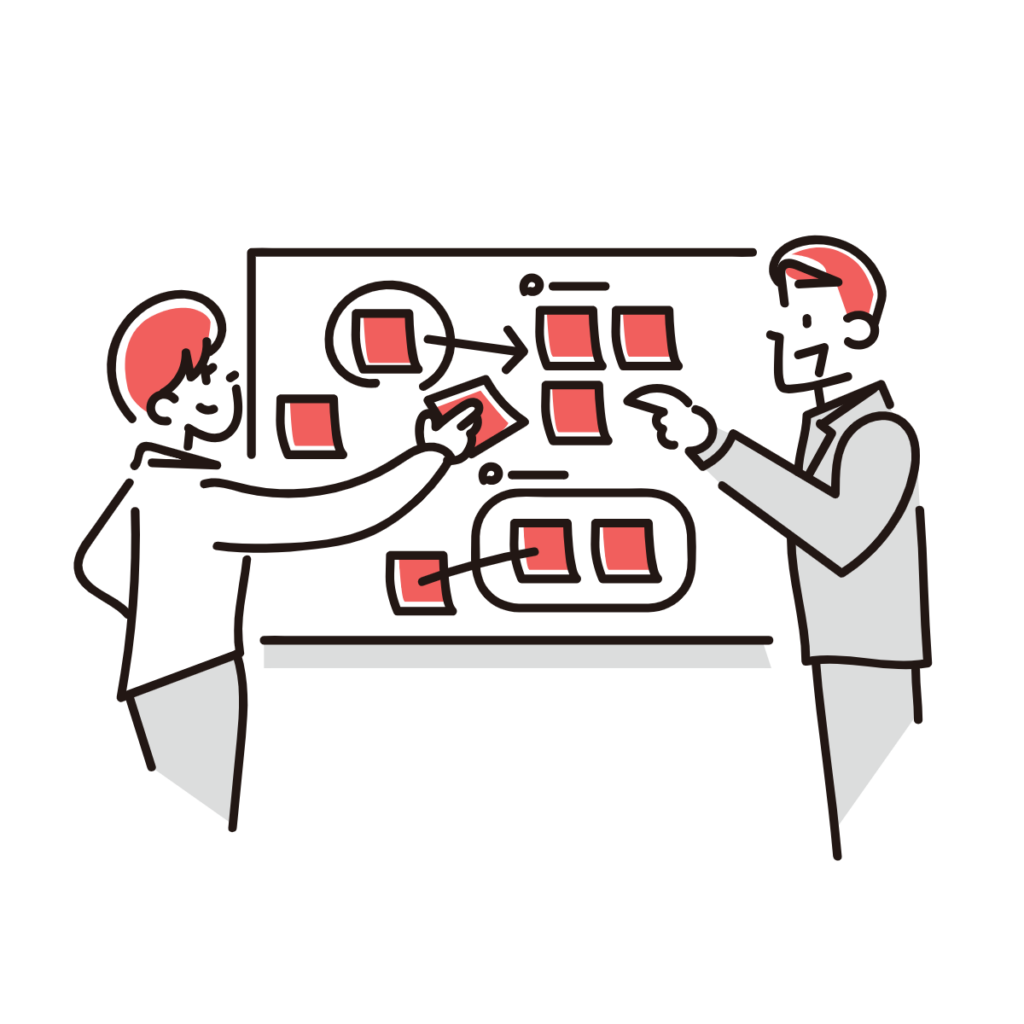
大学職員の人事異動は、企業の総合職と同様に定期的に行われることが一般的です。
多くの大学では2〜5年周期で部署が変わり、異動の範囲も幅広いのが特徴です。
大学職員の人事異動(例)
- 学部間異動(例:文学部 → 理工学部)
- 事務局内異動(例:総務課 → 学生支援課)
- 附属機関への異動(図書館、研究所、附属学校など)
- 他大学や外部機関への出向
このほかにも、会計や施設などお金を扱う部署では、不正防止の観点から一定期間ごとに異動させるケースがあります。
一見すると「多様な経験が積める」というメリットがありますが、実態としては必ずしも人材育成だけが目的ではありません。
人員調整や組織内バランス、特定部署の人間関係リスク回避など、組織の都合が優先されることも多いのです。
大学職員の人事異動がキャリア形成を阻む理由
大学職員の人事異動は、「キャリアの幅を広げる」「ゼネラリストの育成」という建前とは裏腹に、専門性の蓄積を妨げる場合がよくあります。
大学職員の人事異動が個人のキャリア形成を阻む理由を整理してみましょう。
人事異動が大学職員のキャリア形成を阻む理由
- 専門性が積み上がらない
- 長期的な成果が評価されにくい
- 突発的異動で計画が崩れる
人事異動がキャリア形成を阻む理由①|専門性が積み上がらない
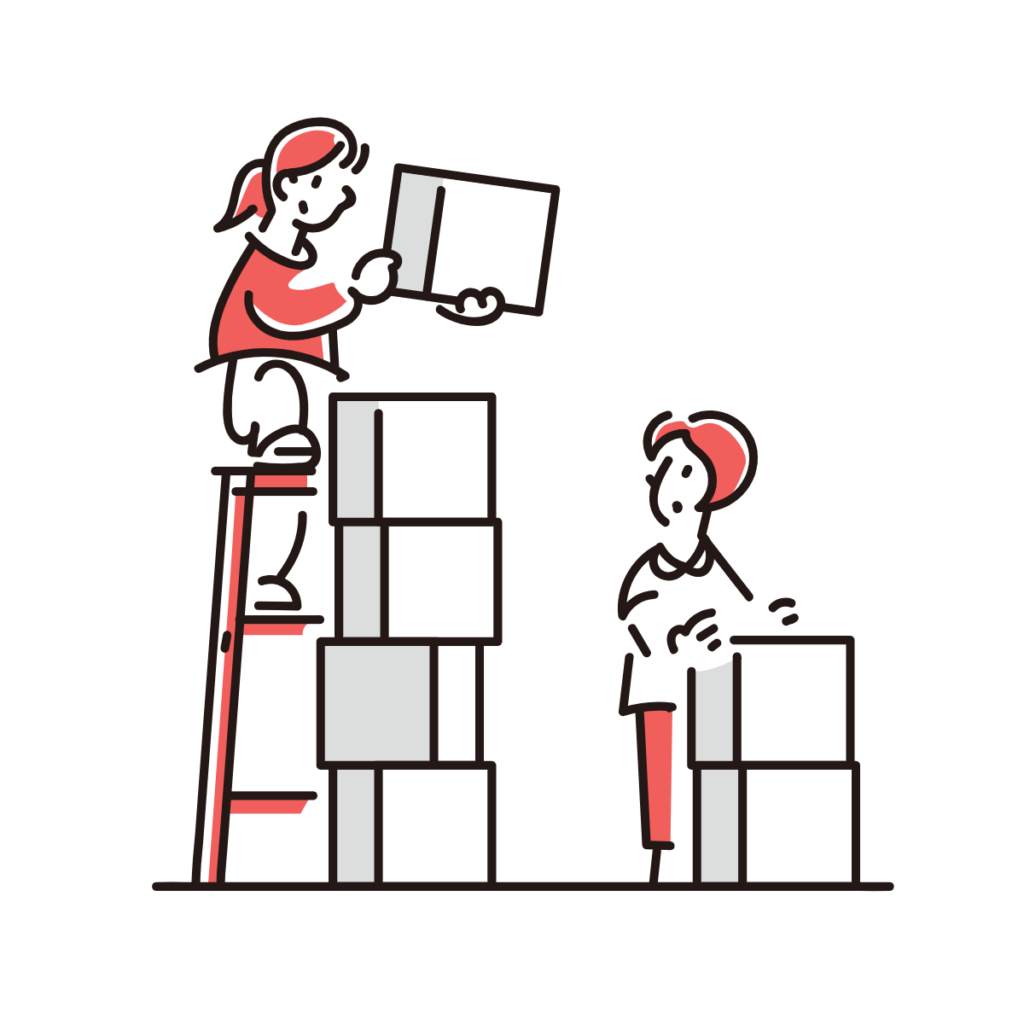
異動先の業務内容がまったく異なる場合、前任部署での経験はほぼ役に立ちません。
例えば、入試業務で培ったノウハウやシステムに関する知識は、学務課や総務課に異動した瞬間に使う機会がなくなります。
人事異動で、業務の関連性が薄い部署を転々としている場合、個人の専門スキルが途切れてしまいがちです。
 りか
りか望まない配属先に異動になると、キャリアの連続性が失われて、リセットされる感覚がやりきれないですよね…
人事異動がキャリア形成を阻む理由②|長期的な成果が評価されにくい
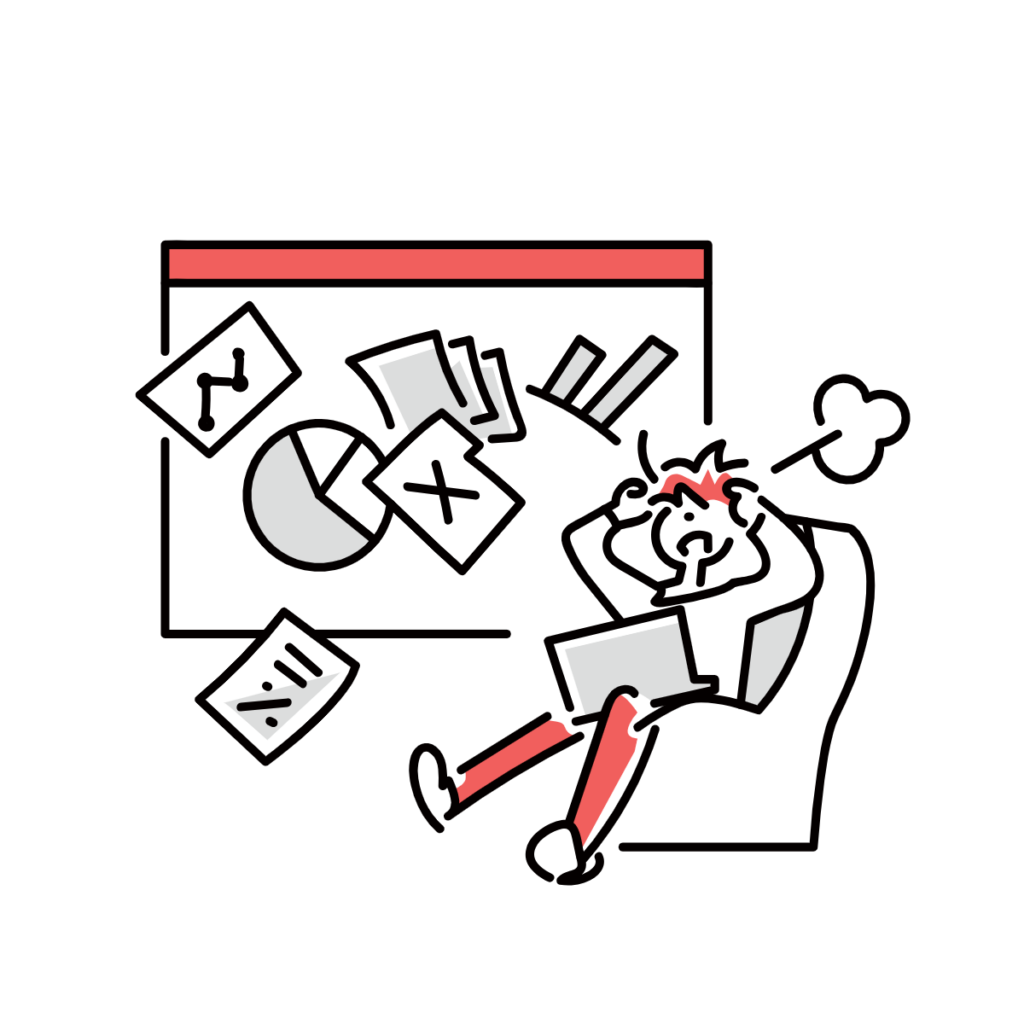
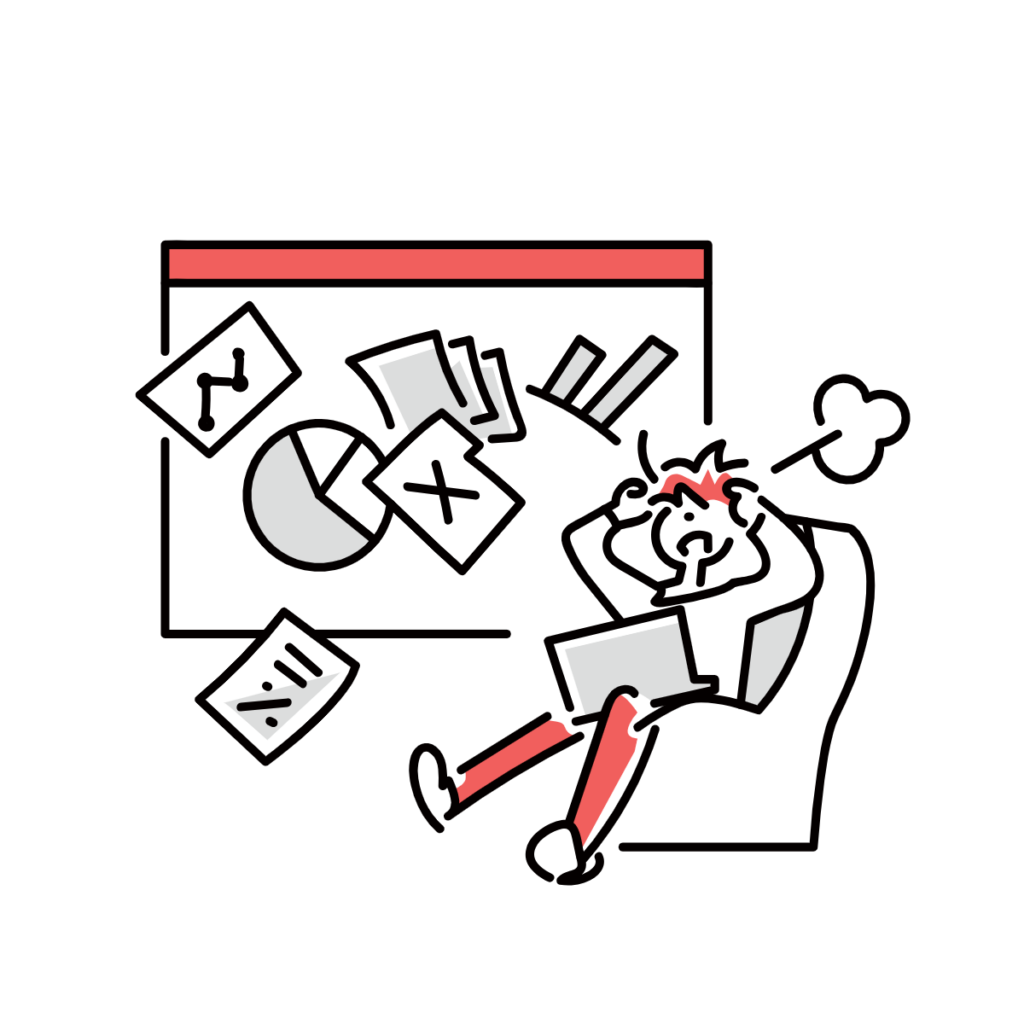
大学には、入試広報や国際交流のように、中長期で成果が出る業務が多く存在します。
このため、予算や計画だけ策定して、実行フェーズを迎える前に人事異動になることも多々あります。
中長期的なプロジェクトに関与した場合、異動のタイミング次第では評価が曖昧になります。



自分が予算だけ作って異動したらプロジェクトは、その後の進捗がシンプルに気になります…
人事異動がキャリア形成を阻む理由③|突発的異動で計画が崩れる
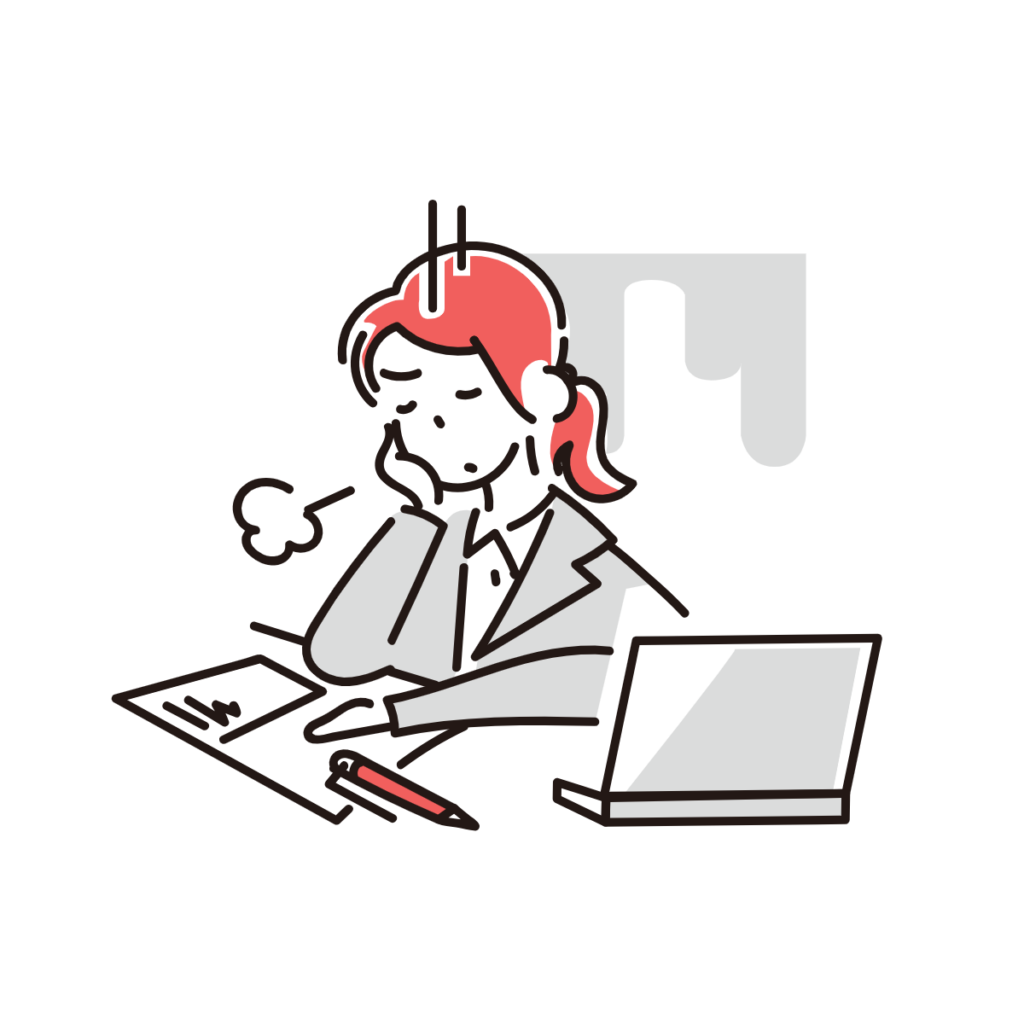
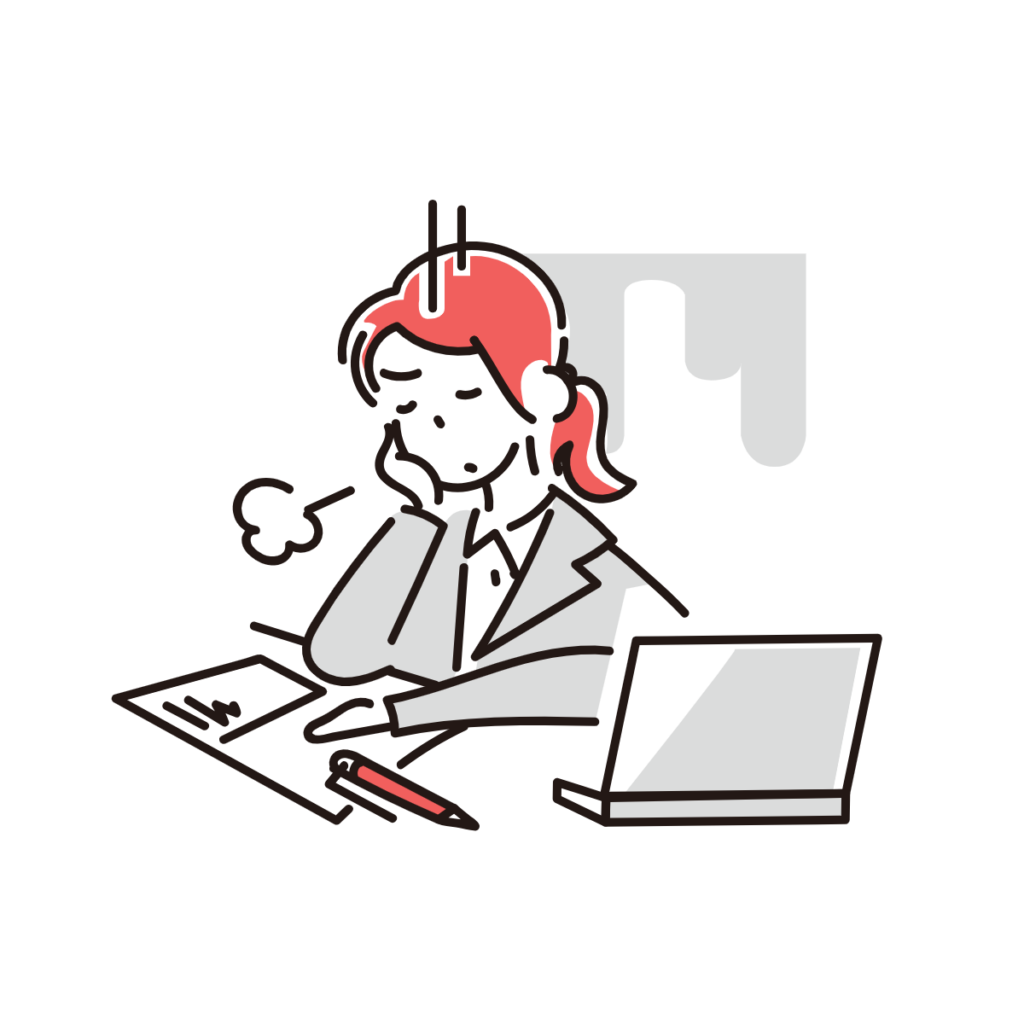
他部署での病気休業や欠員を補填、学部再編等に職員を投入するため等、予期しないタイミングで、突発的な異動が発令される場合があります。
そのようなケースでは、せっかく立てた業務改善の計画や中長期的な目標が途中で途切れてしまうことがあります。
結果的に、キャリア全体の方向性も見えにくくなってしまうのです。



わたし自身も、大学の事務組織で病気休暇が出た関係で、内定者として、予定より早く非常勤職員として入職した経験があります
大学職員の人事異動が与える心理的・実務的ダメージ
異動によるリセットは、心理的にも実務的にも職員個人に与えるダメージが大きいです。
代表的なものとしては、以下の3つが挙げられます。
人事異動が与えるダメージ(例)
- モチベーション低下:努力して成果を上げても、その成果を次の異動先で活かせないと「頑張る意味がない」と感じやすくなります。
- 仕事をイチから覚えなおすストレス:新しい業務フローやシステム、関係者の名前を覚える負担は大きく、精神的疲労につながります。
- 評価・昇進の遅れ:途中で異動すれば、長期的成果が評価に反映されにくく、結果として昇進や昇給にうまくつながらないケースがあります。
大学職員の人事異動が向いている人・向いていない人
大学職員、特に事務職員はゼネラリストとしての人事異動を前提にキャリアを積んでいきます。
そのため、この働き方に向いている人と向いていない人がはっきり分かれます。
ここでは、特に人事異動やキャリア形成という観点から、大学職員に向いている人と向いていない人の代表的な特徴をお伝えします。
大学職員の人事異動が向いている人の特徴


まずは、大学職員の人事異動やゼネラリストとしての働き方が向いている人の代表的な特徴を3つご紹介します。
大学職員に向いている人の特徴3つ
- 組織で安定的に働きたい人
- 出世志向が強い人
- 環境の変化を前向きに受け入れられる人
組織で安定的に働きたい人
一つの大学に腰を据えて、安定した環境で長く働きたいと考えるタイプです。
異動はあくまで組織の一部として受け入れる姿勢を持てるのであれば、大学職員として長く勤めることができるでしょう。
出世志向が強い人
異動を通じて幅広い経験を積み、将来的に管理職や幹部を目指すタイプです。
大学職員の人事制度は、ゼネラリスト的な人材育成方針をポジティブに捉えられる人に合っていると言えます。
環境の変化を前向きに受け入れられる人
異動を「新しいことを学べる機会」と捉え、柔軟に順応できるタイプです。
新しい人間関係づくりや業務習得に抵抗が少ない人には、働く環境としてはあっているでしょう。
大学職員の人事異動が向いていない人の特徴
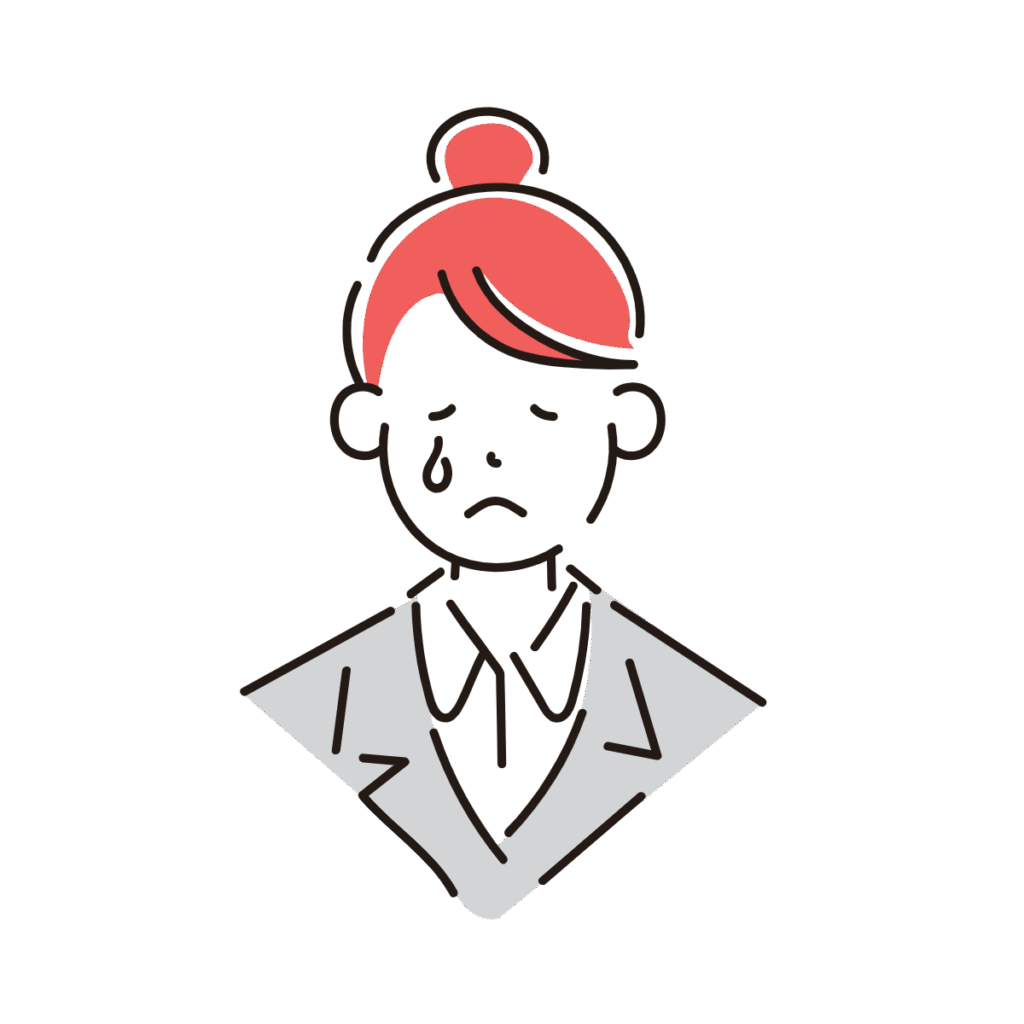
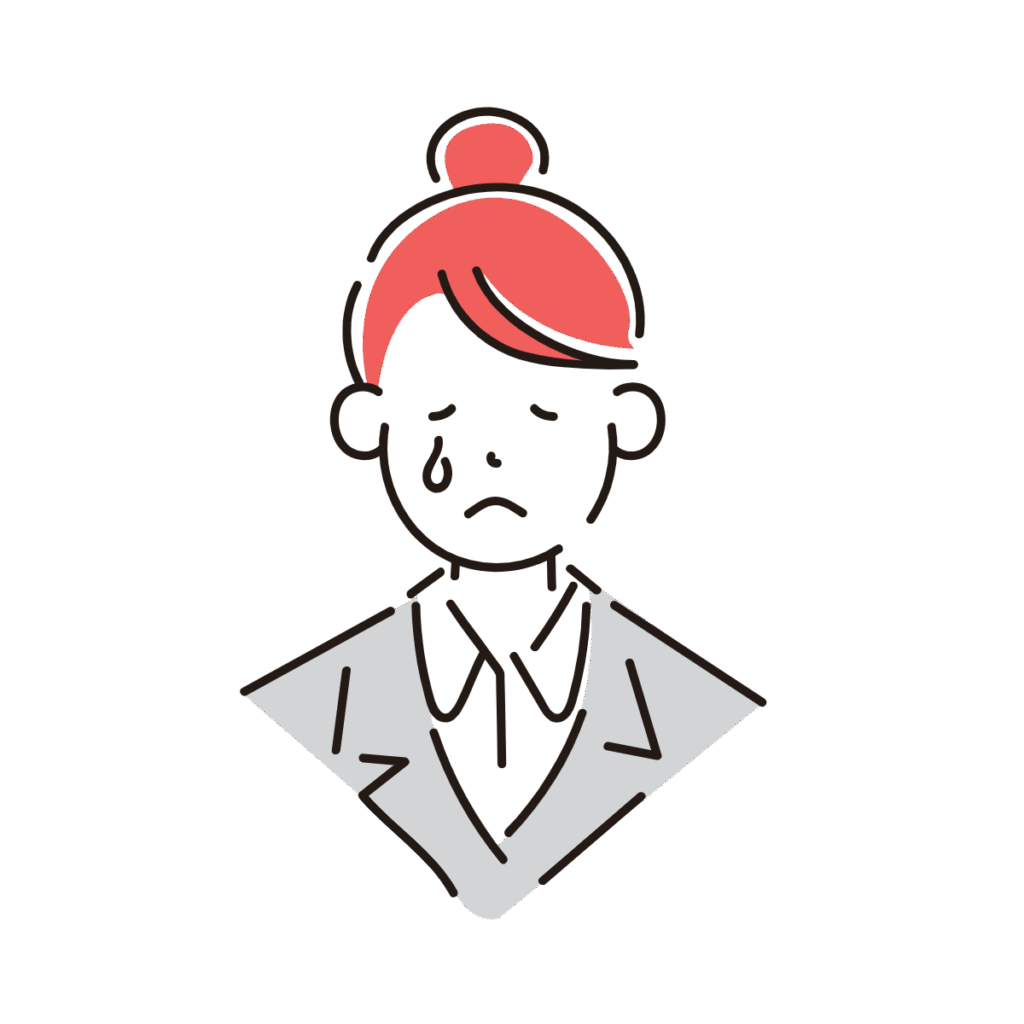
次に、大学職員の人事異動やゼネラリストとしての働き方が向いていない人の代表的な特徴を3つご紹介します。
大学職員が向いていない人の特徴3つ
- 専門性を深めたい人
- 計画的にキャリアを積みたい人
- 環境の変化にストレスを感じやすい人
専門性を深めたい人
一つの分野で専門家としてキャリアを築きたい人にとって、頻繁な異動は大きな妨げとなります。
計画的にキャリアを積みたい人
「数年後にはこの領域で成果を出す」と長期的な目標を立てたり、中長期的なプロジェクトで成果を上げたいと考えている人にとっては、大学職員の人事異動は不確定要素が強すぎます。
環境の変化にストレスを感じやすい人
環境の変化にストレスを感じやすい人は、新しい部署や業務を一から覚えることが大きな負担になります。
異動のたびに精神的に疲弊しやすく、人事異動に振り回されてしまうでしょう。
💡 ゼネラリストとして働くことが向いている人と向いていない人がいます。あなた自身の「キャリア・アンカー」を知っておくと、今後のキャリア選択がしやすくなります。良かったら、こちらの記事も参考にしてみてください。


大学職員が人事異動でキャリアの見通しが立たないときの対策
ここまで見てきていただいたように、人事異動の多い働き方である大学職員は「向いている人」「向いていない人」がはっきりと分かれます。
どちらのタイプであっても、将来の不確実性や異動によるリセットの影響を完全に避けることはできません。
全員に共通する「キャリアの見通しが立たない」という悩みへの対策、大学職員に向いている人と向いていない人、それぞれの対策を考えていきます。
キャリアの見通しが立たないときの対策
- 大学職員として共通する人事異動への備え
- 「大学職員に向いている」と感じる人の対策
- 「大学職員に向いていない」と感じる人の対策
大学職員として共通する人事異動への備え
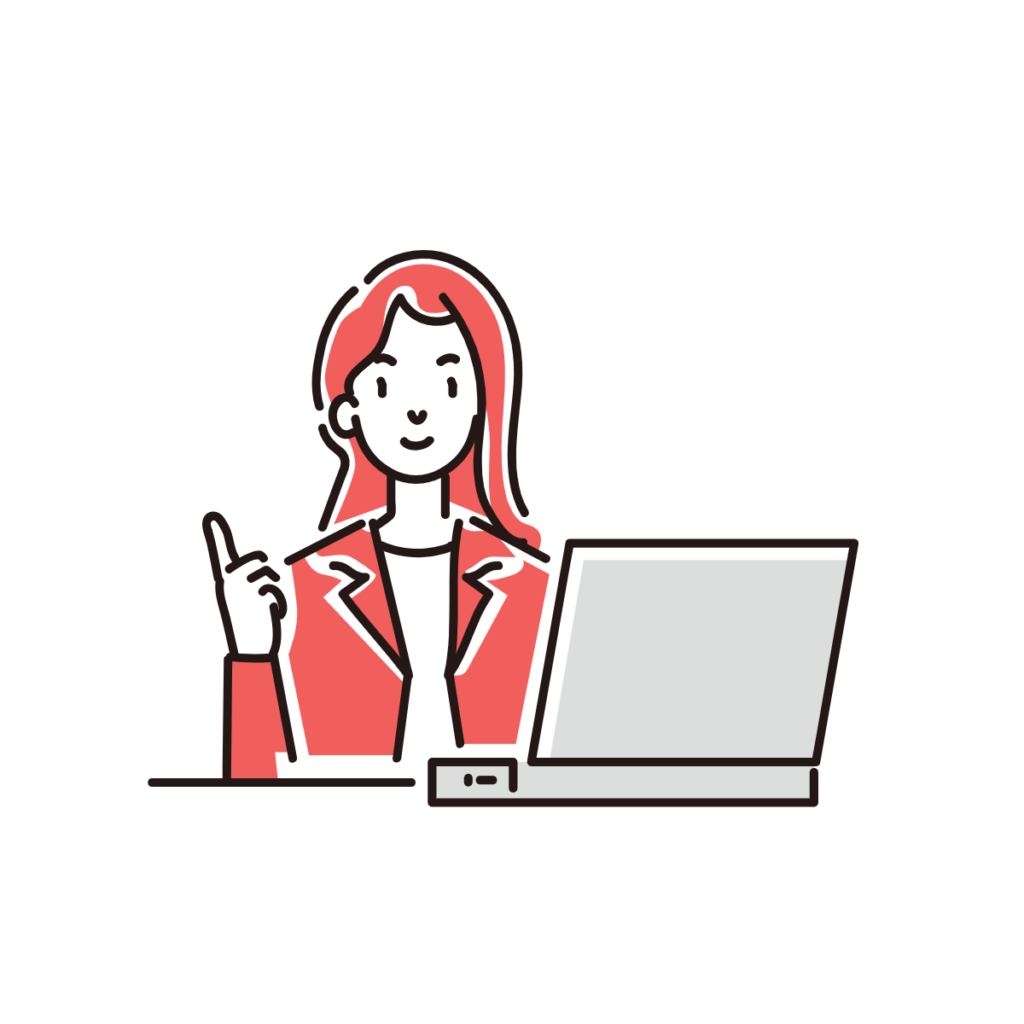
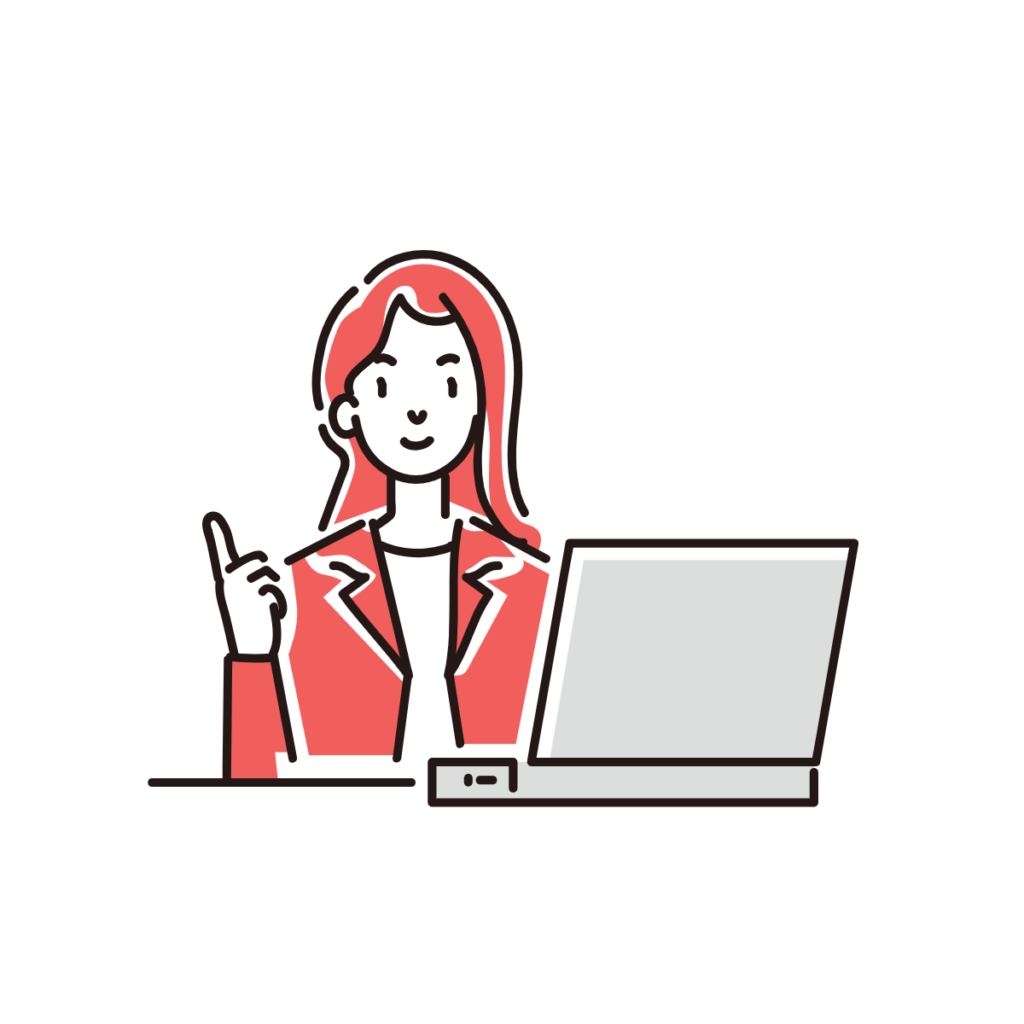
スキルや経験をポータブルな形で残す
異動で経験がゼロになるのを防ぐために、成果物や改善経験をまとめておきましょう。
個人用に要約・整理しておけば、大学内外で役立つ資産になります。
ネットワークを多層化する
部署をまたいだ大学内の人脈だけでは、視野が狭くなりがちで、新しい情報も入ってきづらいです。
他大学や教育関連機関、学会やオンラインコミュニティなど外部とのつながりも築いておくのも良いでしょう。
市場価値を把握しておく
転職サイトやエージェントを定期的に利用して「自分の経験は外でどう評価されるか」を把握しておきましょう。



すぐに転職をしなくても、あなた自身の市場価値を客観的に把握できることで、精神的な安心感も得られます。
「大学職員に向いている」と感じる人の対策
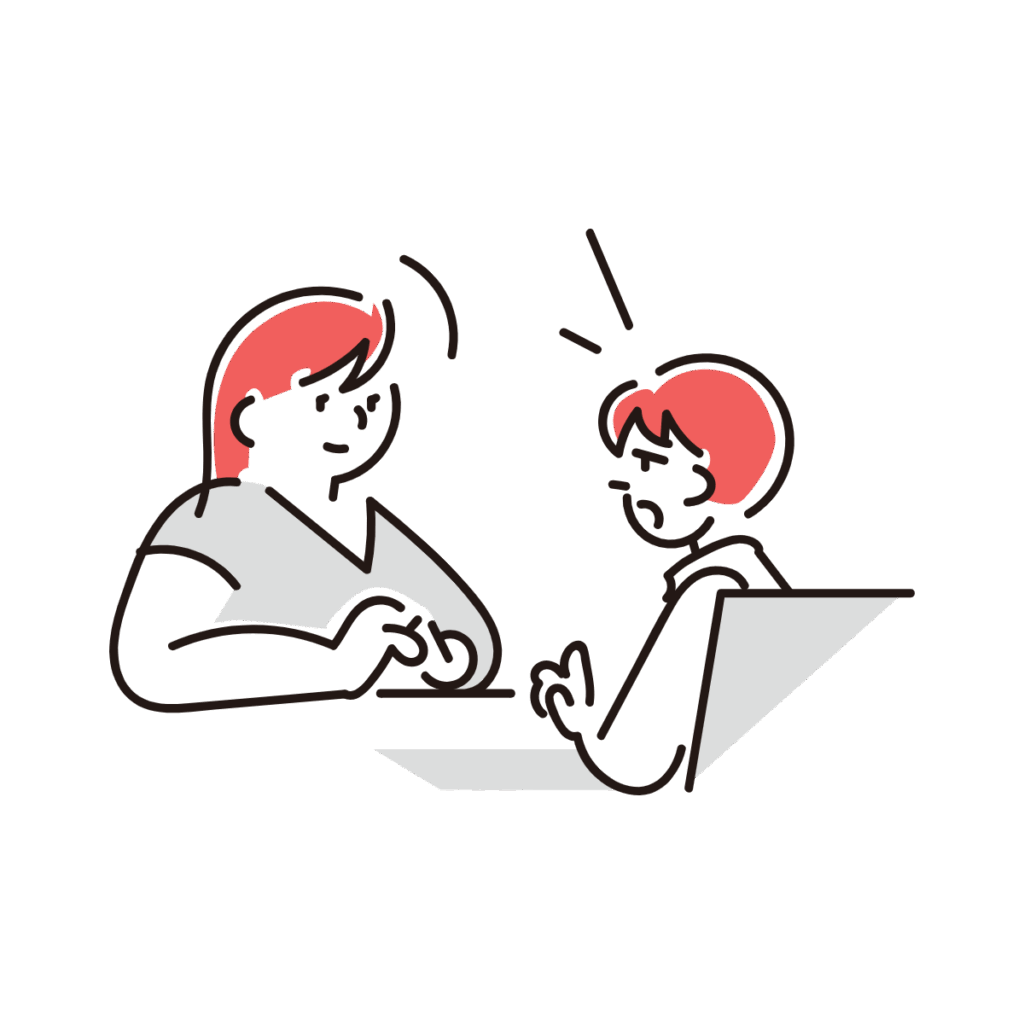
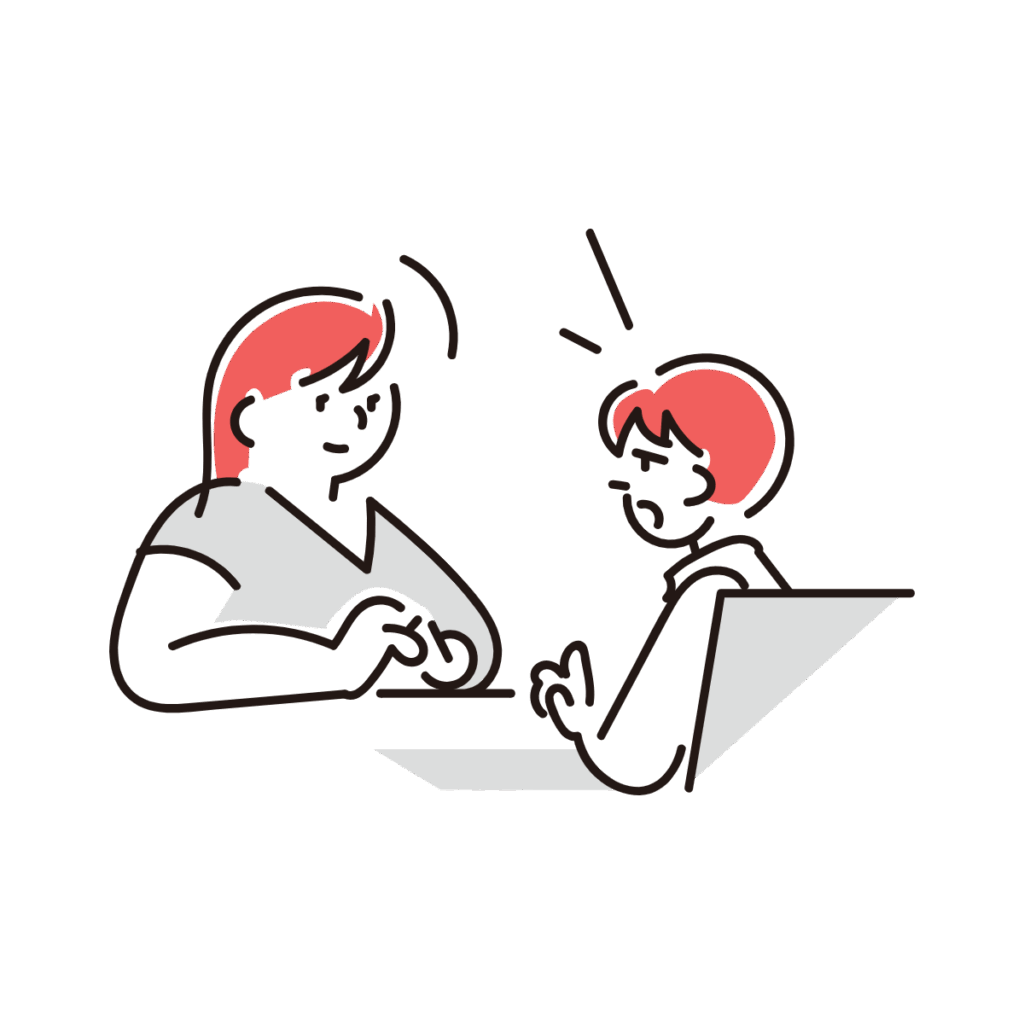
対策①|異動を経験値として資産化する
異動ごとに「学んだこと」「成果」をスキル棚卸しして記録しましょう。
履歴書や昇進試験でも語れる形に残しておくのがお勧めです。
対策②|ゼネラリスト経験を強みに変える
複数部署を経験したことで得られる「大学全体を俯瞰できる視点」は、管理職候補にとって大きな強みです。
出世志向がある人は、その経験を積極的にアピールしましょう。
対策③|安定志向なら生活基盤を整える
「どこに異動しても困らない生活基盤」を意識しましょう。
通勤圏の選び方、家族との役割分担など、ライフスタイル面での備えも重要です。



大学職員としてゼネラリストのキャリアを歩めるタイプであっても、「安心して長く続けられるかどうか」は別問題です。
頻繁に訪れる人事異動をポジティブに活かす工夫が必要です。
「大学職員に向いていない」と感じる人の対策
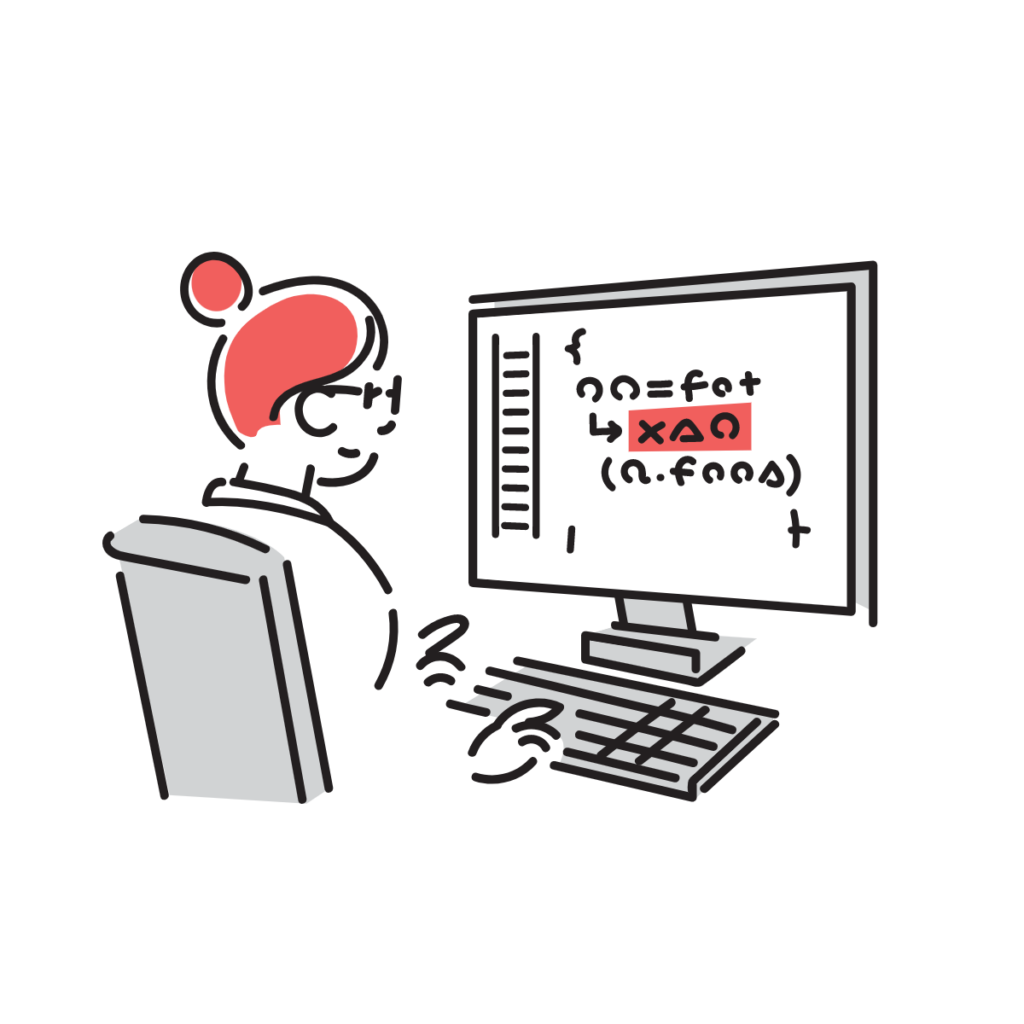
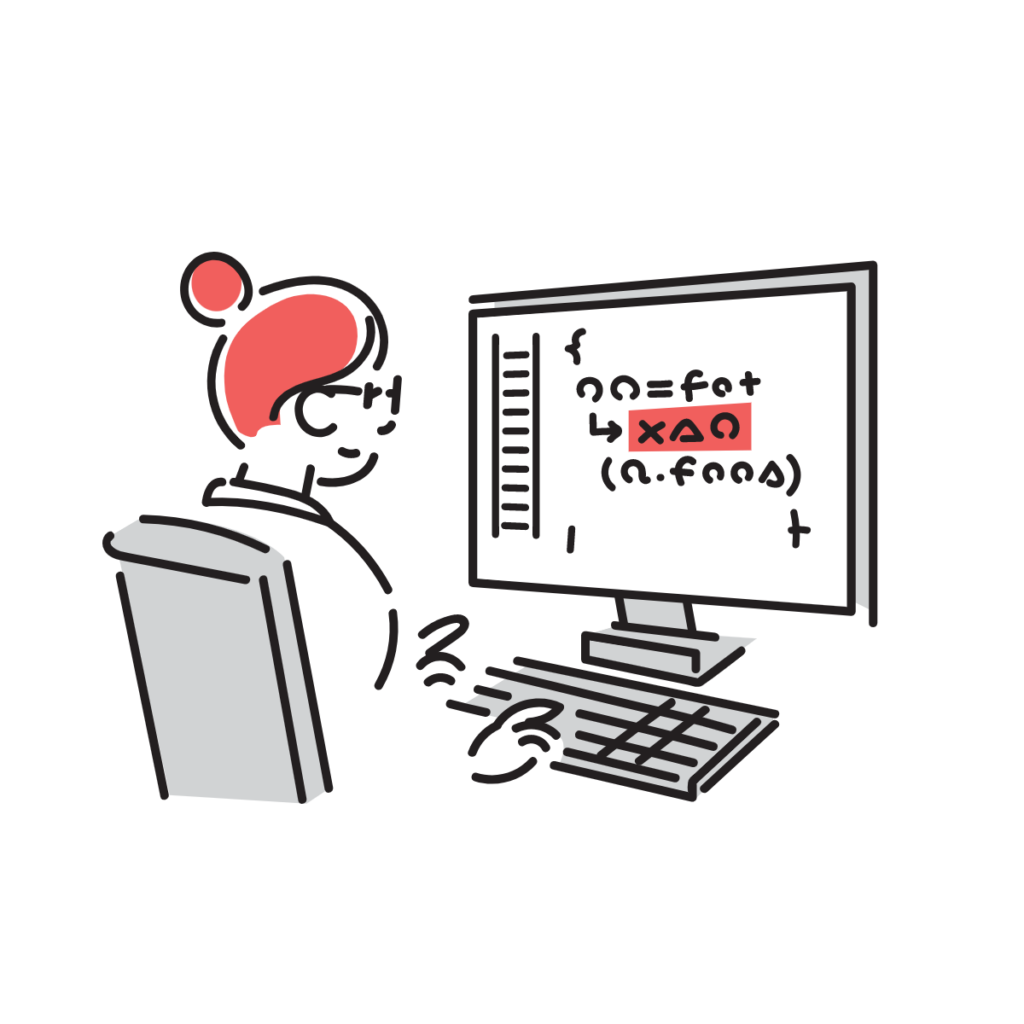
対策①|他大学や教育関連機関への転職
大学職員の経験は教育業界での評価が高い傾向にあります。
特にIR、国際交流、学生支援などの専門領域は強みになります。
対策②|大学内の専門職を志す
IR室、法務、情報システム、施設管理など、専門性を軸にキャリアを築けるポジションも、少ないながら存在します。
そういった専門職へのキャリアチェンジを検討するのも一つの手段です。
対策③|大学外にキャリア資産を築く
資格取得、勉強会への参加、学会活動などを通じて、異動に左右されない「自分の専門性」を育てましょう。
これが将来的にも、あなた自身のキャリアの「資産」になります。



ゼネラリストとしての異動を受け入れるのが難しい人は、別の選択肢を持つことが大切です。
💡安定した職場環境だからと言って、個人の将来性が保障されているとは限りません。大学職員として働き続けることに「将来性がないのでは?」と不安を感じている方は、こちらの記事が参考になると思います。


大学職員の人事異動に備え、自分らしいキャリアを築く(まとめ)
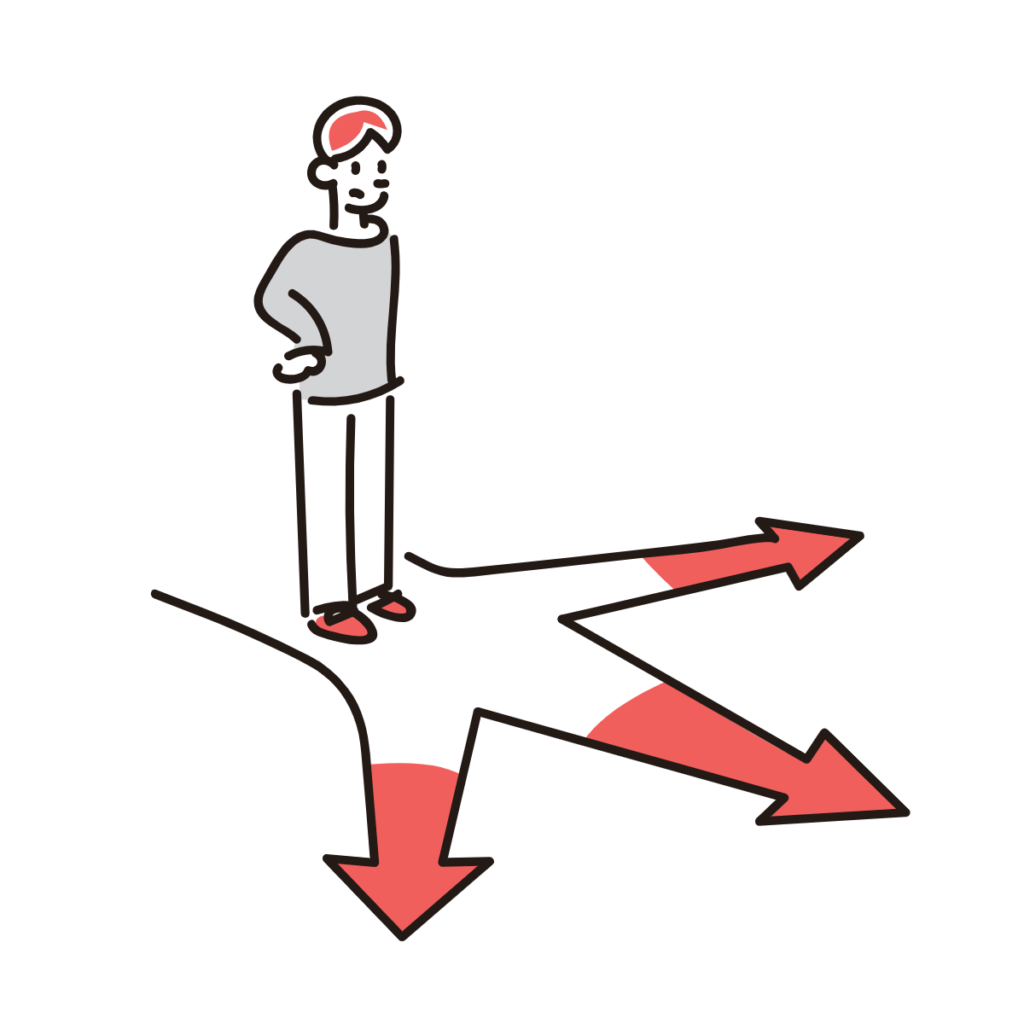
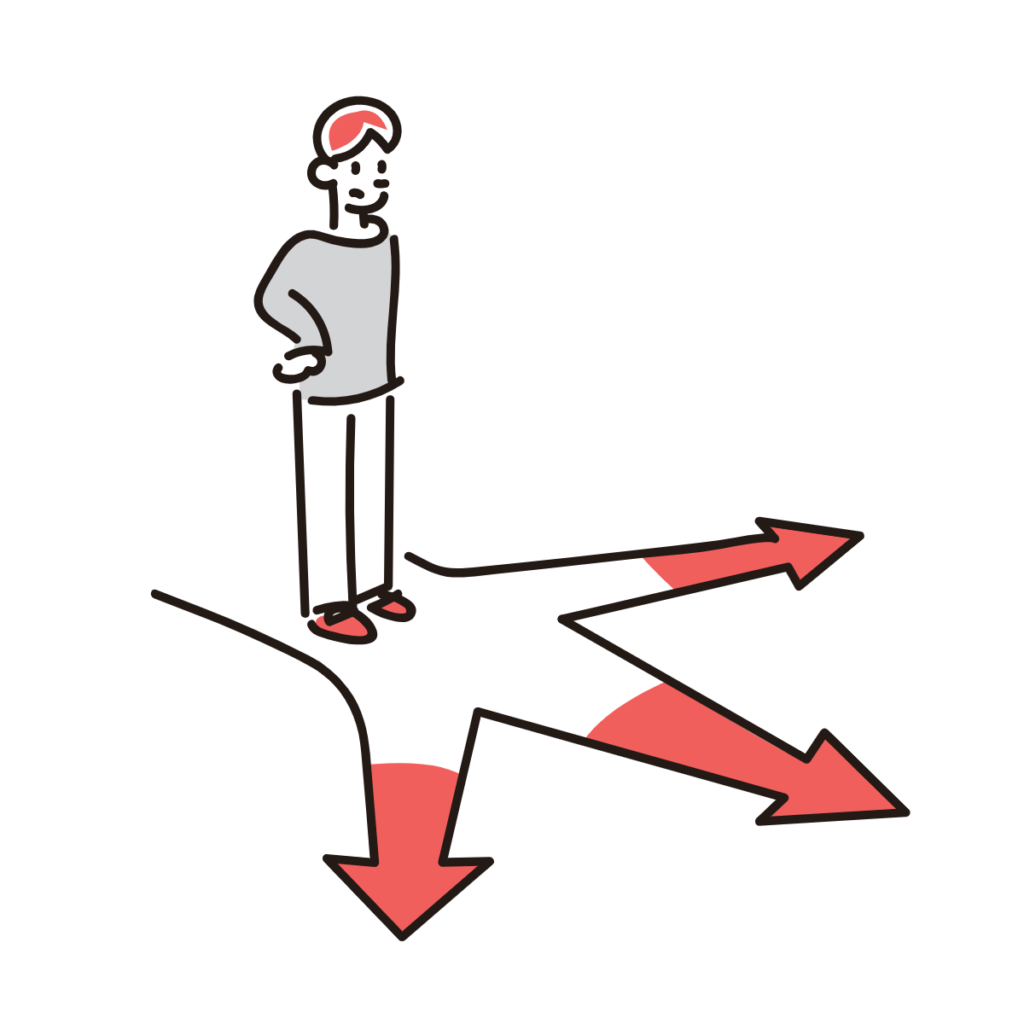
大学職員の人事異動は、避けたくても避けられない現実です。
そして、その異動がキャリアや知識の積み上げをゼロにすることも珍しくありません。
だからこそ、環境に依存しない形でスキル・知識・人脈を、個人レベルで蓄積し続けることが重要です。
次にどんな部署に行かされても、わたしの仕事の価値は変わらない
そう思えるだけの備えを持っていれば、異動のストレスはぐっと軽くなります。
そして、それは大学職員としてだけでなく、あなた個人の将来のキャリア全体にとっても大きな蓄えになるはずです。
💡 大学は安定した職場ですが、それでも「辞めたい」と感じる人が一定数いるのも事実です。わたし自身が大学職員から転職した実体験を書いた記事がありますので、キャリア選択の参考にしていただけると幸いです。


💡 大学という職場は年功序列で、昇給と評価がかみ合わないことが多いです。給与や待遇面での限界を感じている方には、こちらの記事が参考になると思います。



-1024x1024.png)