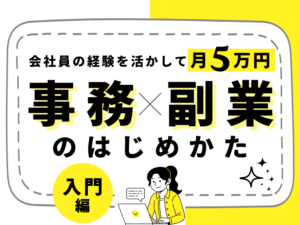「人脈を広げるなら異業種交流会に行こう!
フリーランスや独立を考え始めた人なら、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
名刺を配って顔を売り、そこから新しいチャンスや仕事につなげる…そんなイメージを持っている方は多いと思います。
けれど、実際に参加してみると「思ったほど意味がないのでは?」と感じる人も少なくありません。
わたし自身も独立初期にいくつかの異業種交流会に参加しましたが、メリットよりもデメリットの方が印象に残っています。
今回は、フリーランスを目指している会社員や独立したばかりのフリーランスの方に向けて、異業種交流会のメリットとデメリットを実体験ベースで解説していきます。
そもそも、異業種交流会とは?
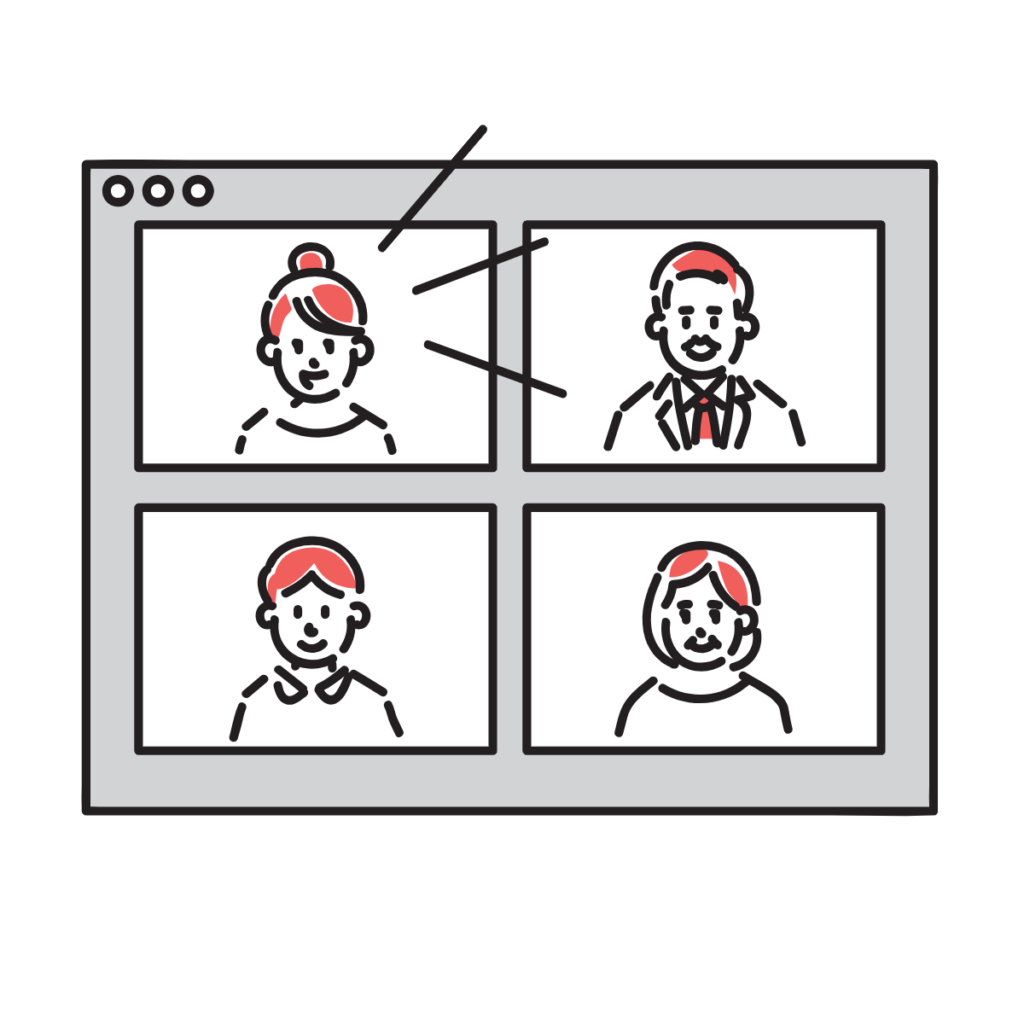
異業種交流会とは、その名のとおり
です。
形式はさまざまで早朝に行う朝活スタイルやランチ会、夜の立食パーティー型、最近ではオンライン交流会も増えています。
参加費は数千円程度が多く、気軽に参加できるのが特徴です。
「普段は出会えない人と知り合える」「刺激を受けられる」という期待感から、独立初期のフリーランスや経営者が足を運びやすい場だと言えるでしょう。
異業種交流会で得られるメリット
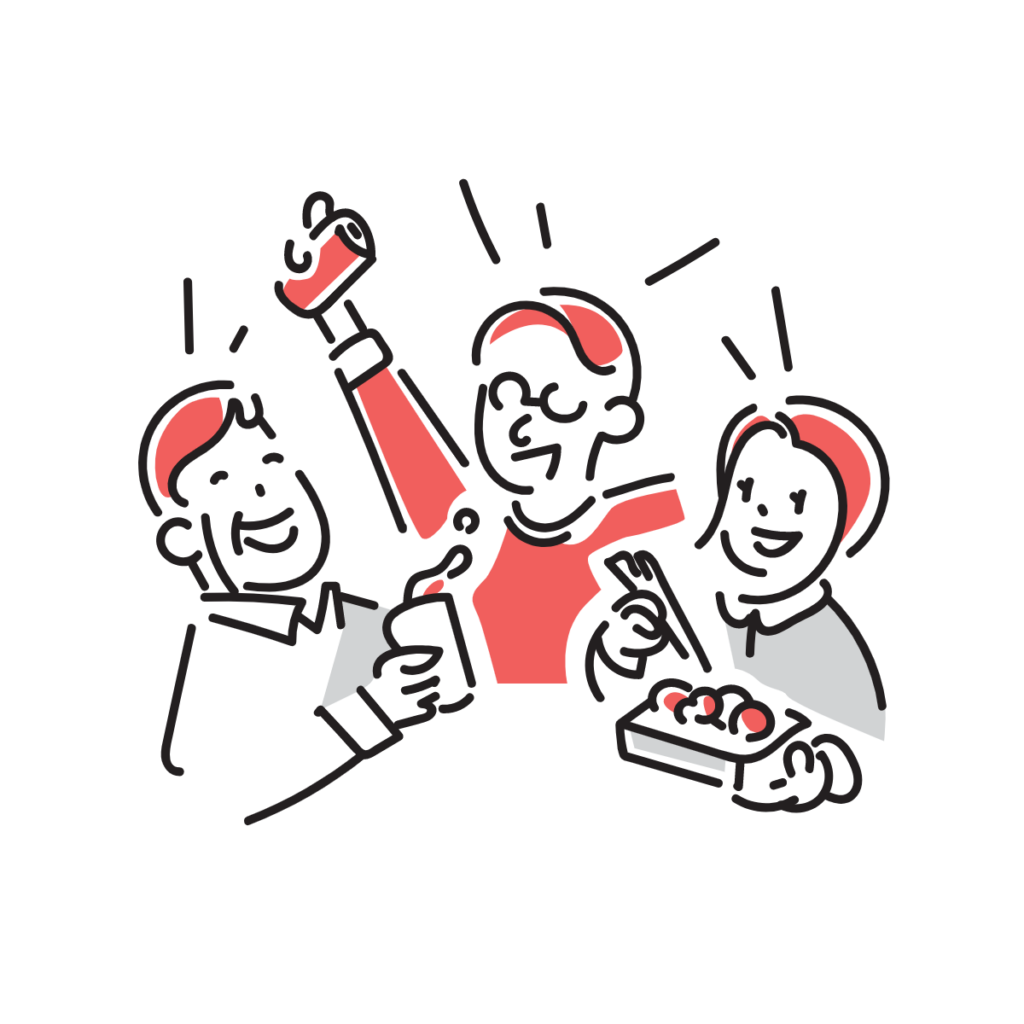
実際に参加してみて、「全く意味がなかった」というわけではありません。
一定のメリットはありると思います。
異業種交流会で得られるメリット
- 情報が得られる:普段接点のない業界の人から話を聞ける
- 営業の練習になる:自分のサービスや活動を短時間で説明する機会が持てる
- 刺激を受けられる:独立して頑張っている人の話からモチベーションが上がる
わたし自身も、最初に参加した交流会では「自分の仕事をどう説明するか」という自己紹介やプレゼンテーションの練習の場にはなりました。
短い時間でわかりやすく話す必要があるので、コミュニケーション力を鍛える場にはなります。
異業種交流会のデメリット5選
異業種交流会には確かにプラスの面もありますが、独立初期のフリーランスにとっては注意すべき落とし穴も多くあります。
実際に参加してみて感じたのは、メリット以上に「時間や労力に見合わない側面」が目立つということでした。
ここでは、その代表的なデメリットを紹介します。
異業種交流会のデメリット5選
- 名刺交換だけで終わりがち
- 発注力がない人が多い
- 役職や役割を持つと負担が大きい
- 紹介案件の質が微妙になりやすい
- 交流会そのものが目的化するリスク
異業種交流会のデメリット①|名刺交換だけで終わりがち

異業種交流会の場では名刺を何十枚も交換しますが、その後に続くことはほとんどありません。
確率でいうと、10%未満だと思います。
名刺交換をした後に、積極的に自分から連絡を取らない限り、後日に先方から連絡が来て具体的なビジネスの話に繋がることは、ゼロではないですが稀です。
異業種交流会のデメリット②|発注力がない人が多い
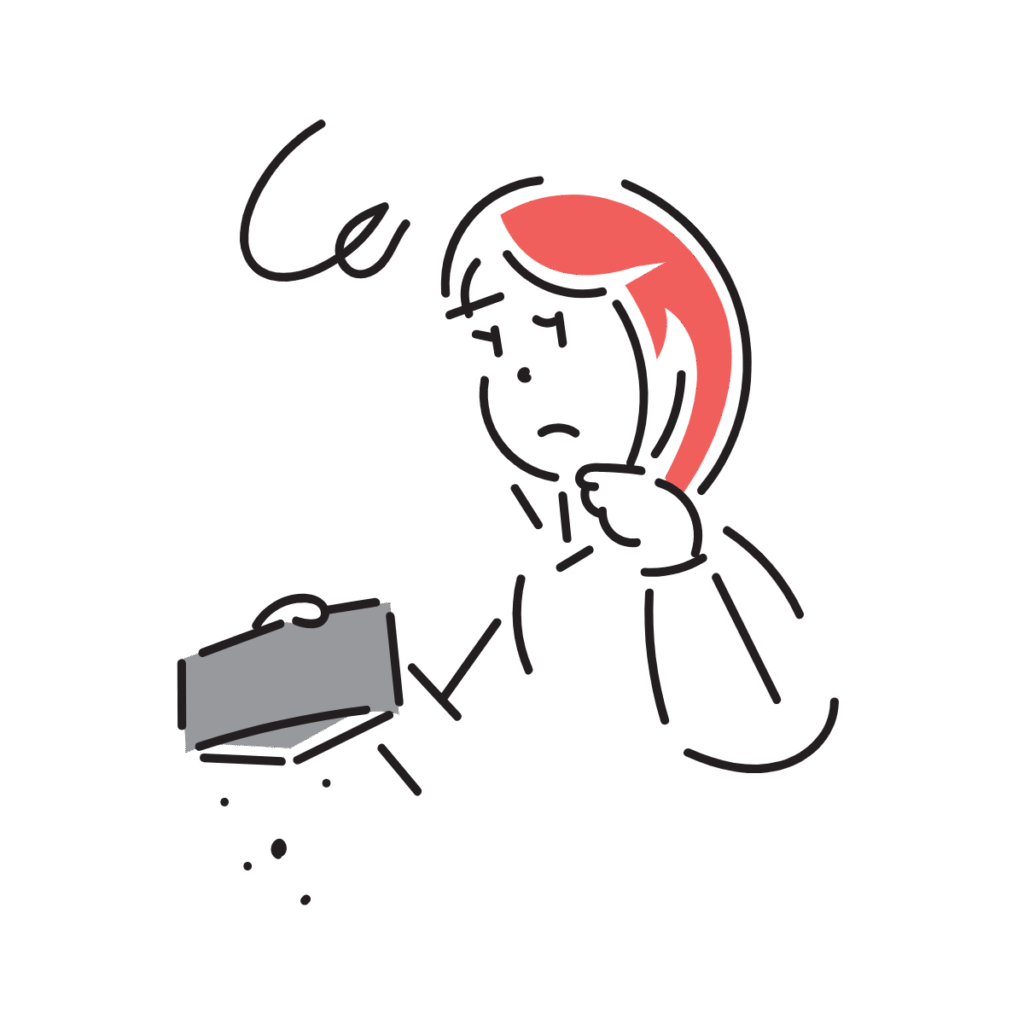
売上を目的として、異業種交流会に参加する方も多いと思います。
つまり、異業種交流会への参加者の多くは「仕事が欲しい人」、営業をしたい立場の人がほとんどです。
駆け出しのフリーランスや個人事業主も多く、そもそも案件を発注するほどの予算や規模を持っていない人が大半です。
結果として、「案件をもらう場」というより「案件を取り合う場」になりやすい構造があります。
異業種交流会のデメリット③|役職や役割を持つと負担が大きい
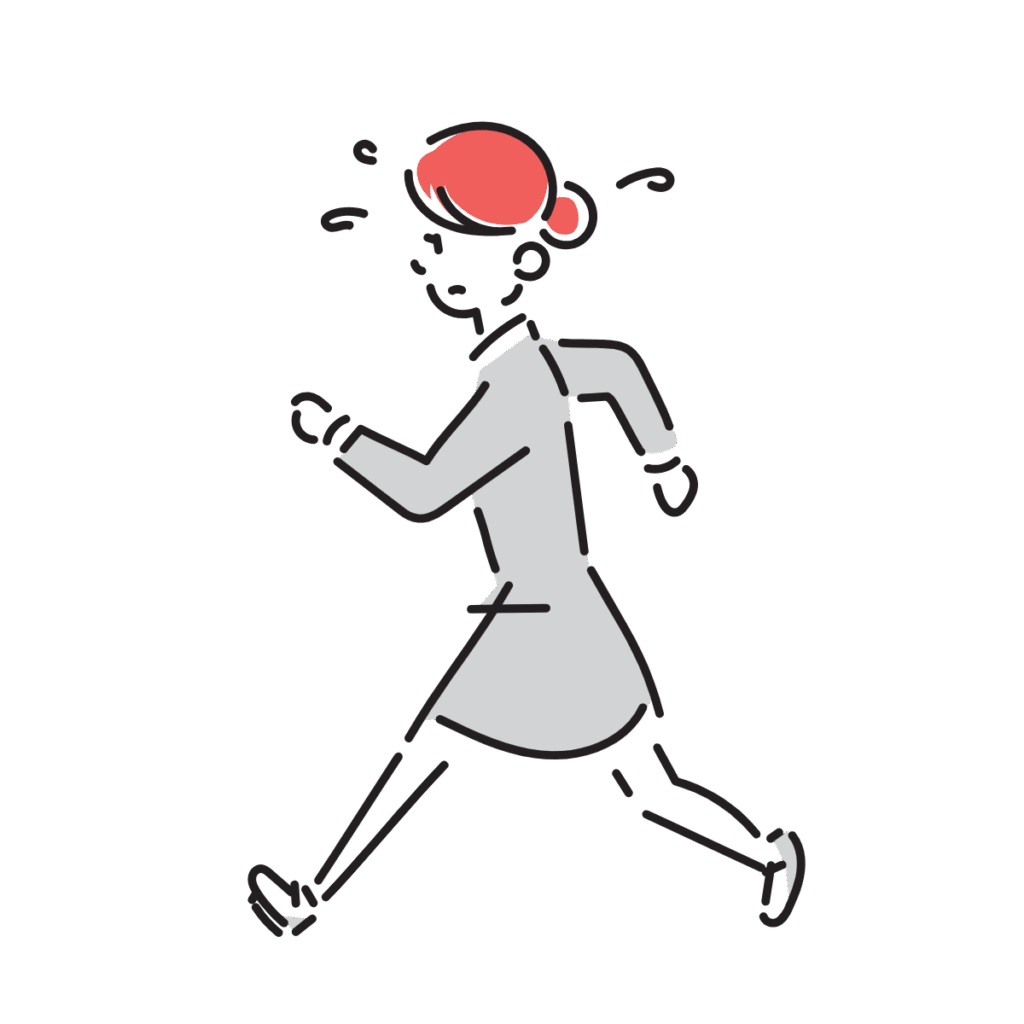
異業種交流会では、幹事や役員などの役割が回ってくることがあります。
すると、イベント運営や調整に時間を取られるようになります。
これらは売上に直結しないタスクなので、異業種交流会自体の運営にクライアントワークの時間を削られるのは大きな痛手だと思います。
異業種交流会のデメリット④|紹介案件の質が微妙になりやすい
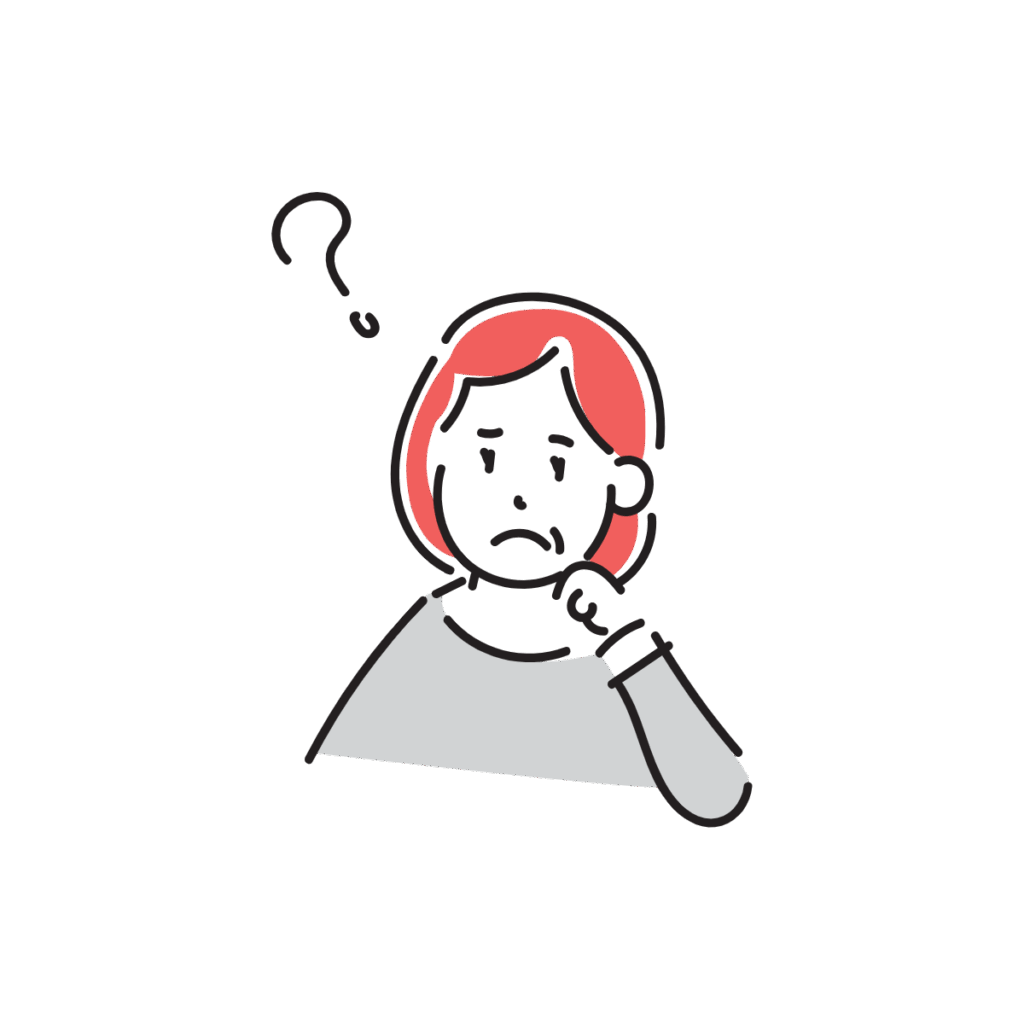
異業種交流会での繋がりから派生して、お仕事を紹介していただけるケースはあります。
ただし、紹介件数をKPIにしている異業種交流会の場合は、紹介する側の都合が優先されて雑なマッチングになるケースも多いと感じました。
仕事内容や条件面が自分の希望とマッチしなくても、紹介者の義理で断りづらかったり、料金を優遇せざるを得なかったりするケースもあります。
ご紹介でお仕事はいただけるけれども、人間関係を優先しすぎずに、しっかり選んで引き受けないと、精神的にも経済的にも負担になりやすいです。
異業種交流会のデメリット⑤|異業種交流会そのものが目的化するリスク
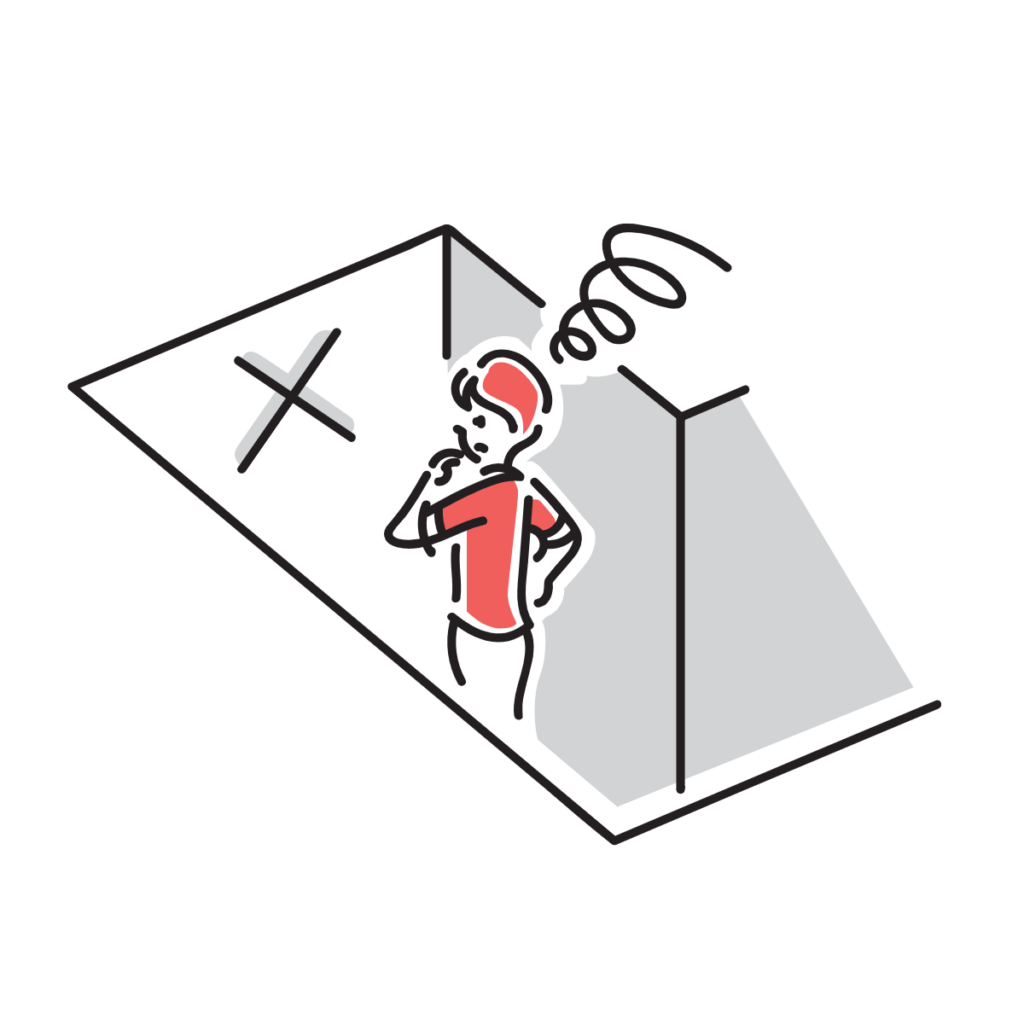
異業種交流会に参加している人のなかには、異業種交流会に参加すること自体が目的になっている人もたくさんいます。
行政書士や婚活アドバイザー等、自営業で活動している方が、異業種交流会の活動に熱を入れすぎて本業がおろそかになっているのを実際にお見掛けしました。
また、異業種交流会では、会長や副会長といった役職が輪番で回ってくることがあります。
形式上は運営を支えるための仕組みですが、実際にはその役職に強いこだわりを持ち、優先順位を高く置く人も少なくありません。(特に男性に多い印象)
本来は交流会で学んだことを自分のビジネスに活かすべきですが、異業種交流会自体が自己目的化してしまい、本末転倒となっている人が結構います。
異業種交流会への参加から学んだこと(実体験)
実際に私自身が異業種交流会に参加して感じたことを振り返ると、大きく二つの学びがありました。
それぞれを詳しくお伝えします。
異業種交流会への参加から学んだこと
- 売上目的で異業種交流会に行くのは遠回り
- 成長目的で参加するなら意味はあるが「場選び」が大切
実体験からの学び①|売上目的で異業種交流会に行くのは遠回り
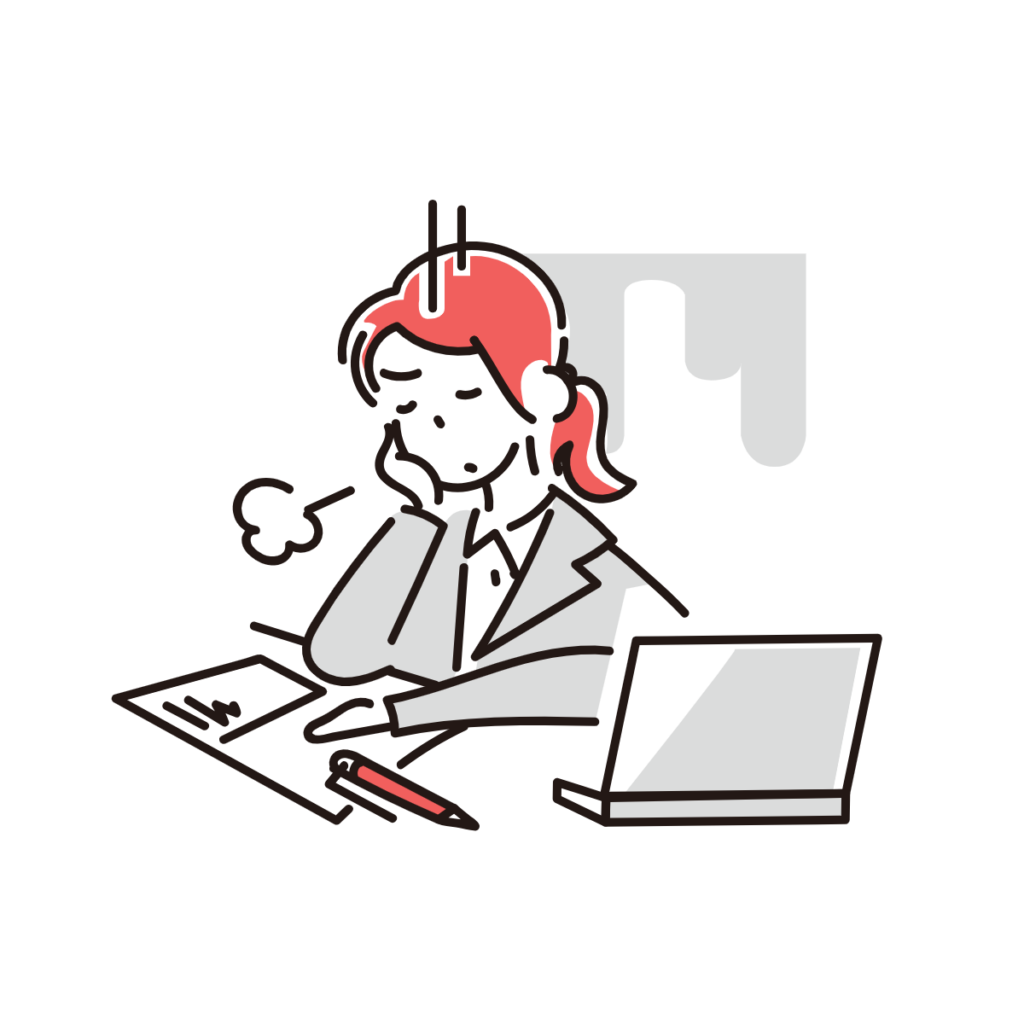
わたし自身、オンライン事務代行として独立した当初は「仕事につながれば」と思い異業種交流会に参加しました。
そして、実際にお仕事をご紹介いただいて、受注につながったこともあります。
しかし、内容は本当に欲しい仕事内容ではなく、条件を譲歩しなければならないことも多く、義理や縁で断りづらい案件が含まれていました。
名刺交換や紹介を通じて案件が発生することはあっても、安定的な顧客獲得につながることはほとんどありませんでした。
結論としては、売上目的で異業種交流会に通うのは遠回りであり、むしろ既存の人脈や業界特化の学びに力を注ぐ方が早いと感じました。
実体験からの学び②|成長目的で参加するなら意味はあるが「場選び」が大切
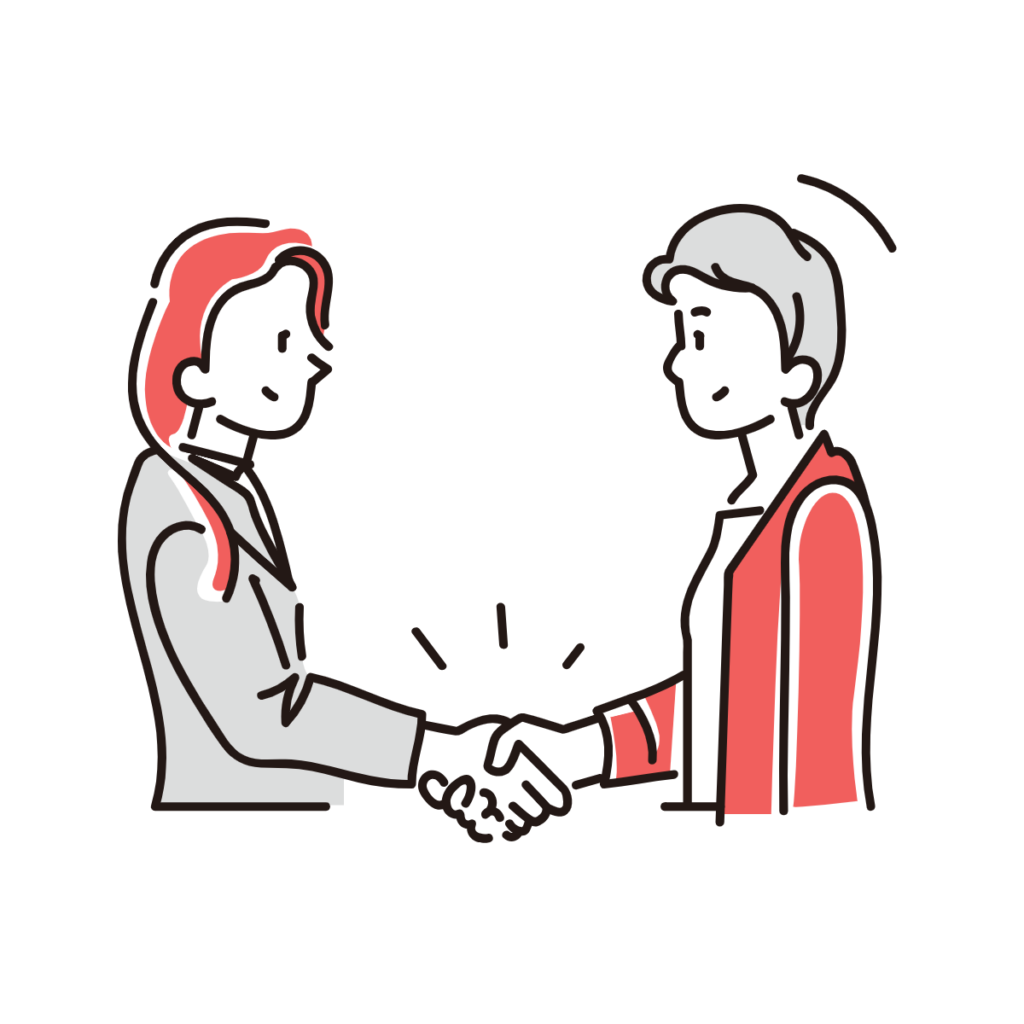
一方で、異業種交流会に「学びや成長」を求める参加者もいます。
わたし自身も経営者向けの勉強会型の異業種交流会に参加したことがありました。
そこでは刺激を受ける場面もありましたが、実際には2代目・3代目経営者や大規模事業の方が多く、立場やフェーズが違いすぎて参考になりにくいと感じました。
また、参加しているうちに交流会そのものに所属することが目的化し、役職や運営にこだわる人も少なくありませんでした。
本業よりも交流会活動に時間や労力を割いてしまい、成長どころか負担になっているように見受けられるケースもありました。
この経験から学んだのは、売上以外の目的で参加する場合でも「どんな場を選ぶか」が極めて重要だということです。
自分の立場や成長フェーズに近い人が集まる会であれば学びや刺激を得られますが、そうでなければただの時間消費になってしまいます。
💡 異業種交流会も、参加するタイミングや場選びを間違えなければ、有効だと思います。人間関係が自己成長に効果的な理由はこちらの記事で解説していますので、良かったら参考にしてみてください。

異業種交流会は独立初期にはお勧めはしない(まとめ)
異業種交流会にはそれなりにメリットもありますが、独立初期のフリーランスにとっては「意味ない」と感じやすいポイントも数多く存在します。
異業種交流会のデメリット
- 名刺交換や売り込み合戦で終わる
- 発注力のない参加者ばかり
- 紹介案件の質が微妙になりやすい
- 役職や役割に時間を奪われる
- 異業種交流会自体が自己目的化する
こうした実態を知らずに参加すると、貴重な時間とお金を浪費してしまいます。
大切なのは、自分なりの目的を持って参加すること、目的に叶った場を慎重に選ぶことです。
目的を明確にせず闇雲に異業種交流会に通うのではなく、まずは既存のつながりや業界特化の学び、そして自分の発信を強化する方が、仕事につながる可能性は高いと思います。
「人脈づくり=仕事が取れる」という幻想に振り回されず、売上や事業成長に直結する行動を優先していきましょう。
💡 オンライン事務代行のフリーランスとして、案件を獲得するためのコツはこちらの記事で紹介しています。営業活動を強化したいと感じている方は、こちらの記事が参考になると思います。


-1024x1024.png)
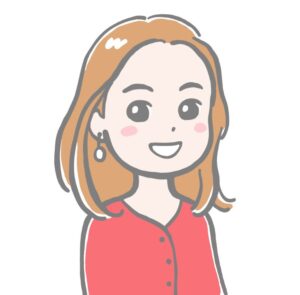
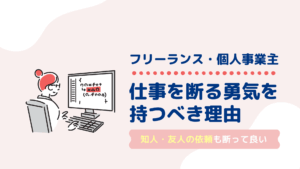


でどう違う?種類と節税対策-300x169.png)