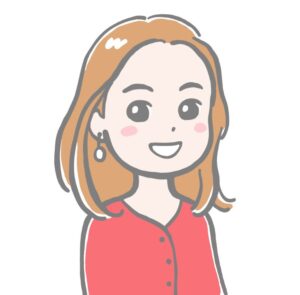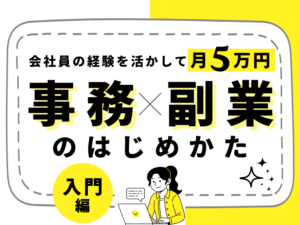人生を変えたい
もっと稼げるようになりたい
理想の働き方を手に入れたい
そんなとき、あなたはまず何を変えるべきだと思いますか?
スキルアップでしょうか?
それとも時間管理の仕方ですか?
実は、もっとも効果的に変化する方法として「付き合う人を変えること」が挙げられます。
この考え方のベースにあるのが、ジムローンの「5人の法則」です。
この記事では、自己啓発の先駆者ジムローンが提唱したこの法則を深掘りしつつ、人間関係を見直すことが、なぜ稼ぐ力にもつながるのかをわかりやすく解説します。
この記事を読んで、今のあなたより稼いでいる人や既に理想の未来を叶えている人と「積極的に関わりたい…」と思ってもらえたら幸いです。
ジムローンの「5人の法則」とは?人生を変えるシンプルな教え
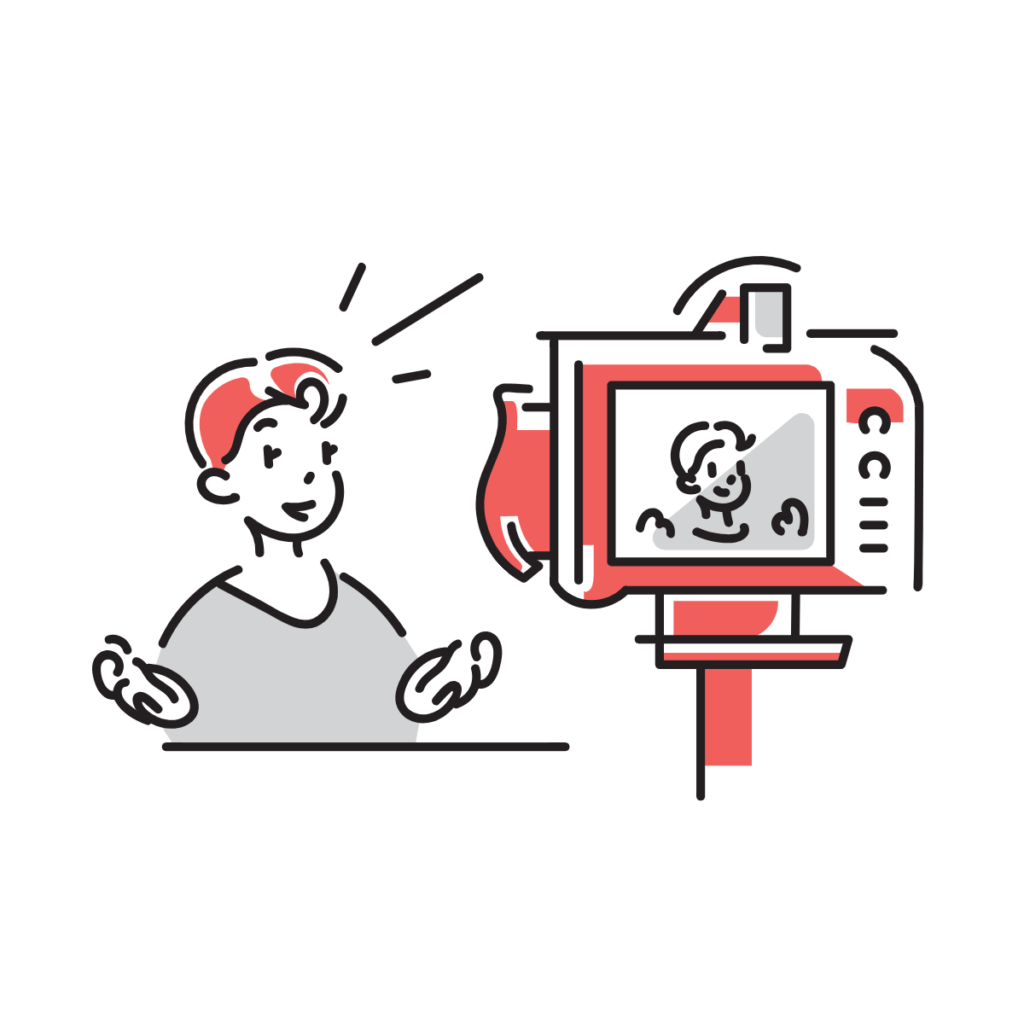
ジムローン(JimRohn)は、アメリカの自己啓発界で広く知られるスピーカーです。
成功哲学を語った多くの講演・著書を通じて、世界中のビジネスパーソンや起業家に影響を与えてきました。
その彼が遺した有名な言葉がこちらです。
“You are the average of the five people you spend the most time with.”
「あなたは、最も多くの時間を過ごす5人の平均である」
この「5人の法則」は、「人は自分の周りの人間関係から大きな影響を受ける」というシンプルな真理を表しています。
付き合う人が変われば、考え方・習慣・言葉遣い・目標設定も変わり、自然と行動や結果まで変わっていくのです。
人間関係は稼ぐ力にも直結する「5人の法則」の裏付け
なぜ「付き合う人」がそこまで重要なのでしょうか?
そこには、心理学や脳科学でも説明できるいくつかのメカニズムがあります。
「5人の法則」の裏付け
- ミラーニューロンの働き
- 感情の伝染
- 学習性無力感(金魚の実験)
「5人の法則」の裏付け①|ミラーニューロンの働き
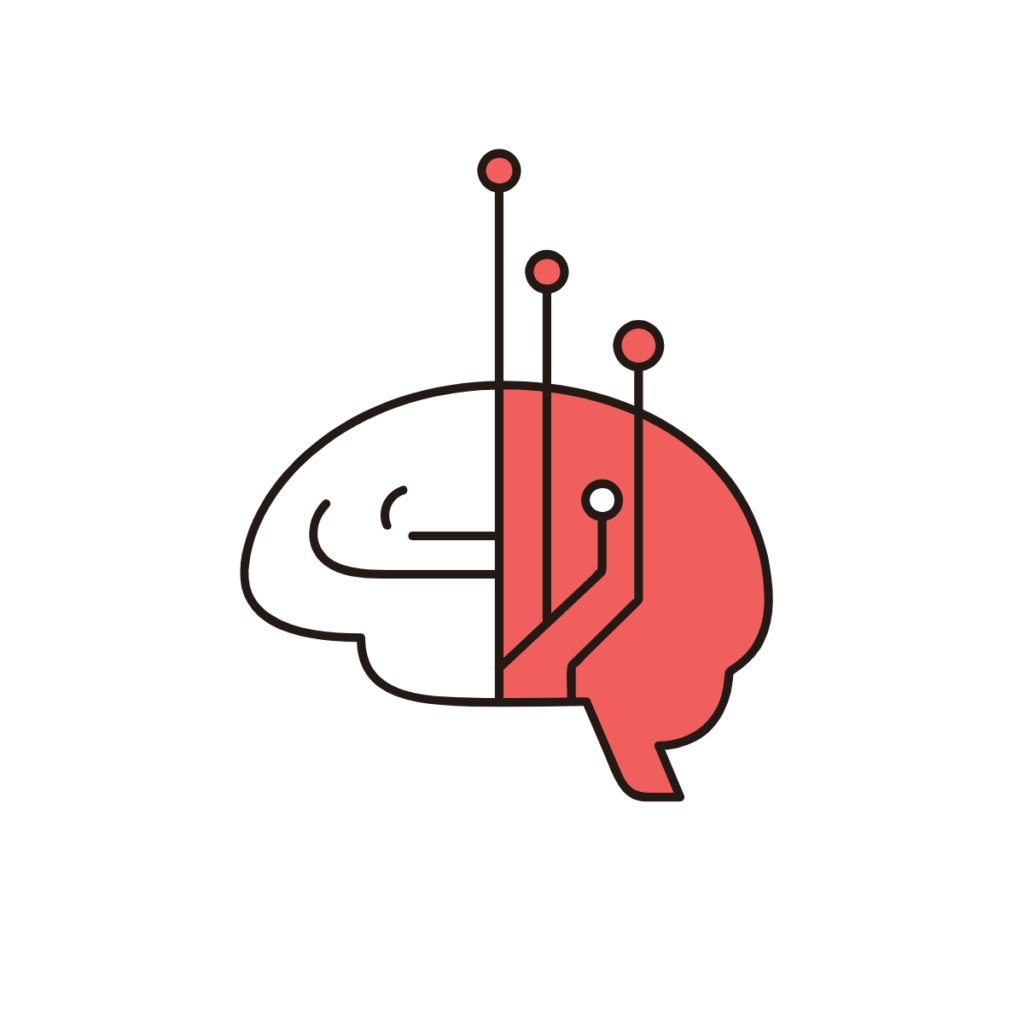
ミラーニューロンとは、1990年代にイタリアの脳科学者たちによって発見された神経細胞です。
特徴的なのは、「他人の行動を見るだけで、自分の脳の中でも同じような神経活動が起こる」という点です。
- 誰かが笑っているのを見ると、つられて笑ってしまう
- 緊張している人と一緒にいると、自分まで落ち着かなくなる
- やる気に満ちた人のそばにいると、自分もモチベーションが上がる
こうした現象の背景には、ミラーニューロンの働きがあると考えられています。
つまり、人間の脳は「周りの人の感情や行動を、無意識のうちに模倣する」性質を持っているのです。
この仕組みは、学習や共感、社会性の発達に重要だとされており、誰と一緒に過ごすかが、自分の行動パターンや思考回路に直接影響を与えることの科学的な裏付けにもなっています。
「付き合う人を変えれば、自分も変わる」というジムローンの5人の法則は、感覚的なものではなく、脳の仕組みによっても説明がつくのです。
「5人の法則」の裏付け②|感情の伝染
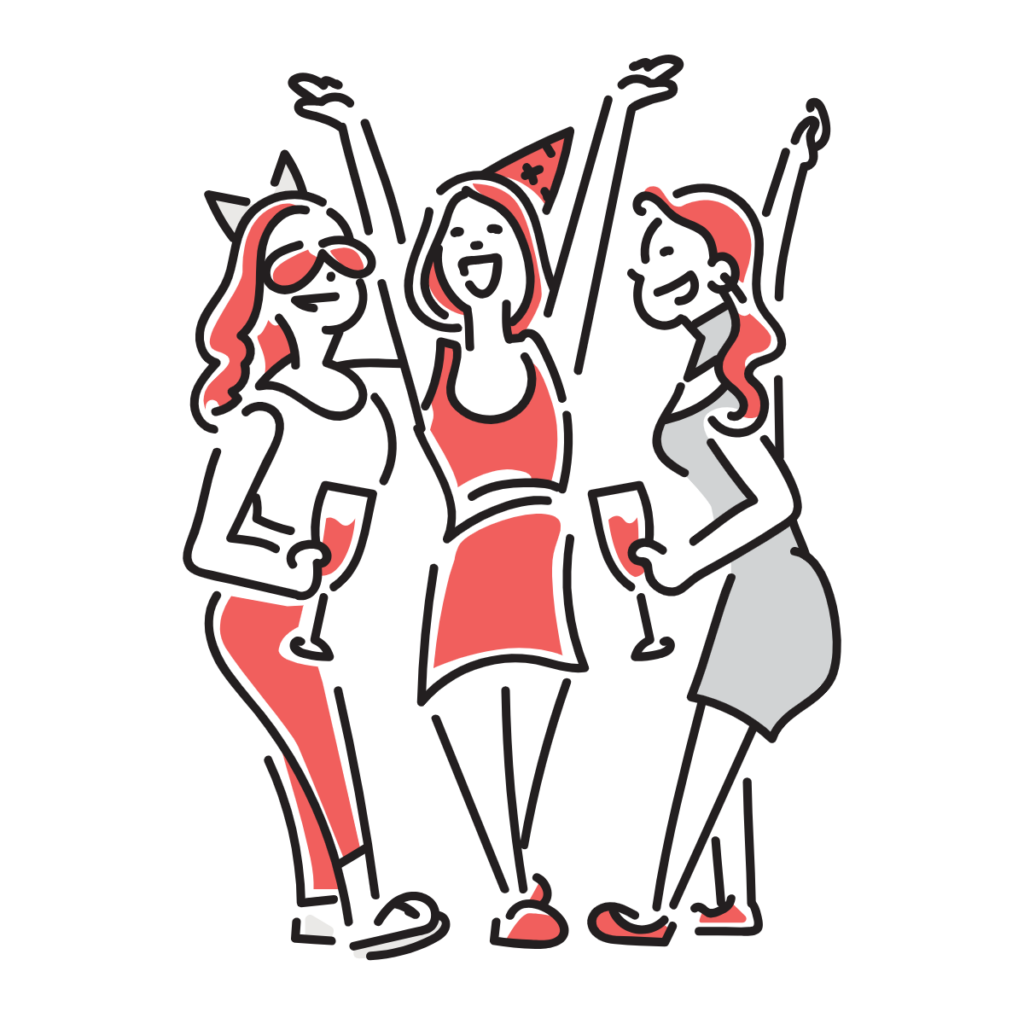
人の感情は、思っている以上に周囲に影響を与えます。
これは「感情の伝染(emotional contagion)」と呼ばれ、心理学でも認められた現象です。
たとえば、前向きな人と一緒にいると自分も元気になれたり、反対に、愚痴ばかりの人と過ごすと気分が沈んだりしますよね。
これは気のせいではなく、人間は無意識のうちに他人の感情を模倣しやすい性質があるためです。
ハーバード大学の研究でも、幸福は「友人の友人の友人」にまで伝染すると示されており、誰と接するかが自分の幸福感や思考にも直結していることがわかります。
つまり、ジムローンの「5人の法則」は、脳の仕組みや感情の連鎖という科学的背景を伴った現実的な法則なのです。
「5人の法則」の裏付け③|学習性無力感(金魚の実験)
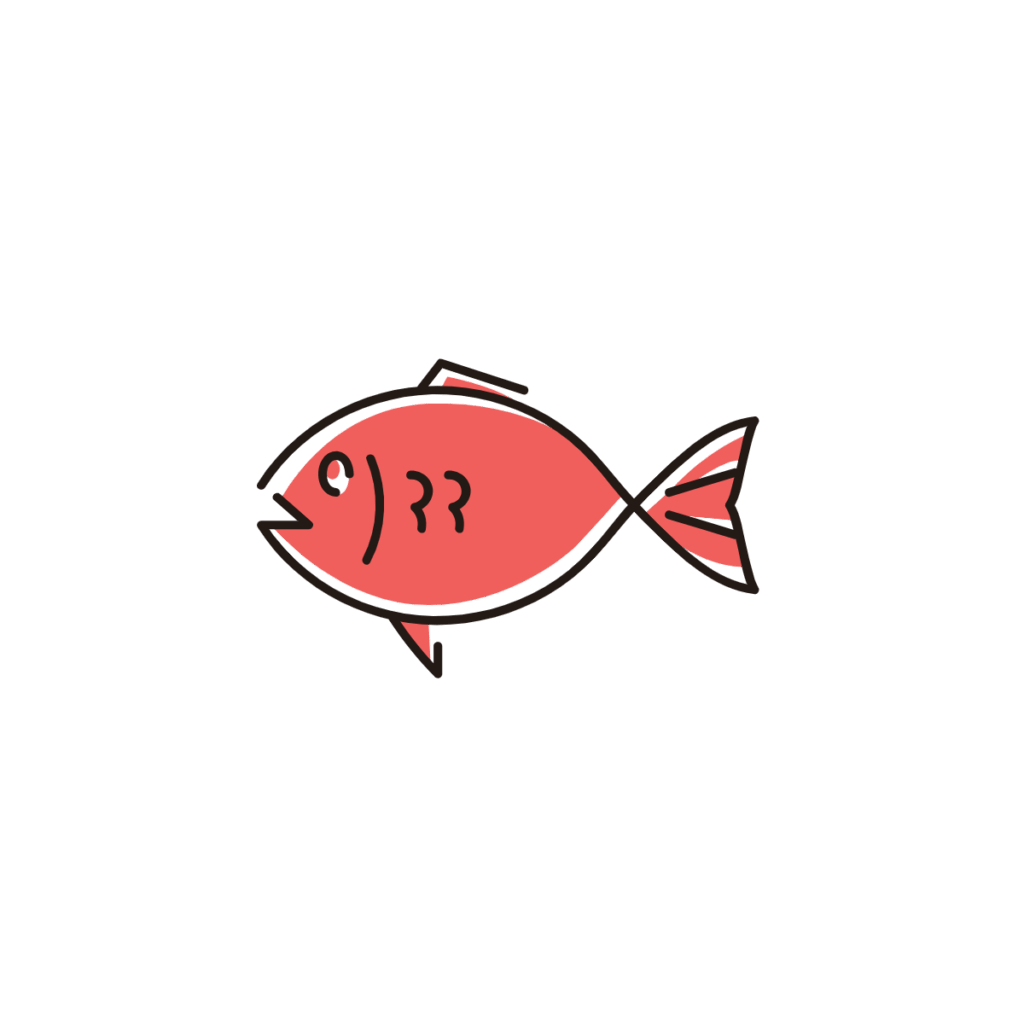
環境の影響の強さを示す有名な例に、「金魚の実験」があります。
金魚を2つの水槽に分けて中央に透明な仕切りを入れると、何度もぶつかっていくうちに「向こうには行けない」と学習します。
その後、仕切りを取り外しても、金魚はもう反対側へ行こうとしなくなってしまうのです。
これは「学習性無力感」と呼ばれ、現実の人間関係にも通じます。
挑戦しない人ばかりの中にいると、「どうせ無理」「自分にはできない」と無意識のうちに思い込まされ、行動を起こせなくなってしまうのです。
まずは「今の5人」を棚卸ししてみよう

ここで、ちょっと手を止めて考えてみてください。
あなたが普段もっとも多く時間を過ごしている5人は誰ですか?
(具体例)
- 職場の同僚
- パートナー
- 親
- 友人
- SNSのフォロー相手
あなたが良く関わる5人、意外と無意識に選んでいないでしょうか。
その5人は、あなたを前向きにさせてくれる存在ですか?
それとも、現状維持や否定的な言葉を投げかけてくる相手ですか?
「今の自分を変えたい」と思うなら、まずは「今の5人」を客観的に棚卸ししてみましょう。
「理想の5人」を選ぶときのヒント
それでは、どんな人を“5人”に選ぶと良いのでしょうか?
これから先の望む未来を手に入れるために、あなたにとっての「理想の5人」を考えてみましょう。
「理想の5人」を選ぶときのヒント
- 理想の5人を選ぶための5つの視点
- オンライン時代の「デジタル5人」も見直そう
ヒント①|理想の5人を選ぶための5つの視点
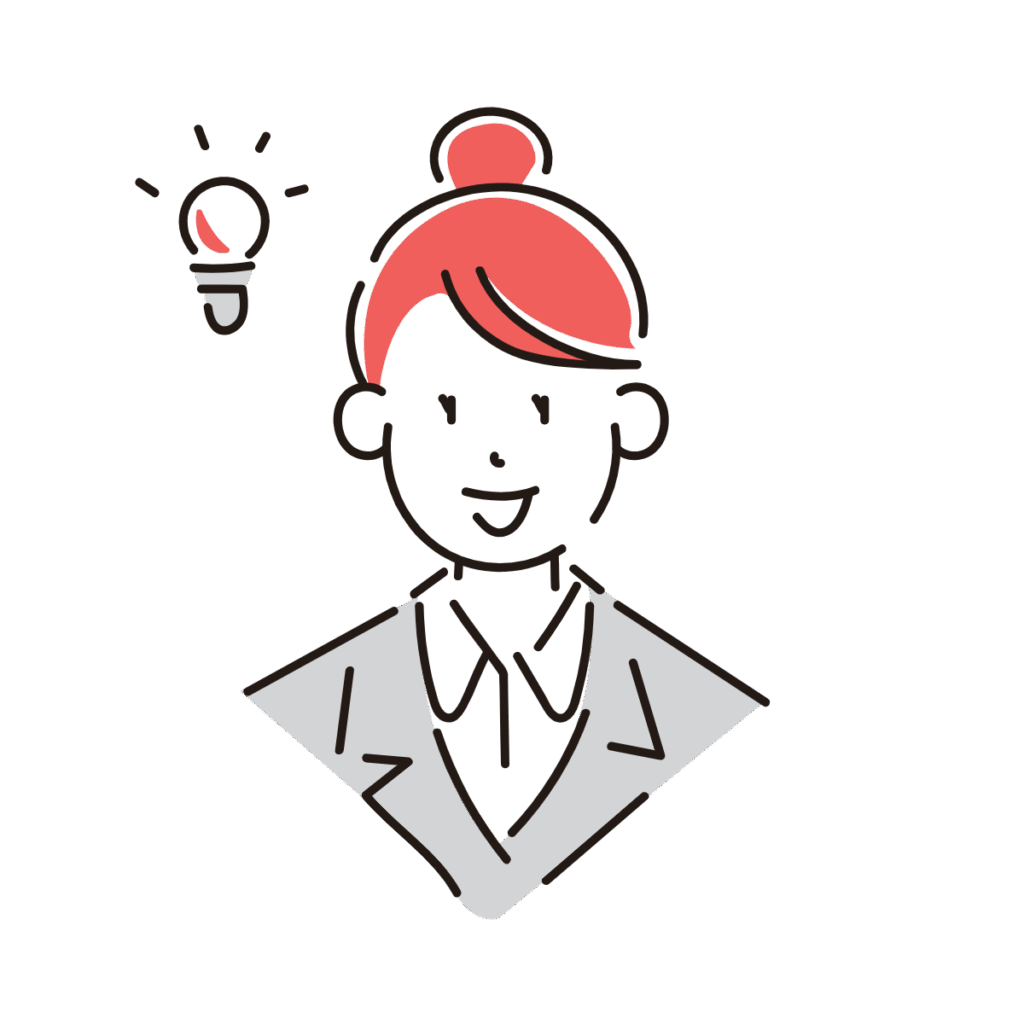
ここでは、理想の5人を選ぶためのヒントを紹介します。
理想の5人を選ぶ「5つの視点」
- 自分より少し先を歩いている人
- 否定よりも行動を大事にする人
- お金の使い方・時間の使い方が丁寧な人
- 一緒にいると前向きな気持ちになれる人
- 発信者として尊敬できる人(オンラインでもOK)
理想の5人を選ぶ視点①|自分より少し先を歩いている人
完全な成功者でなくてもOKです。
あなたが掲げている目標や理想に対して、あなたより少し先を進んでいる人は、よい影響を与えてくれます。
理想の5人を選ぶ視点②|否定よりも行動を大事にする人
言い訳より、まずやってみる姿勢を持つ人が好ましいです。
理想の5人を選ぶ視点③|お金の使い方・時間の使い方が丁寧な人
価値観は伝染します。
大切なお金と時間を「どこに投資しているか」に注目しましょう。
理想の5人を選ぶ視点④|一緒にいると前向きな気持ちになれる人
ただ心地よいだけの関係ではなく、あなた自身を鼓舞してくれる存在も大切です。
理想の5人を選ぶ視点⑤|発信者として尊敬できる人(オンラインでもOK)
本・音声・動画などで「この人の考え方をもっと知りたい」と思える人を選びましょう。
ヒント②|オンライン時代の「デジタル5人」も見直そう
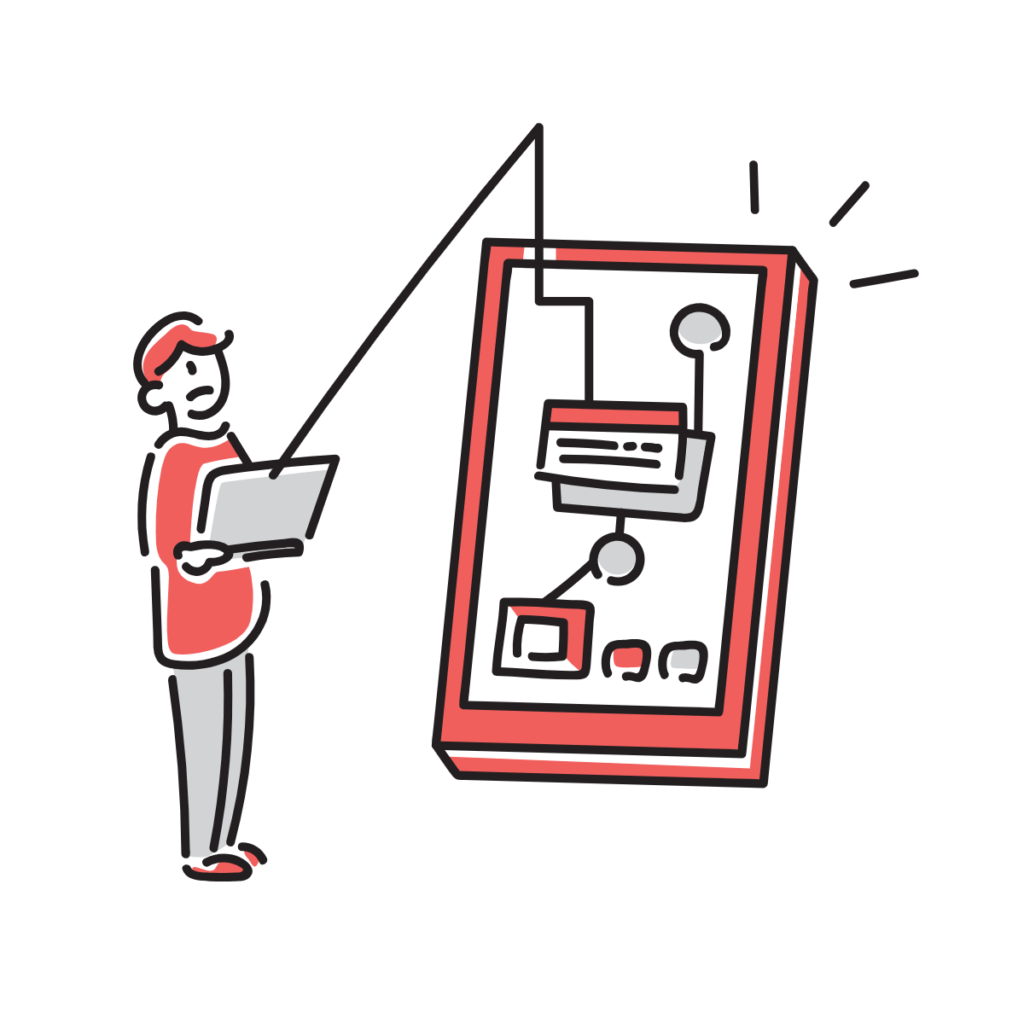
5人の法則は、リアルな人間関係だけに限りません。
今やSNSやYouTube、Voicy、Podcastなど、
日常的に触れている情報源=“デジタル5人”
も強力な影響を与えています。
具体的には…
- X(旧Twitter)で誰をフォローしているか
- YouTubeでどんなチャンネルを見ているか
- 毎朝聴いている音声配信のパーソナリティは誰か
- よく読む本の著者はどんな人か
これらも、あなたの考え方や行動を形づくる「擬似的な人間関係」です。
付き合う人をいきなり変えるのが難しいなら、まずはデジタル上の「5人」を見直すことから始めてみましょう。
理想のライフスタイルや収入を実現している人の発信に触れることで、自分の価値観や判断軸が自然と変わっていきます。
わたしが副業時代にやっていたこと(体験談)
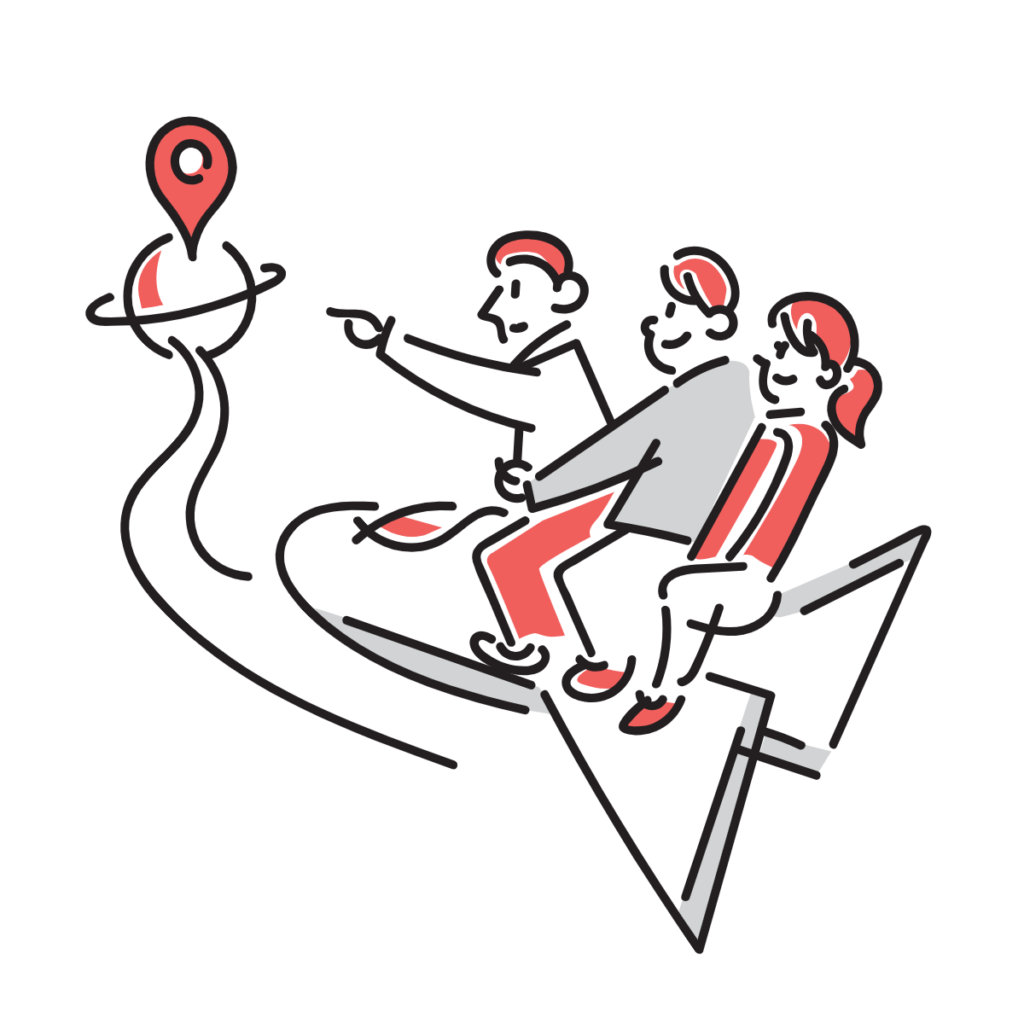
わたしは、2021年に会社員をしながら、オンライン事務代行の副業を始めました。
その当時は、「5人の法則」という言葉すら知らないものの、自分が目指す働き方をしている人や少し先を行く人と積極的に関わるようにしていました。
オンライン事務代行の副業をしながら、ゆくゆくはフリーランスとして活動したいと思っていたので、そういった働き方を既に叶えている人と積極的に関わろうと考えていました。
副業時代にやっていたこと(例)
- フリーランスとして活躍している方のストアカ講座を受講する
- フリーランスの人が主催しているオンラインサロンに参加する
- クライアントワークを通じて個人事業主や経営者の方との接点を増やす
- 地元の目黒3ma会(異業種交流会)に参加する
- クライアントが加入している異業種交流会にビジター参加させてもらう
副業時代も含めて、ここ3~4年はいつも周囲の「人間関係」を変えることで、自分自身を成長させてきました。
わたしは、20代の頃は、スキルアップすれば自分の市場価値が高められて、結果的に(自動的に)収入が上がるものと大きな勘違いしていました。
ですが、副業を始めてからというもの、スキルアップはもちろん必要ですが、「人間関係を変えることで、自分自身を成長させられる」という実感を持ち、考え方を大きく改めています。
 りか
りか今は法人設立しているので、フリーランスではなく、経営者の人たちと積極的に関わるようにしています
付き合う人を変えれば、稼ぐ力も人生も変わる(まとめ)


人生を変えたい
もっと稼げるようになりたい
理想の働き方を手に入れたい
そう思ったときに、自己投資やスキルアップももちろん大切ですが、まずは「付き合う人」を変えることが最短ルートになるかもしれません。
なぜなら、人は環境に適応して生きているからです。
「現実の5人」を「デジタル5人」まで含めて、あなたの周囲を見直してみましょう。
そして、稼ぎたいと思っているなら、既に自分よりも稼いでいる人と一緒に過ごしたり、関わることができる場を多く持つようにしましょう。
未来の自分を変えるヒントは、これからの「人間関係」にあります。



場合によっては、一時的に友達が減ってしまったり、今まで親しくしていた家族や親戚とも、少し距離を置く必要があるかもしれません。

-1024x1024.png)