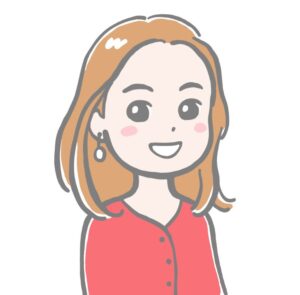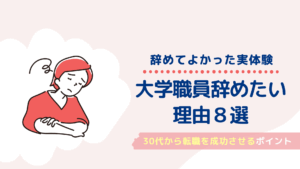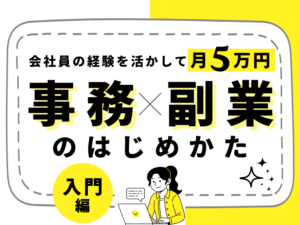このまま総務を続けていていいのだろうか?
そんな不安を抱えたことはありませんか?
AIやRPAなどの自動化技術が急速に進化するなかで、「総務の仕事はそのうちなくなる」といった声も聞かれるようになりました。
一方で、現場では日々、多岐にわたる業務に追われ、「誰でもできる仕事」とは到底思えないという実感もあるはずです。
本記事では、総務の仕事がなぜ「なくなる」と言われているのか、まずはその背景を整理します。
そのうえで、AI時代においても価値を発揮し続けるための視点や行動のヒントをお伝えしていきます。
将来への不安を「可能性」に変えるためのヒントを、一緒に探していきましょう。
総務の仕事は本当になくなるのか?将来が不安になる4つの背景
まずは、総務の仕事がなぜ「なくなる」と言われているのか、将来が不安になる背景を具体的に見ていきましょう。
代表的なものを4つご紹介します。
将来が不安になる背景4つ
- 定型業務の自動化の進展
- 間接部門は「コストセンター」という風潮
- 総務=雑用・誰でもできる仕事という誤解
- 努力や工夫が評価されづらい
総務の将来性が不安になる背景①|定型業務の自動化の進展
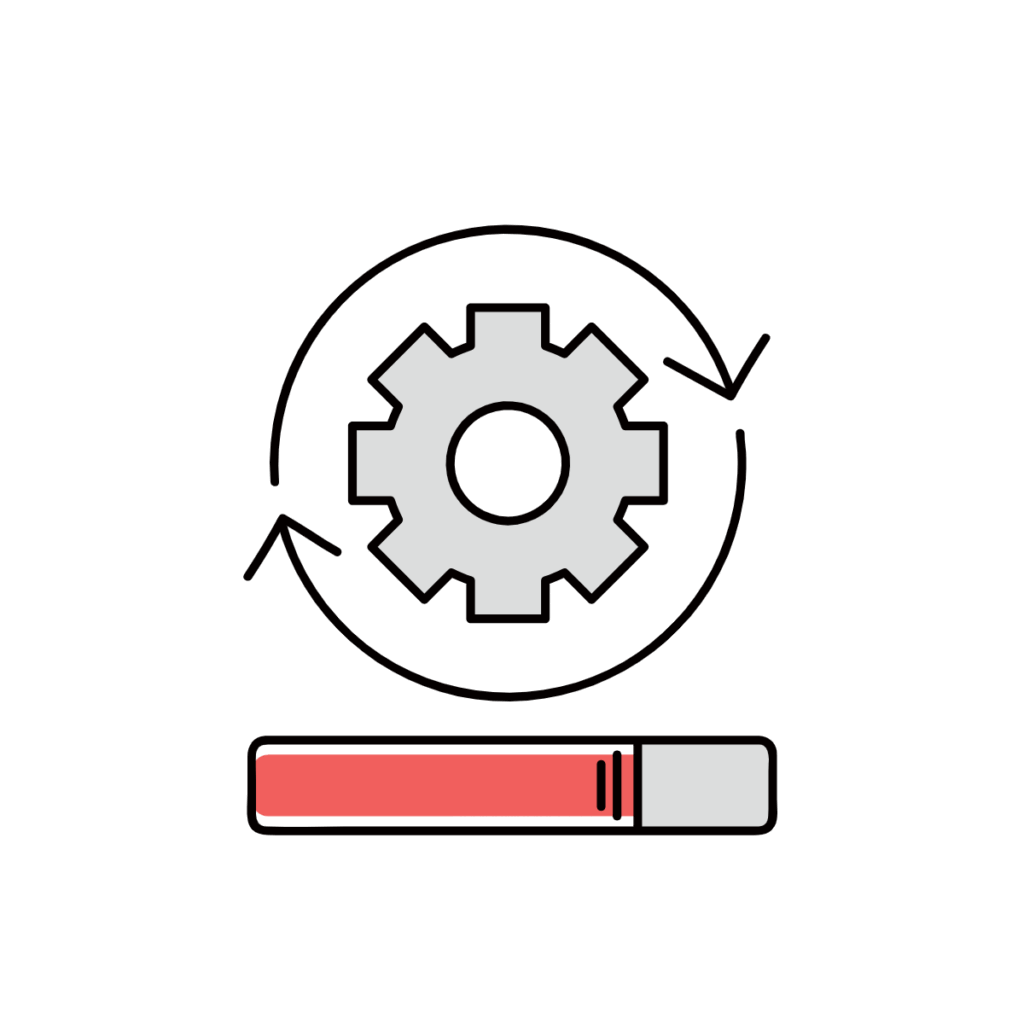
ここ数年で、総務が担ってきたルーチン業務は大きく変化しつつあります。
たとえば、RPA(業務自動化ツール)を導入すれば、勤怠情報の集計や備品の発注、データ入力といった定型業務はボタンひとつで完了する時代です。
また、クラウドサービスの活用により、紙やハンコに依存した業務フローも見直され、リモート環境で完結できる業務が増えてきました。
さらに、ChatGPTのような生成AIを使えば、社内文書のたたき台作成や案内文のドラフト作成なども高速化できます。
こうしたテクノロジーの進化は、確かに一部の総務業務を「人の手から手放す」方向に導いているのです。
総務の将来性が不安になる背景②|間接部門は「コストセンター」という風潮

多くの企業では、営業や商品開発などの“売上をつくる部門”が重視される一方で、総務や経理などの“間接部門”は「コストセンター(利益を生まない部門)」として見なされがちです。
その結果、「削れるところは削りたい」「なるべく省力化したい」という経営判断が入りやすく、バックオフィスのリストラや業務委託が進む背景にもなっています。
総務に限らず、間接部門全体に対するこの風潮は、将来性への不安を加速させる要因のひとつです。
総務の将来性が不安になる背景③|総務=雑用・誰でもできる仕事という誤解
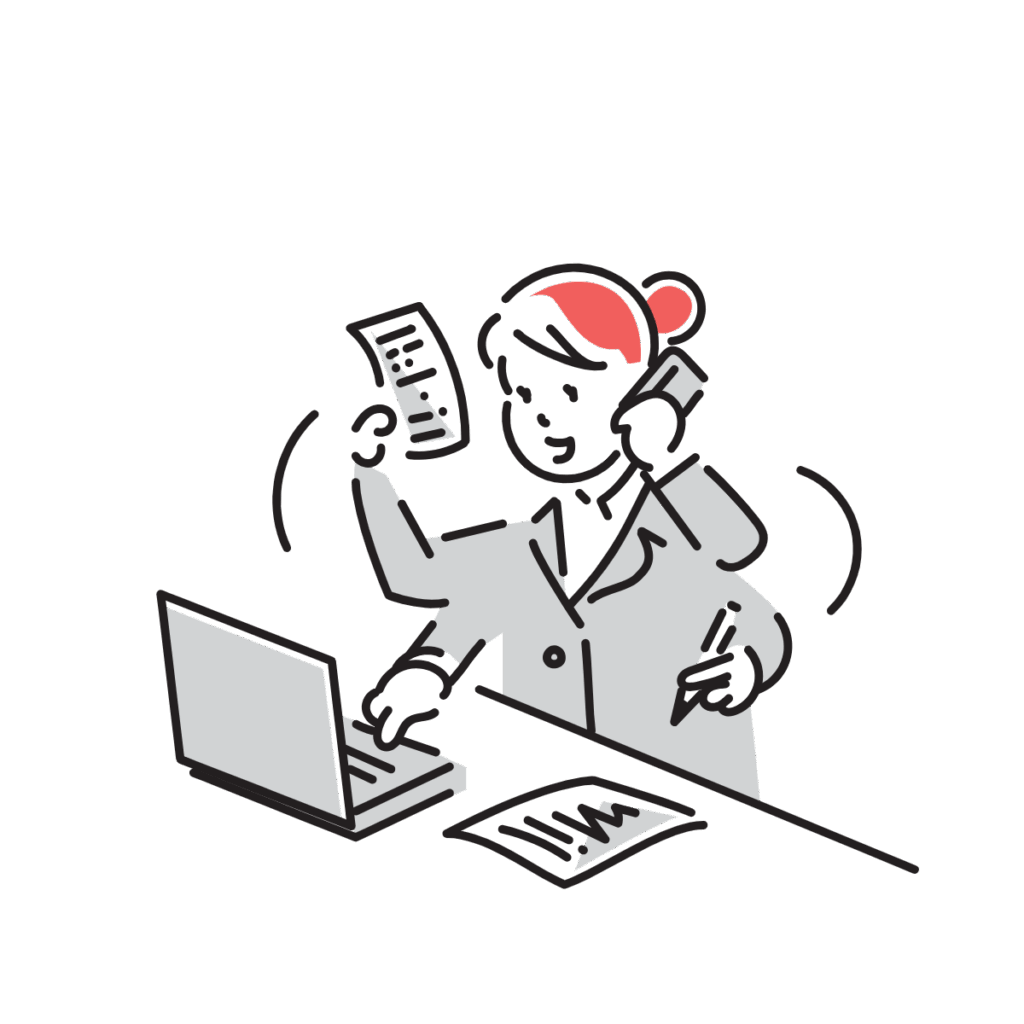
「雑用係」「何でも屋」という印象を持たれやすいのも、総務の悩みどころです。
事実、社内から依頼される仕事は幅広く、郵便物の仕分けから備品の手配、会議室の準備や急なトラブル対応まで、臨機応変に対応する柔軟性が求められます。
しかし、それが裏目に出て「専門性がない」「誰でもできる」と見なされてしまうことも少なくありません。
こうした誤解が、AIや外注に置き換えられても仕方ないというネガティブな認識につながっているのです。
総務の将来性が不安になる背景④|努力や工夫が評価されづらい

総務の仕事は“うまくいっていて当たり前”と思われがちです。
例えば…
- 備品の在庫が常に補充されている
- 会議室がきちんと予約されている
- トラブルが起きてもすぐに対応されている
――こうした状況を支えているのは、総務の日々の積み重ねによるものです。
ところが、それが“成果”として可視化されにくいため、社内からは「何をしているのかわからない」と言われてしまうこともあります。
努力が見えにくく、評価されづらい構造が、不安や無力感につながってしまうのです。
AI時代でも総務の仕事が「完全にはなくならない」理由
総務のすべての仕事がなくなるわけではありませんが、真っ先に影響を受けるのは“定型的でルール化しやすい業務”です。
一定のパターンやルールに基づいて処理できるため、「人が判断しなくてもいい仕事」と見なされやすいのが特徴です。
だからこそ、総務職が今後も価値を発揮し続けるには、こうした仕事に固執するのではなく、「人にしかできない仕事」に重心を移していくことが重要です。
総務の仕事は「人にしかできない」理由4つ
- 臨機応変な判断・調整・対応が多い
- 物理的にオフィスで行われる業務が残る
- 社内のつなぎ役・調整役のポジション
- 「縁の下の力持ち」としての価値
総務の仕事は人にしかできない理由①|臨機応変な判断・調整・対応が多い
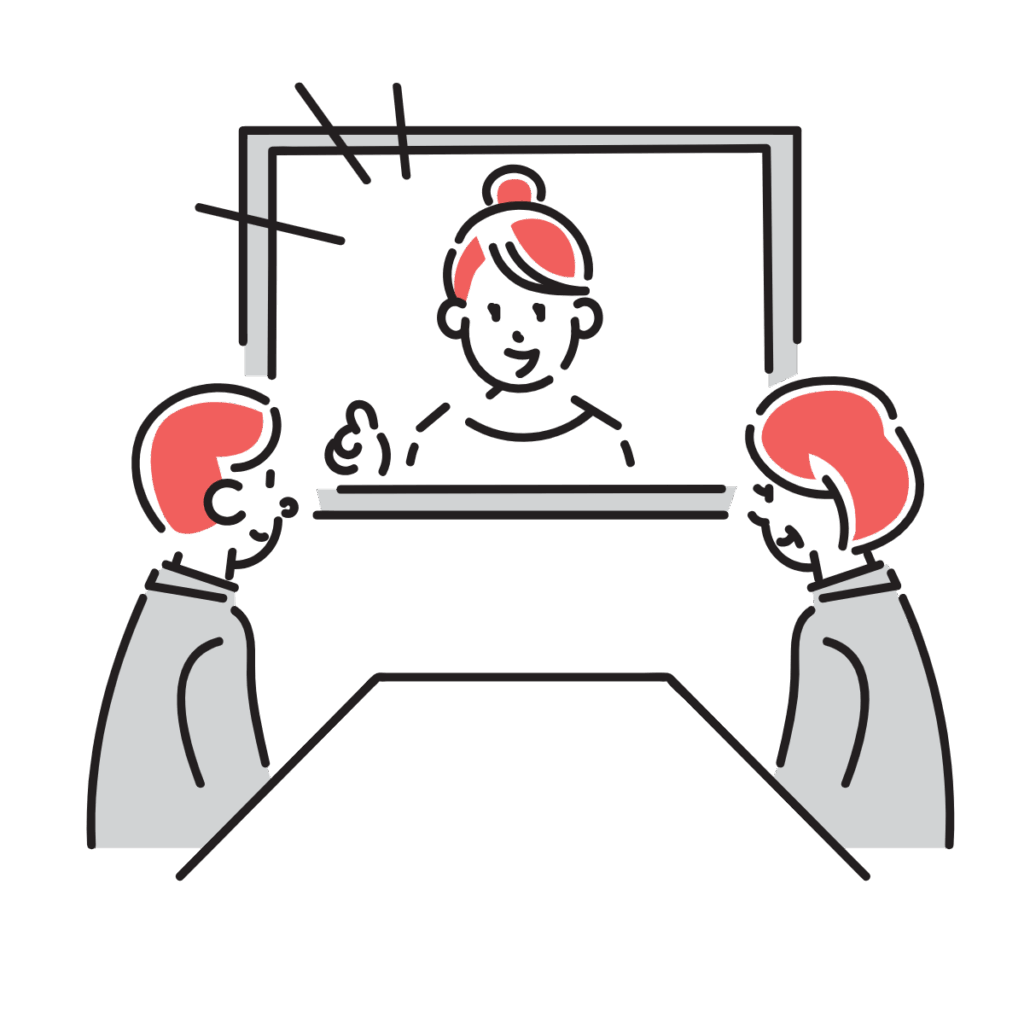
たとえば、社内イベントのトラブル対応や急なレイアウト変更、備品の不具合対応など、「状況を見て判断する」仕事はAIには難しい領域です。
総務には、予定外の出来事にすばやく対応する柔軟性や、判断力、社内の人間関係を踏まえた配慮が求められます。
これらは、スキルというよりも“現場感覚”に近いものです。
総務の仕事は人にしかできない理由②|物理的にオフィスで行われる業務が残る
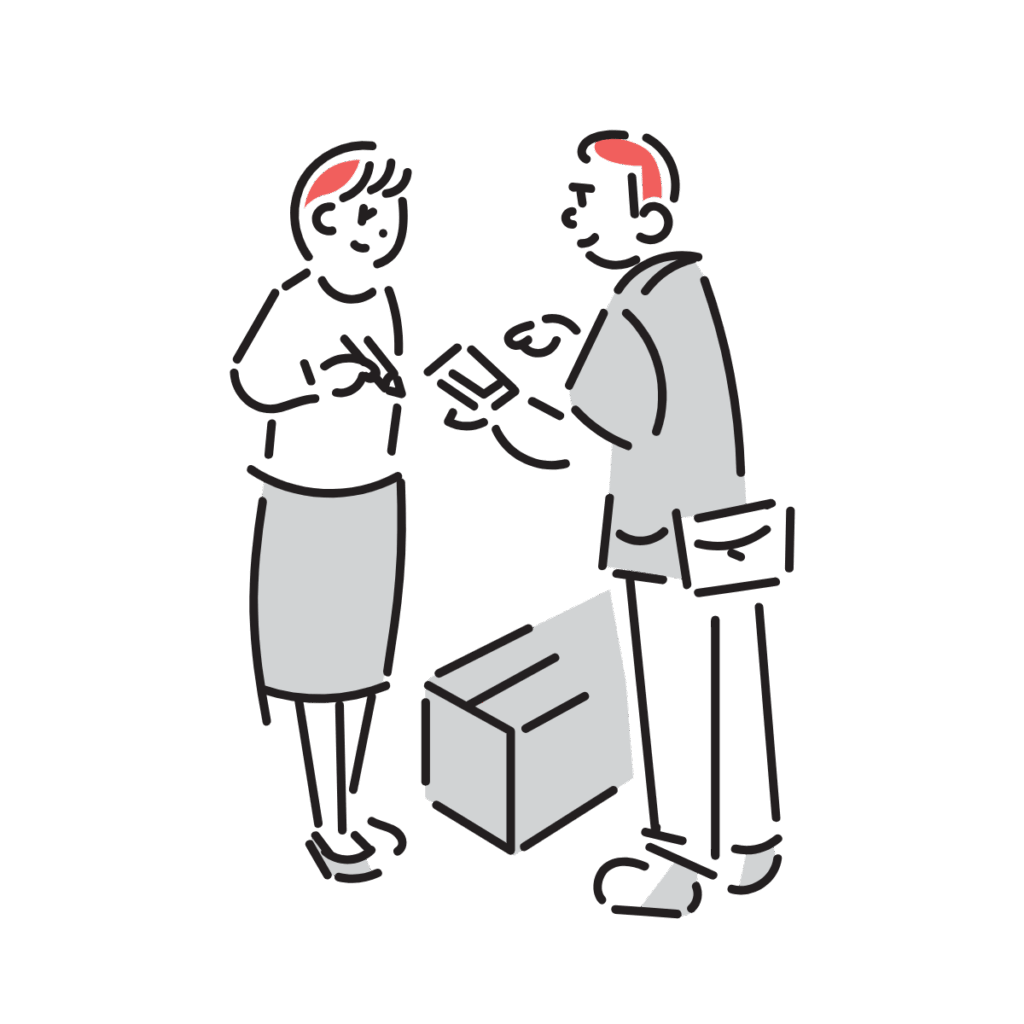
物理的な場で行われる業務は、引き続き人の手が必要です。
郵便物の仕分けや宅配便の受け取り、来客対応、備品の管理や会議室の整備などは、誰かがその場で判断し、手を動かさなければなりません。
特にオフィスに人が戻ってくる流れが一部で再開している今、現場で“気が利く存在”としての総務は、今後も一定の価値を持ち続けるでしょう。
総務の仕事は人にしかできない理由③|社内のつなぎ役・調整役のポジション

AIやシステムがどれだけ進化しても、最終的に人と人をつなぐのは“人”です。
- 部署間の意見調整
- 経営層と現場を橋渡しする役割
- 社内規程の見直しに関わる気配り
など、目立たないけれど組織運営に不可欠な仕事は数多く存在します。
「誰がやるか明確でない仕事を、自然に引き受ける存在」
として、総務の柔軟な立ち回りは代替困難です。
総務の仕事は人にしかできない理由④|「縁の下の力持ち」としての価値
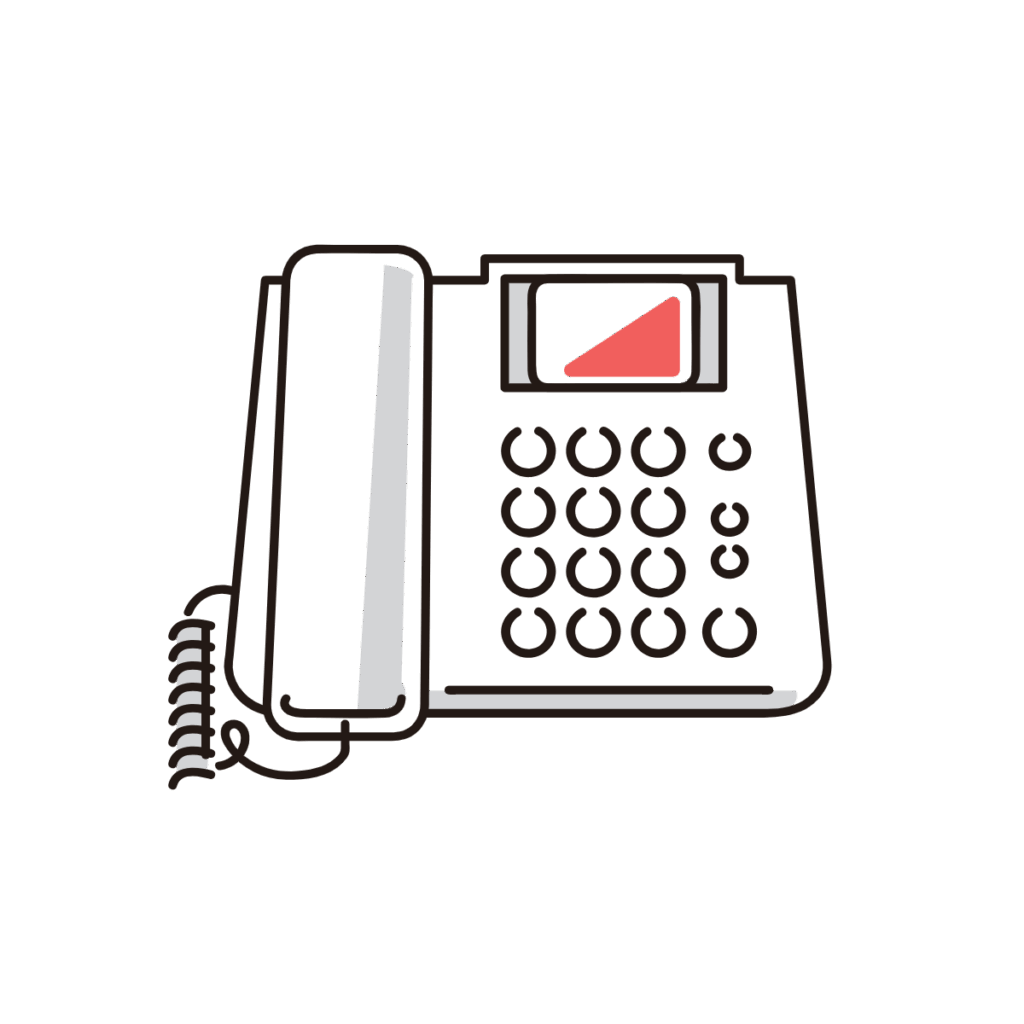
“トラブルがないこと”こそが成果、というのが総務の本質です。
- 電話がつながる
- コピー機が使える
- 備品がある
- 誰かが困っていたら助ける
こうした日々の積み重ねがあるからこそ、社員が安心して業務に集中できます。
その貢献は定量的に示しにくいですが、職場の安定感を支える「縁の下の力持ち」としての価値は、今後も必要とされ続けます。
AI時代に総務が生き残るためのキャリア戦略6つ
総務職が今後も市場価値を発揮し続けるためには、「人にしかできない仕事」に重心を移していくことが必要なことをお伝えしました。
中長期的なキャリアを考える上で、どのような戦略が取れるのか、具体的な事例を6つご紹介します。
総務のキャリア戦略6つ
- 存在価値を言語化する
- 他職種との「ハイブリッド人材」を目指す
- 業務改善の提案・DX推進の立役者になる
- マネジメント職を目指す
- 総務としての専門性を深める
- 隣接職種へのキャリアチェンジ
総務が生き残るためのキャリア戦略①|存在価値を言語化する

総務の価値は、「目に見えないけれど、なくなったら困る仕事」に詰まっています。
だからこそ、自分の役割を言語化する力が問われます。
たとえば、「わたしは雑用係です」ではなく、「社員が安心して働ける環境をつくる仕事です」と言い換えてみましょう。
さらに、「〇〇部門との調整役として、業務の橋渡しをしています」と、具体的なエピソードを添えることで、自分の存在価値を明確に伝えられるようになります。
総務が生き残るためのキャリア戦略②|他職種との「ハイブリッド人材」を目指す

総務の仕事は「単体」では評価されづらい一方で、他のスキルと組み合わせることで強い武器になります。
例えば、以下のような視点で、ハイブリッド人材を目指すことができます。
- 総務 × ITスキル → DX推進の担い手に
- 総務 × 広報 → 社内報やSNS運用に強い人材へ
- 総務 × 経理 → 管理部門を横断的に支える存在に
これらは一朝一夕で身につくものではありませんが、無料のオンライン講座(YouTubeやUdemyなど)や社内の異動希望など、小さな一歩から始められます。
「〇〇には詳しくないから無理」ではなく、「少し興味があること」から掛け算を始めてみましょう。
総務が生き残るためのキャリア戦略③|業務改善の提案・DX推進の立役者になる
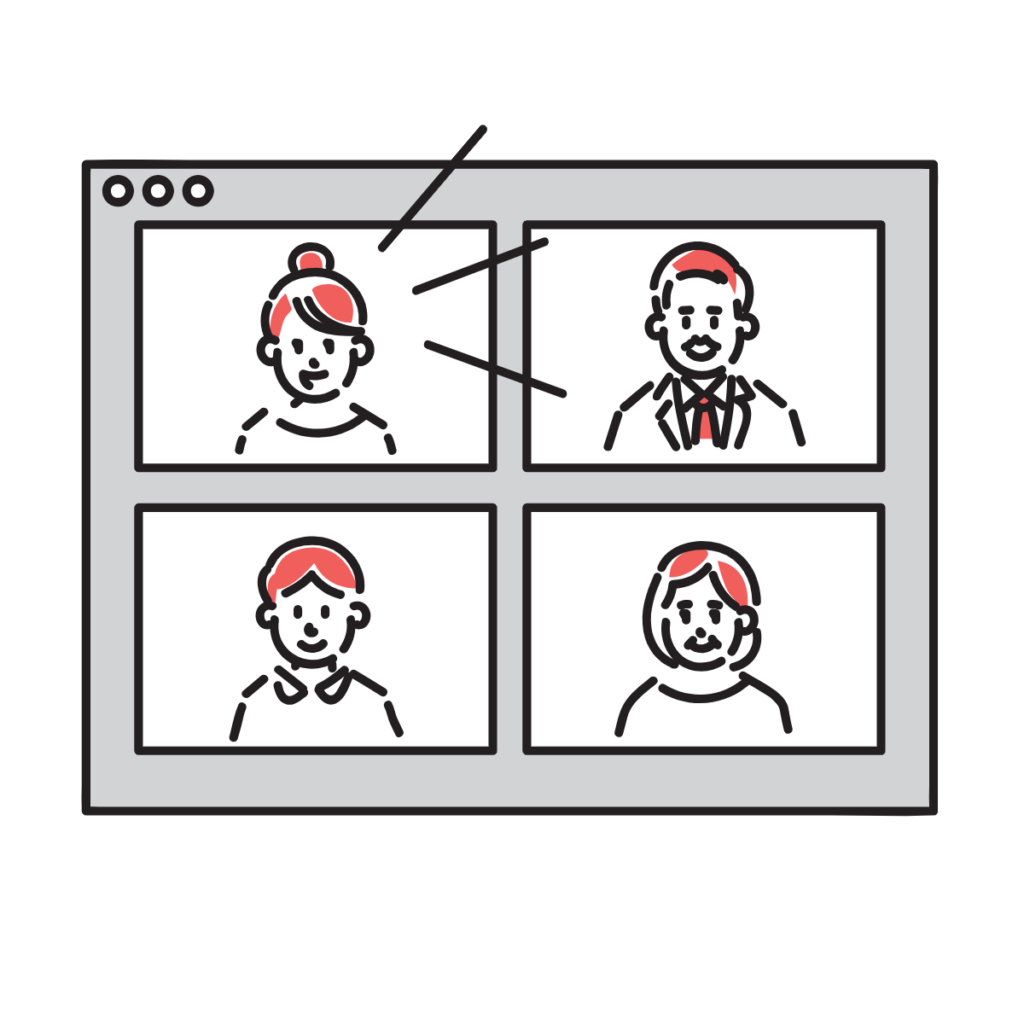
「業務をこなす人」から、「業務を変える人」へとソフトしていきましょう。
これは、総務が“裏方”から“仕組みづくりの担い手”へと進化するための第一歩です。
たとえば、
- 備品管理のルールを見直して発注ミスを減らす
- 紙で行っていた申請フローをGoogleフォームに切り替える
といった改善は、すべて“仕組みを変える”行動です。
日常の中にある「なんとなく不便」を見逃さず、「それ、変えられるかも?」と提案できる人は、AI時代でも重宝されます。
総務が生き残るためのキャリア戦略④|マネジメント職を目指す
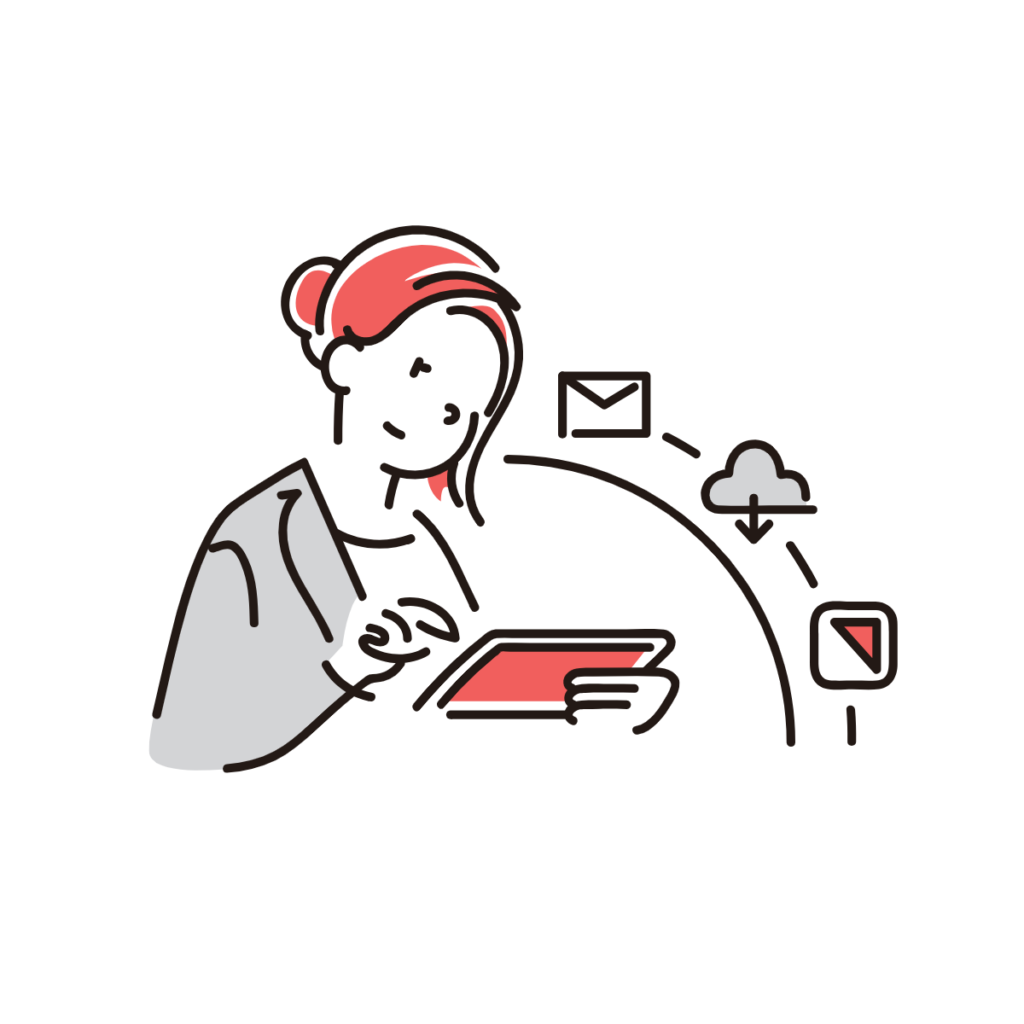
総務としてキャリアを積む中で、マネジメントへのステップアップを視野に入れることも選択肢のひとつです。
社内ルールや環境整備に精通しているからこそ、「組織全体をどう動かすか」「どのようにメンバーの力を引き出すか」を考える立場に進むことは自然な流れとも言えます。
管理職としての視点を持つためには、業務を俯瞰して見る力や、他部門との交渉力、社内外との信頼構築力が求められます。
現場を知っているからこそできるマネジメントは、AIにはできない貴重な役割です。
総務が生き残るためのキャリア戦略⑤|総務としての専門性を深める

総務の仕事は“広く浅く”と思われがちですが、実は「広く×深く」へのシフトが可能です。
たとえば、以下のような分野において、専門性を磨くことができます。
- オフィス環境の設計や安全衛生管理のプロ
- 社内コミュニケーションの最適化・社内報運営
- コンプライアンス整備や危機管理対応の支援役
“誰でもできる”から“自分だからできる”仕事へとシフトしていきましょう。
総務ならではの経験を、「再現性のあるスキル」として言語化・体系化していくことが、専門性につながります。
総務が生き残るためのキャリア戦略⑥|隣接職種へのキャリアチェンジ
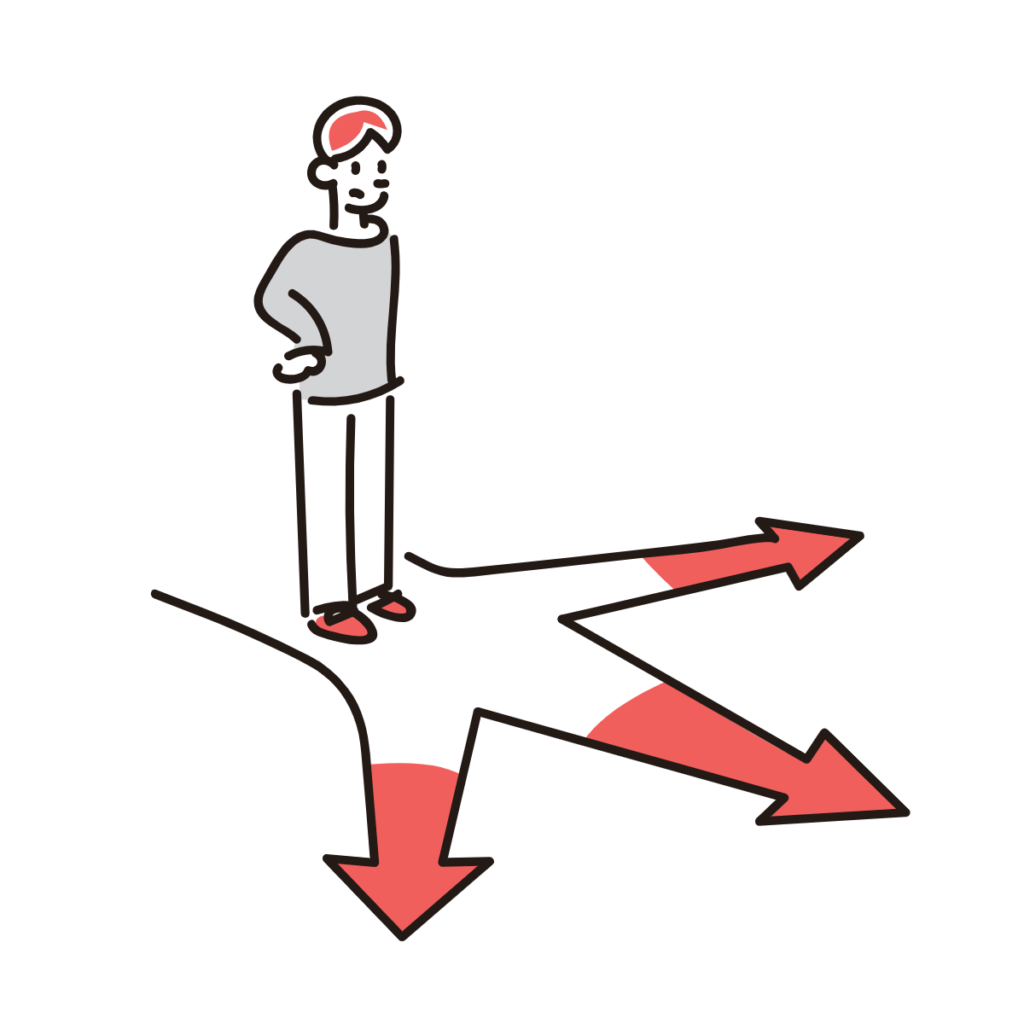
一方で、総務での経験を土台に、隣接する専門職へキャリアチェンジする道もあります。
例えば…
- 契約書チェックや文書管理に携わっていた → 法務職へ
- 勤怠管理や就業規則の運用を担当していた → 労務職へ
- 会社の行事やイベント企画の運営経験 → 広報・採用・総務企画職へ
いずれも、総務で培った「段取り力・事務処理能力・全体を見る力」が大きな強みになります。
AIでは補えない“人の視点”と“社内実務の知見”を活かし、「社外でも通用する専門性」を手に入れる選択肢として、有効なステップです。
AI時代に必要な総務人材のスキルアップ3つ
理想とするキャリアへと近づくために、今日から実践できる総務人材としてのスキルアップの方法を3つご紹介します。
総務人材のスキルアップ3つ
- 変化を受け入れ、学ぶ姿勢を持つ
- 副業や資格取得で選択肢を広げる
- 情報発信・社外とのつながりで視野を広げる
総務人材のスキルアップ①|変化を受け入れ、学ぶ姿勢を持つ

AIやデジタル技術の進化は止まりません。
だからこそ、「総務の仕事は変わるもの」と捉え、学び続ける柔軟性が必要です。
たとえば、ChatGPTやNotion AIのような生成AIを日常業務に取り入れると、案内文や社内メールの下書き、マニュアルの骨子作成が一気に効率化できます。
また、無料で使えるRPA(Power Automateなど)を試すことで、業務自動化の可能性を体感することもできます。
変化を拒むのではなく、少しずつ慣れる姿勢こそが、将来の自分を守る力になります。
総務人材のスキルアップ②|副業や資格取得で選択肢を広げる
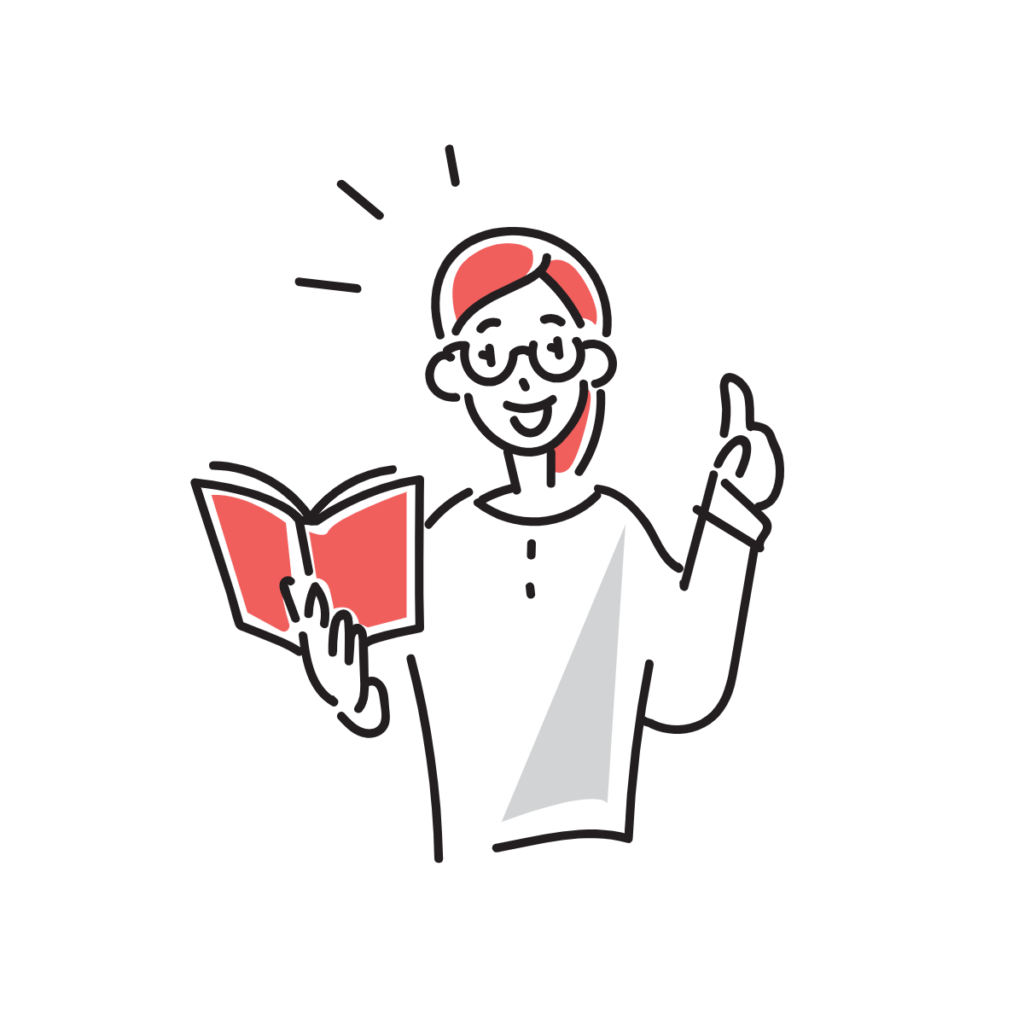
副業や資格取得は、会社の外にある視点を取り入れ、自立したキャリアを築く手段です。
たとえば副業では、スキルシェアサービス(ココナラ・タイムチケット等)で「事務代行」「採用支援」「議事録作成」などを経験してみることで、自分の市場価値を知るきっかけになります。
また、興味がある専門分野に関しては、以下のような資格取得を検討しても良いでしょう。
- 労務分野 → 社会保険労務士、衛生管理者
- 法務分野 → ビジネス実務法務検定
- オフィス環境整備 → ファシリティマネージャー など
副業と資格は、「やりたいことを試す」「専門性を高める」の両面で効果があるため、自分の強みや方向性を探るためのヒントにもなります。
総務人材のスキルアップ③|情報発信・社外とのつながりで視野を広げる

社内に閉じこもっていると、「自分の価値」がわからなくなることもあります。
だからこそ、社外との接点を持つことはとても重要です。
例えば、
- noteやX(旧Twitter)などで、自分の仕事について発信してみる
- オンラインセミナーや勉強会に参加してみる
- 同じ悩みを持つ人と交流するコミュニティに入ってみる
など、できることはたくさんあります。
情報収集の意味でも、人との出会いの面でも、社外の空気に触れることは視野を広げる大きなきっかけになります。
「今の会社がすべてではない」と気づけるだけでも、キャリアの選択肢は大きく広がるはずです。
総務の将来性が不安なら、「変化」を味方にすればよい(まとめ)

総務の仕事はなくなるかもしれない
そんな声に、不安を感じるのは当然のことです。
しかし、その不安の正体は、“なくなる仕事”への恐れだけでなく、変化にどう対応していいかわからない不安でもあるのではないでしょうか。
実際には、総務の仕事がすべてAIに取って代わられるわけではありません。
- 現場での柔軟な対応力
- 社内調整の力
- 目に見えない安心感を生み出す力
これらは、AIが苦手とする領域であり、人にしかできない仕事です。
だからこそ、今こそ「これまで通り」ではなく、「これからのあり方」を考えるタイミングです。
学びを止めず、業務を変える視点を持ち、自分の価値を言語化し、必要とされるフィールドを広げていく…
そんな一歩一歩の積み重ねが、AI時代にも埋もれない“選ばれる人材”をつくっていきます。
将来に不安を感じたら、それは“変化のサイン”かもしれません。
その変化を、どうかあなたの味方にしてください。

-1024x1024.png)